1.まずは、本音とその周辺
 ♣
♣つい最近、一人の高校生が、なんかの話の折に竹村建一の話がでたとき、
「あの人キライや」といったんです。
少し前にも、友禅の型彫りをやっている大分昔の教え子が一緒に飲んでいる時に、やっぱりおんなじようなニュアンスで、「どうも感覚的に好きになれん」というのを聞いていました。
ぼく自身は、べつにキライでもない。
で、ぼくは、おんなじことを二回も続けてきいたこともあって、気になり、その高校生に、
「なんでキライやねん」と、たずねました。
「だいたい本音をはっきりいいすぎるみたい。そしてそれを人に押しつけすぎる」
「商売でもなんでも、あんまりはっきりいうと、自分の手の内を見せることになるし、うまくないでしょう」
それはなんかちょっとちがう、とぼくは思いました。そういうやり方ができるのは、狭い社会集団の中で、お互いに何となく分りあえる場合だけではないか。はっきりせんと損する場合もある。ぼくがそういう風に反論すると、彼は、なお淡々と、
「やっぱり本音とたて前は使い分けんとあかんと思いますよ。本音ばかりでは世の中うまくいかんでしょう。大平さんだって、アメリカ行って、本音はいうてませんよ」
ぼくは、「う−ん」と唸りました。
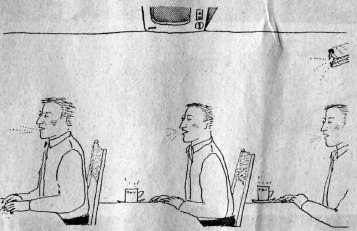 一つには、この頃のお行儀のよい、ちょっとアホみたいにみえる生徒の胸の中には、大人が想像もしない明晰なというかセコイというか、とにかくある見通しと割り切りがあると、少しは否定的に推定していたことが、ズバリ当ったような気がしたこと。もう一つには、どっちかといえば、「本音人間」に属するぼく自身、なんか合口を突きつけられたような気がした。さらには、今の学校は、やはりこういう若者を生みだすのか、といまさらのように思いました。そんないろんな理由で、ぼくは絶句したんだと思うのです。
一つには、この頃のお行儀のよい、ちょっとアホみたいにみえる生徒の胸の中には、大人が想像もしない明晰なというかセコイというか、とにかくある見通しと割り切りがあると、少しは否定的に推定していたことが、ズバリ当ったような気がしたこと。もう一つには、どっちかといえば、「本音人間」に属するぼく自身、なんか合口を突きつけられたような気がした。さらには、今の学校は、やはりこういう若者を生みだすのか、といまさらのように思いました。そんないろんな理由で、ぼくは絶句したんだと思うのです。もちろん、人には好き嫌いがいろいろあって当然の話です。事実、その時、そばにいた別の高校生の一人は、「ワシは好きや」といい、その本音・たて前使い分け論の高校生に「お前会社入ったら出世するワ」とコメントしました。それだけで、しまい。絶対議論にはなりません。これが現代の風潮というのか。お互いに分りあっていて、決して争わない。十年前は、こんなものではありませんでした。口角泡をとばす議論が始まったものです。今の高校生は大人になったと単純に喜ぶべきなのでしょうか。
ぼく自身、普通の時なら、もっとひつこく議論をいどんだと思うんです。でも、もうこの原稿をせっつかれている時でした。へたにやり合うと、混乱をきたして原稿書けんようになるかも知れん。反射的に、そんなビビリがきました。
まあ、ぼくが、突っかけても、今日びの若者の彼は、まず乗ってこなかったとは思うのですが‥‥‥。
それにしても、もう大分前の『山と渓谷』という雑誌の特集グラビア「高田直樹の山とその周辺」のうちの酒のんでる写真のキャプションに、〈談論風発、竹村建一ばりに何でもズバズバいう〉と書かれたぼくとしては、少々気になるやりとりではあったのです。
♣♣
あの『山と渓谷』の特集グラビア「高田直樹の山とその周辺」は、もう何年も前のことです。
ぼくは、さらに遡ること三年前から、その山の雑誌に連載をやっていました。「なんで山登るねん」。そういうケッタイなタイトルの、なんていえばいいのか、まあ強いていえばエッセイみたいな文章を書いていたのです。
最初は一年位という話だったのですが、読者からの反響がけっこうすごくて、とうとう三年間書き続ける破目になりました。そして、その最終回に、いまいった特集グラビアがあったという訳。
すぐ、この三年分の連載をまとめて、『なんで山登るねん』が出ました。これがまた、どういう訳か、すごく売れたのです。出版五日目に売切れ、重版ということで、担当のセツダさんは、
「社はじまって以来じゃないですか。大変なことなんですよ」
と、ぼくに電話してきました。
「よかったですね。二人とも、運がよかったんですよ」
と、ぼくがいうと、彼はすかさず、
「いやいや、運も才能のうちですよ」
といったものです。
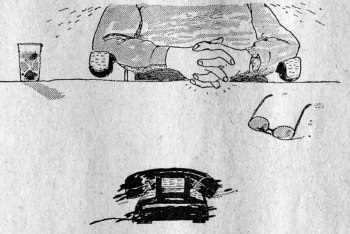 さて、本が売れ続けたのはよかったのですが、ぼくの内面はちょっと苦しくなりました。ずっと前から、ぼくには、山登りの世界では、本をだすと、そいつは駄目になるというある固定観念があったようなんです。それと、この「ぐうたら登山のすすめ」みたいな本を読んだ読者が想像するぼくは、多分、ぼくのほんの一部分にすぎない、という気もしました。
さて、本が売れ続けたのはよかったのですが、ぼくの内面はちょっと苦しくなりました。ずっと前から、ぼくには、山登りの世界では、本をだすと、そいつは駄目になるというある固定観念があったようなんです。それと、この「ぐうたら登山のすすめ」みたいな本を読んだ読者が想像するぼくは、多分、ぼくのほんの一部分にすぎない、という気もしました。なんか一発、すごい山登りをせないかん。そういう強迫観念にとらわれ始めた訳です。だいたいぼくは、その時までに、五回の海外遠征登山をやっていたのですが、成功したのは二回だけ。おまけに、それも初登頂ではなかったのです。
それで、ぼくが選んだ山は、勝手知ったカラコルムのラトックⅠ 峰という7100米少しのすごい岩ばっかりの未踏峰でした。この山には、これまでに日本や外国の登山隊四隊が挑んで、みんな失敗していました。「極限の山」とも「攀れるはずがない山」ともいわれていたんです。ぼくは、隊員を集め始めました。一九七八年の秋口のことでした。最優秀と思われる登山家に日本国中電話して誘ったのです。そんなやり方は、誰もやったことはなかったのですが、すぐにメンバーが揃いました。なにしろ目標の山がよかった。優れた登山家ほど困難をめざすものなのです。
でも隊員はみんな、所属するクラブが異なる、いわば寄合い世帯です。これまで、そうした混成パーティが成功した例は、まだ一つもなかった。
巷では、タカダ隊は、キャラバンの途中で空中分解するといわれていたそうですし、だんだん尾鰭がついて、成田空港で大ゲンカ、ということになっていたんだそうです。
♣♣♣
ちょうど、その頃、同じ出版社から『なんで山登るねん』の続編を書いてほしいという依頼がありました。そういう話は、この本が出た直後にもありました。一年後位に出したい。ぼちぼち初めてほしい、などといわれていたんです。でも、ぼくは、あんなんは、あれ切りや、そう思っていました。
でも、「ラトックにはお金いるでしょう。出しますから。時間がなくなったら、ホテルに入ってもらいますから」とまで云われると、いやする訳にもいかなくなった。
ぼくは、遠征出発前の忙がしい毎日を、グランドホテルから通勤しながら、『続なんで山登るねん』を、一気に書きました。
「こんども売れますかねえ」
と、ぼくがいうと、セツダさんは、
「大丈夫でしょう。ナオキの星は、まだ輝いているようですから」
ラトックⅠ峰の遠征準備が、大詰めに近づき、メンバーは、個人ボックスを梱包し、その箱に、自分の名前と一緒に勝手な落書きをしました。ある隊員は「やるぞ」と書き、別の隊員は、Try onと書いた。恋人の名前を書いた奴もいたようです。
 ぼくは、成功しますようにというはかない願いを込めて、でもみんなに分らないようにウルドー語で〈ラトックにナオキの星を〉と書いたのです。ほんとの話、ぼくは成功するとは思ってなかった。万に一つ成功するかも知れない。なんとかやってやろうと思っていただけなんです。
ぼくは、成功しますようにというはかない願いを込めて、でもみんなに分らないようにウルドー語で〈ラトックにナオキの星を〉と書いたのです。ほんとの話、ぼくは成功するとは思ってなかった。万に一つ成功するかも知れない。なんとかやってやろうと思っていただけなんです。ところが、驚いたことに、ラトックは成功した。それも、六人ものメンバーが登頂するという大成功を収めた訳です。
当事者のぼくが驚いた位ですから、巷の「空中分解説」を信じていた連中は、もっとびっくりしたことでしょう。
友人のスポーツ誌の記者は、ぼくが東京に帰り着いた時、酒に酔った勢いでか、
「タカダセンセイ、申し訳ない。ぼくは失敗すると思ってました」
そういうと、飲み屋の土間に土下座しようとした。いや、びっくりしました。
ぼくの周りは俄然、騒やかになりました。色んな新聞などから取材の申し込みがあり、外国からの原稿依頼や、講演の依頼も増えました。ある全国紙の婦人部が、「現代のいい男」という特集に登場するよう頼んできたりして、ぼくは、ほんとに疲れました。
春先になって、少しは静かになったと思っていたら、この原稿の依頼があったという訳です。
ぼく自身、『なんで山登るねん』が、山登りの人達だけに売れているのではないことは分っていたし、家庭の主婦や、若者は、全然ちがう読み方をしていることも、何となく人から聞き知ってはいました。だから、「教育論を‥‥‥」という依頼は分らぬではなかった。
でも、考えてみるまでもなく、ぼくは教育論が書けるようなご立派な教師ではありません。困ったなあ。けれどよく考えれば、ぐうたら教師の教育論もおもろいんではなかろうか。まあなんとかサマになるのかも知れん。そんな気もしました。