- HOME Archives: August 2007
20.便りのないのが無事の便り
♣
ある秋の深い目の放課後のことでした。ぼくは、何の用事もないし、そうかといって家に帰るのも何となくじゃまくさいといった気分で、ただぼんやり椅子にだらしなく腰かけ、窓ごしに見える空を見あげていました。
 その時、建てつけの悪くなった戸がゴトゴトと開き、卒業生のCちゃんが入ってきました。何とも陰欝な顔つきです。彼女は、在学中に何度か、山岳部の主催するスキー講習会には参加していましたし、一回きりぼくが顧問になった時の「社研」の部長だったりで、ぼくはかなりよく知っていました。たしか、彼女、浪人中のはずでした。「どうや、元気」というぼくの言葉を無視して、Cちゃんは、
その時、建てつけの悪くなった戸がゴトゴトと開き、卒業生のCちゃんが入ってきました。何とも陰欝な顔つきです。彼女は、在学中に何度か、山岳部の主催するスキー講習会には参加していましたし、一回きりぼくが顧問になった時の「社研」の部長だったりで、ぼくはかなりよく知っていました。たしか、彼女、浪人中のはずでした。「どうや、元気」というぼくの言葉を無視して、Cちゃんは、
「センセ、バイク乗せてくれへん」
と、か細い声でいいました。
ぼくは一瞬とまどい黙っていました。ちょっと真意を計りかねたのです。彼女は、ぼくが、めったに人をバイクに乗せたりはしないことを知っているはずでした。
三〇半ばを過ぎてからバイクに熱中した、あの当時、たしか、女の子をのっけて、走ったことはありました。
ぼくのイメージとしては、ぼくが乗せる女の子は髪の毛が長くないといけない。その女の子の髪の毛は、バイクの疾走と共に真直ぐに後になびかなければならない。でも、髪が長かったら誰でもいいという訳じゃありません。バイクに乗せるというのは、乗用車に乗せるというのとは、全然ちがいます。身体が何となく接触するし、胴に手を回されるのが普通です。かなり親近感がないと、くすぐったいし、気色悪いんです。
まあ、とにかく、そうした女の子が、うまい具合にいて、乗せてくれというので走りました。ショーウィンドーの前を走り過ぎながら、チラッと見たら、イメージに全く反して、髪の毛は、全然なびいていないのです。ただバサバサと乱れているだけでした。なんとも、ぼくばガッカリしたのでした。
さて、Cちゃんは、ぼくが黙っているので、じっと返事を待っている風でしたが、
「もうかなり参ってるの」
とポツリといいました。多分、受験勉強に疲れているのでしょう。
うっとしいなあ。ぼくはユーウツな感じだったのですが、なんだか、彼女の気迫に押されていました。「ワシ、髪の毛の長い奴しか乗せへんねん」などという冗談でごまかす訳にも行かぬ感じで、大分考えてから、ぼくは「よっしゃ」と答えていました。
校門から走り出ると、ぼくは、真直ぐに、西を目指しました。別にどこへというあてもありません。ただその時、秋の入日が西山に傾きつつあり、それがとてもキレイだったからです。
引返してきたとき、もう夕暮れがあたりを包み、秋の空は、物哀しい色でした。Cちゃんは、
「センセ、ありがと。スッとした」
とだけいって、自転車で帰ってゆきました。
♣♣
何年かたった一九七五年、ぼくは、カラコルムのラトックⅡ峰を攀りにゆくことになりました。この山を狙ったのは、登攀倶楽部というクライマーの集団でした。彼等は、ほとんどみんな、大学には行ってない連中で、いわゆるブルーカラーに属していました。でも、その攀り方は、大学山岳部の奴等とは比較にならない位、尖鋭的なものでした。
例えば、土曜日の午後、単身バイクに乗って穂高に向かい、ほとんど眠らず、そのまま数百米の岩壁の困難なルートを攀り、またバイクで走って日曜日の朝に帰ってくるというようなことをケロリとやってのけるといったものでした。
「五条坂クラブ」とかいう名前のバイク集団を作って、五条通りで白バイと追いかけっこをしているような奴もいました。また、四帖半の安アパートで、インスタントラーメンで飢えをしのぎながら、力仕事のアルバイトをして、金がたまると山へ出掛ける。「山ではまともなメシが食えるところが魅力です」などと冗談をいったりする彼等は、岩壁に張りつくと、見事なまでのテクニックとパワーを見せたものです。
若い頃から、どちらかといえば、恵まれた環境条件の中で、のんびりと山登りを楽しんできたともいえるぼくにとって、彼等の生きざまや山登りは驚異的に思えました。そして同時に何ともいえぬ新鮮さと魅力を感じたのも事実でした。頼まれるままに、彼等の雇われ隊長となるのを承知したのは、多分、こうした気分のせいだったと思います。
遠征準備の事務所というか、集会や物資集積や梱枹場所として、ぼくは古巣である大学山岳部の部室を使うことにしました。そこなら、昼夜を問わず自由に使えるし、寝泊りもできます。「山岳部ルーム」の隣りの部屋には数人の女子学生がいました。ぼくは、その中にCちゃんを見出したのでした。
「よお、久しぶりやな。これなに部やねん」
彼女が、志望通り大学に入って、ぼくの後輩ということになったということは聞いていました。でも、こんな所にいるとは思わなかった。この部屋は、「ジョモンケン」のボックスなのだそうです。
「それなんや」
ああそうか。女性問題研究会か。「女問研」てケッタイな名前やなあ。なんでも、いまは、どこの大学にも「女問研」があるのだそうです。そういえば、巷では榎美沙子がガンバッていました。
とにかく、もと「バロック音楽研究会」のボックスだったのを、女の力で乗っ取ったとかいう、このステレオもあるかなり快適な部屋を、ぼくは、遠征準備のための別室として使えることになったのです。
♣♣♣
Cちゃんは、このウーマンリブ・グループのリーダーでした。でも、彼女の温和で、どちらかというと内向的な性格を反映してか、この「女問研」は、他所の大学のそれとはちがい、極めて穏健だとのことでした。大してこれといった活動はせず、高群逸枝の『日本女性史』の輪読会などをやっているそうでした。「助言者として参加して下さい」などといわれ、好奇心の強いぼくは、「うん」と答えたのですが、遠征隊の準備に追われて、その機会はありませんでした。
この部屋でぼくが出会った「女問研」の面々は、やっぱり何となく、普通の女子大生とはちがうように感じました。キャアキャアワァワァいっている並の女子学生ともちがうし、あどけなさと幼稚さが売物みないな女性とは別物という感じでした。口数少なく、キリッとしていて、シャキッとした筋金入りみたいで、おまけに、それがわりかし整った顔立ちであったりしたら、ぼくは、年甲斐もなく、なんだかボーとしてしまい、ちょっとした少年のあこがれみたいな心情を覚えていたようでした。
さて、二ヶ月ほどの準備の後、ぼくは、パキスタンの高峰に向かい、失敗して帰ってきました。帰国してしばらくして、もう秋の気配の濃いある日、Cちゃんが学校に電話をかけてきました。例によって藪から棒です。
「センセ、ちょっと相談があるんですけど」
「元気か、ほんで、何ですか」
「あのう……。女問研の○○さんがドジったんです」
「はあ。何をです」
いきなりドジッたといわれても、何のことかも分らず、ぼくはポカンとして、全く要領を得ぬ返事をしていました。
「ほら、センセ、知ったはるでしょ。あの人、ステキやっていうたはった人」
ぼくには、まだはっきりしません。彼女にそんなこというたかな、と考えていました。
「あのう、ボーイフレンドと、それで失敗して……」
「ふうん」とだけ答えて、ぼくは絶句していました。別にうろたえもしなかったけれど、なんだか、事務室のみんなが、きき耳をたてているような気がしました。
「なるほど。分った。夜、家に電話してくれませんか」
さり気なくそういって、ぼくは電話を切ったのです。
やっぱり、ぼくは少しびっくりしていました。考えてみれば、そういうこともあって当然という話なのですが、なんだか、起こり得べからざることが起こったという気がしたのです。
並の女子大生ならいざ知らず、「女問研」の、あの女の子が……。全く信じられんという気分で、ぼくは化学準備室への廊下を歩いていました。と同時、何ともややこしい話を持ち込んできたCちゃんに、あるうとましさを感じていました。
♣♣♣♣
夜かかってきた電話で話を詳しく聞いているうちに、ぼくはムカムカ腹が立ってきました。当の本人はただオロオロとうろたえているだけだそうです。おまけに、なんだか、相手の男だけが悪いみたいないい方をしているようです。
「わたしらも、なんかほっとく訳にもゆかんという気がして……」
ぼくは、とうとう頭にきてしまい、
「アホか、自分の身体のことも自分でめんどうみれんと、なにが女性の権利じゃ。ええ年して、中学生みたいなこというとるな」
と怒鳴ってしまいました。しかし、考えてみれば、あの遠征のときには、色々手助けしてもらったことだし、ぼくにも少々の義理はありそうです。俺の知ったことかと、つっぱねる訳にもゆかんなあ。そんな気がしました。
ぼくは、直ぐ、遠征隊のドクターであった山岳部の後輩のタカヒコに電話したんです。
「へええ、そら困ったな。けど、それ、相手はタカダはんとちがうんかいな」
「バカモン」
ぼくはますますムカムカしました。
「そらね、あんなもん、盲腸の手術よりも簡単やということもできますよ。けど、盲腸とはやっぱりちがうんですワ」
と、タカヒコはいい、「なんとか考えたってえな」というぼくの頼みに、
「困ったなあ、そらぼくとこの病院へ来てもろたら、話は簡単ですねん。けど、ワシかて、看護婦に、変に疑われるのイヤですしねえ」
と答え、ここで、ぼくたちは、一緒に笑ったのです。
とにかく「なんとかええとこを探します」といってもらい、ようやくぼくはホッとし、女房に、ちょっと話したのです。すると彼女は、
「それ、パパとちがうの、相手」
「アホか」
ぼくは滅入ってしまったのでした。
しばらくして、一件落着の連絡が入りました。「女問研」の学生ということで、誰しもピンク・ヘルを連想したらしく、場所さがしはかなり難航したようでした。ところが、あんなうっとおしい話を持込んできた当のCちゃんからは、何の連絡もありませんでした。けっこう腹がたちました。もう話なんかするか、とも思いました。でも正直いって、ぼく自身も、そんなこと早く忘れたかったのです。
一年ほどして、ひょっこり、もう忘れた頃に、Cちゃんが学校にやってきました。
あれから、なかなか大変だったようです。まずお父さんがなくなった。教師だったお父さんは、冬は元気にスキーをしていたのに、春には入院し、ガンが脳に転移したため、記憶喪失みたいになり、死の床につきそう娘に、つきそってくれてうれしいが早く帰らないとお父さんが心配するよ、などといったそうです。父親が入院するのとほとんど同時に母親も入院した。胃潰瘍の手術はすぐに済んで、元気に退院したのですが、これもホントはガンだったのだそうです。それを知っているのはCちゃんだけです。
こういうややこしい話になると、彼女は、ほとんど毎日のようにぼくの所にやってきては、ポツリポツリと話しては帰ります。聞いてしまったぼくの方は、ほんとにつかれる感じなのです。
何日目かに、彼女は、こう話しました。
「お父さんには好きな人がいたみたい。入院してから分ったん。お母さんには、生徒の母親やいうてたけど……。その女の人私のこと小さいときから知ってるみたいな態度なんよ」
その人には高校生の娘がいるそうです。Cちゃんはそれが気がかりな様子で何度もこの話をするので、ぼくはからかい半分に、
「その高校へ行って、その娘見てきたら……。あんたに、よう似てたりして」
というと、彼女は、常になくキッとして、「お父さんが好きな女性がいくらいても、それはそれやけど、私とおんなじように可愛いがってる娘が他にいると想像することは耐えられないことなん」
あれから、もう何年にもなります。その後彼女からは何の連絡もありません。便りがないのが無事の便り……。きっと元気でやっているのだろう。ぼくはそう思っています。
ある秋の深い目の放課後のことでした。ぼくは、何の用事もないし、そうかといって家に帰るのも何となくじゃまくさいといった気分で、ただぼんやり椅子にだらしなく腰かけ、窓ごしに見える空を見あげていました。
 その時、建てつけの悪くなった戸がゴトゴトと開き、卒業生のCちゃんが入ってきました。何とも陰欝な顔つきです。彼女は、在学中に何度か、山岳部の主催するスキー講習会には参加していましたし、一回きりぼくが顧問になった時の「社研」の部長だったりで、ぼくはかなりよく知っていました。たしか、彼女、浪人中のはずでした。「どうや、元気」というぼくの言葉を無視して、Cちゃんは、
その時、建てつけの悪くなった戸がゴトゴトと開き、卒業生のCちゃんが入ってきました。何とも陰欝な顔つきです。彼女は、在学中に何度か、山岳部の主催するスキー講習会には参加していましたし、一回きりぼくが顧問になった時の「社研」の部長だったりで、ぼくはかなりよく知っていました。たしか、彼女、浪人中のはずでした。「どうや、元気」というぼくの言葉を無視して、Cちゃんは、「センセ、バイク乗せてくれへん」
と、か細い声でいいました。
ぼくは一瞬とまどい黙っていました。ちょっと真意を計りかねたのです。彼女は、ぼくが、めったに人をバイクに乗せたりはしないことを知っているはずでした。
三〇半ばを過ぎてからバイクに熱中した、あの当時、たしか、女の子をのっけて、走ったことはありました。
ぼくのイメージとしては、ぼくが乗せる女の子は髪の毛が長くないといけない。その女の子の髪の毛は、バイクの疾走と共に真直ぐに後になびかなければならない。でも、髪が長かったら誰でもいいという訳じゃありません。バイクに乗せるというのは、乗用車に乗せるというのとは、全然ちがいます。身体が何となく接触するし、胴に手を回されるのが普通です。かなり親近感がないと、くすぐったいし、気色悪いんです。
まあ、とにかく、そうした女の子が、うまい具合にいて、乗せてくれというので走りました。ショーウィンドーの前を走り過ぎながら、チラッと見たら、イメージに全く反して、髪の毛は、全然なびいていないのです。ただバサバサと乱れているだけでした。なんとも、ぼくばガッカリしたのでした。
さて、Cちゃんは、ぼくが黙っているので、じっと返事を待っている風でしたが、
「もうかなり参ってるの」
とポツリといいました。多分、受験勉強に疲れているのでしょう。
うっとしいなあ。ぼくはユーウツな感じだったのですが、なんだか、彼女の気迫に押されていました。「ワシ、髪の毛の長い奴しか乗せへんねん」などという冗談でごまかす訳にも行かぬ感じで、大分考えてから、ぼくは「よっしゃ」と答えていました。
校門から走り出ると、ぼくは、真直ぐに、西を目指しました。別にどこへというあてもありません。ただその時、秋の入日が西山に傾きつつあり、それがとてもキレイだったからです。
引返してきたとき、もう夕暮れがあたりを包み、秋の空は、物哀しい色でした。Cちゃんは、
「センセ、ありがと。スッとした」
とだけいって、自転車で帰ってゆきました。
♣♣
何年かたった一九七五年、ぼくは、カラコルムのラトックⅡ峰を攀りにゆくことになりました。この山を狙ったのは、登攀倶楽部というクライマーの集団でした。彼等は、ほとんどみんな、大学には行ってない連中で、いわゆるブルーカラーに属していました。でも、その攀り方は、大学山岳部の奴等とは比較にならない位、尖鋭的なものでした。
例えば、土曜日の午後、単身バイクに乗って穂高に向かい、ほとんど眠らず、そのまま数百米の岩壁の困難なルートを攀り、またバイクで走って日曜日の朝に帰ってくるというようなことをケロリとやってのけるといったものでした。
「五条坂クラブ」とかいう名前のバイク集団を作って、五条通りで白バイと追いかけっこをしているような奴もいました。また、四帖半の安アパートで、インスタントラーメンで飢えをしのぎながら、力仕事のアルバイトをして、金がたまると山へ出掛ける。「山ではまともなメシが食えるところが魅力です」などと冗談をいったりする彼等は、岩壁に張りつくと、見事なまでのテクニックとパワーを見せたものです。
若い頃から、どちらかといえば、恵まれた環境条件の中で、のんびりと山登りを楽しんできたともいえるぼくにとって、彼等の生きざまや山登りは驚異的に思えました。そして同時に何ともいえぬ新鮮さと魅力を感じたのも事実でした。頼まれるままに、彼等の雇われ隊長となるのを承知したのは、多分、こうした気分のせいだったと思います。
遠征準備の事務所というか、集会や物資集積や梱枹場所として、ぼくは古巣である大学山岳部の部室を使うことにしました。そこなら、昼夜を問わず自由に使えるし、寝泊りもできます。「山岳部ルーム」の隣りの部屋には数人の女子学生がいました。ぼくは、その中にCちゃんを見出したのでした。
「よお、久しぶりやな。これなに部やねん」
彼女が、志望通り大学に入って、ぼくの後輩ということになったということは聞いていました。でも、こんな所にいるとは思わなかった。この部屋は、「ジョモンケン」のボックスなのだそうです。
「それなんや」
ああそうか。女性問題研究会か。「女問研」てケッタイな名前やなあ。なんでも、いまは、どこの大学にも「女問研」があるのだそうです。そういえば、巷では榎美沙子がガンバッていました。
とにかく、もと「バロック音楽研究会」のボックスだったのを、女の力で乗っ取ったとかいう、このステレオもあるかなり快適な部屋を、ぼくは、遠征準備のための別室として使えることになったのです。
♣♣♣
Cちゃんは、このウーマンリブ・グループのリーダーでした。でも、彼女の温和で、どちらかというと内向的な性格を反映してか、この「女問研」は、他所の大学のそれとはちがい、極めて穏健だとのことでした。大してこれといった活動はせず、高群逸枝の『日本女性史』の輪読会などをやっているそうでした。「助言者として参加して下さい」などといわれ、好奇心の強いぼくは、「うん」と答えたのですが、遠征隊の準備に追われて、その機会はありませんでした。
この部屋でぼくが出会った「女問研」の面々は、やっぱり何となく、普通の女子大生とはちがうように感じました。キャアキャアワァワァいっている並の女子学生ともちがうし、あどけなさと幼稚さが売物みないな女性とは別物という感じでした。口数少なく、キリッとしていて、シャキッとした筋金入りみたいで、おまけに、それがわりかし整った顔立ちであったりしたら、ぼくは、年甲斐もなく、なんだかボーとしてしまい、ちょっとした少年のあこがれみたいな心情を覚えていたようでした。
さて、二ヶ月ほどの準備の後、ぼくは、パキスタンの高峰に向かい、失敗して帰ってきました。帰国してしばらくして、もう秋の気配の濃いある日、Cちゃんが学校に電話をかけてきました。例によって藪から棒です。
「センセ、ちょっと相談があるんですけど」
「元気か、ほんで、何ですか」
「あのう……。女問研の○○さんがドジったんです」
「はあ。何をです」
いきなりドジッたといわれても、何のことかも分らず、ぼくはポカンとして、全く要領を得ぬ返事をしていました。
「ほら、センセ、知ったはるでしょ。あの人、ステキやっていうたはった人」
ぼくには、まだはっきりしません。彼女にそんなこというたかな、と考えていました。
「あのう、ボーイフレンドと、それで失敗して……」
「ふうん」とだけ答えて、ぼくは絶句していました。別にうろたえもしなかったけれど、なんだか、事務室のみんなが、きき耳をたてているような気がしました。
「なるほど。分った。夜、家に電話してくれませんか」
さり気なくそういって、ぼくは電話を切ったのです。
やっぱり、ぼくは少しびっくりしていました。考えてみれば、そういうこともあって当然という話なのですが、なんだか、起こり得べからざることが起こったという気がしたのです。
並の女子大生ならいざ知らず、「女問研」の、あの女の子が……。全く信じられんという気分で、ぼくは化学準備室への廊下を歩いていました。と同時、何ともややこしい話を持ち込んできたCちゃんに、あるうとましさを感じていました。
♣♣♣♣
夜かかってきた電話で話を詳しく聞いているうちに、ぼくはムカムカ腹が立ってきました。当の本人はただオロオロとうろたえているだけだそうです。おまけに、なんだか、相手の男だけが悪いみたいないい方をしているようです。
「わたしらも、なんかほっとく訳にもゆかんという気がして……」
ぼくは、とうとう頭にきてしまい、
「アホか、自分の身体のことも自分でめんどうみれんと、なにが女性の権利じゃ。ええ年して、中学生みたいなこというとるな」
と怒鳴ってしまいました。しかし、考えてみれば、あの遠征のときには、色々手助けしてもらったことだし、ぼくにも少々の義理はありそうです。俺の知ったことかと、つっぱねる訳にもゆかんなあ。そんな気がしました。
ぼくは、直ぐ、遠征隊のドクターであった山岳部の後輩のタカヒコに電話したんです。
「へええ、そら困ったな。けど、それ、相手はタカダはんとちがうんかいな」
「バカモン」
ぼくはますますムカムカしました。
「そらね、あんなもん、盲腸の手術よりも簡単やということもできますよ。けど、盲腸とはやっぱりちがうんですワ」
と、タカヒコはいい、「なんとか考えたってえな」というぼくの頼みに、
「困ったなあ、そらぼくとこの病院へ来てもろたら、話は簡単ですねん。けど、ワシかて、看護婦に、変に疑われるのイヤですしねえ」
と答え、ここで、ぼくたちは、一緒に笑ったのです。
とにかく「なんとかええとこを探します」といってもらい、ようやくぼくはホッとし、女房に、ちょっと話したのです。すると彼女は、
「それ、パパとちがうの、相手」
「アホか」
ぼくは滅入ってしまったのでした。
しばらくして、一件落着の連絡が入りました。「女問研」の学生ということで、誰しもピンク・ヘルを連想したらしく、場所さがしはかなり難航したようでした。ところが、あんなうっとおしい話を持込んできた当のCちゃんからは、何の連絡もありませんでした。けっこう腹がたちました。もう話なんかするか、とも思いました。でも正直いって、ぼく自身も、そんなこと早く忘れたかったのです。
一年ほどして、ひょっこり、もう忘れた頃に、Cちゃんが学校にやってきました。
あれから、なかなか大変だったようです。まずお父さんがなくなった。教師だったお父さんは、冬は元気にスキーをしていたのに、春には入院し、ガンが脳に転移したため、記憶喪失みたいになり、死の床につきそう娘に、つきそってくれてうれしいが早く帰らないとお父さんが心配するよ、などといったそうです。父親が入院するのとほとんど同時に母親も入院した。胃潰瘍の手術はすぐに済んで、元気に退院したのですが、これもホントはガンだったのだそうです。それを知っているのはCちゃんだけです。
こういうややこしい話になると、彼女は、ほとんど毎日のようにぼくの所にやってきては、ポツリポツリと話しては帰ります。聞いてしまったぼくの方は、ほんとにつかれる感じなのです。
何日目かに、彼女は、こう話しました。
「お父さんには好きな人がいたみたい。入院してから分ったん。お母さんには、生徒の母親やいうてたけど……。その女の人私のこと小さいときから知ってるみたいな態度なんよ」
その人には高校生の娘がいるそうです。Cちゃんはそれが気がかりな様子で何度もこの話をするので、ぼくはからかい半分に、
「その高校へ行って、その娘見てきたら……。あんたに、よう似てたりして」
というと、彼女は、常になくキッとして、「お父さんが好きな女性がいくらいても、それはそれやけど、私とおんなじように可愛いがってる娘が他にいると想像することは耐えられないことなん」
あれから、もう何年にもなります。その後彼女からは何の連絡もありません。便りがないのが無事の便り……。きっと元気でやっているのだろう。ぼくはそう思っています。
19.問題生徒はぼくのカウンセラー
♣
大阪のある一流ホテルから学校に電話がかかり、「おたくの生徒に、次のような名前の生徒おりますか」と、五人ほどの名前をあげたのです。調べるまでもなく、その名前は、みんな、教師の名前だった。これが、いわゆる「ホテル事件」の発端でした。そのホテルの説明によれば、ことのいきさつは、こんなことでした。
ある日、同志社の学生のなにがしと名乗って、予約電話がかかった。翌日、その学生達が現われると、それぞれの部屋に投宿した。彼等は、その夜、ホテル内のレストランやバーで飲み喰いし、もちろんサイソだけで、です。そして、多分夜が明けてからでしょうが、いずこともなく姿を消してしまった。喰い逃げ、泊り逃げという訳です。
ホテルはすぐ調べました。これといった手掛りがある訳ではなかったのですが、ただひとつ、彼等が、夜、市外通話をした電話番号が記録されていたのです。それがみんな京都だった。ホテルは、その電話番号をダイヤルし、「お宅には、大学生がおいでになりますか」とたずねました。すると、その三つ四つの電話先はほとんど大学生の子供はいなかったけれど、共通して、カツラ高校に行っている女子高生がいるということが分ったのです。
そういう訳で、学校に電話が掛ってきたということだったのです。
学校はすぐ調査を始め、女生徒達のつながりから、泊り逃げ生徒を割り出すのに、ほとんど時間はかかりませんでした。彼等はみんな、ごく普通の、どっちかといえば成績もよい方に属する生徒でした。もう十数年も前のことで、ぼくは、もう彼等の名前さえ憶えていません。
さて、この泊り逃げ計画を思いついたのはAでした。それも、全くの思いつきなのです。彼は、小さい頃から、父親に連れられて、ホテルに泊ることがよくあって、ホテルの仕組みに詳しくなりました。今とちがって、もう十年以上も前のその頃は、ホテルは、なんか特殊な所という感じだったようです。
彼は、友人達と学校の芝生でだべっている時、ホテルという所は、サインだけで飲み喰いできるし、その気にさえなれば、ただで泊れるはずだといったんです。
それを聞いていた連中の意見は二つに分れたそうです。いや、そら無理やで、という者と、彼がそういうからには、やれるのとちがうかな、というグループとに、です。無理や、いややれる、と議論しているうちに、もともと架空の話として楽しんでいたみたいなこの計画は、だんだんと現実株を帯びてきて、可能性をとなえるグループは真剣になったのです。
「よし、これを証明するためには、実際やってみるよりしかたない。やるぞ」そういうことになり、「やれる」グループから何人かがおりて、五人ほどが残ったのです。
♣♣
 生徒がなんらかの問題を起こした時には、その事実関係の取調べには担任があたるという規定があります。その内容は、補導委員会に報告され、五人の委員が、「生徒処置規定」に基づいて、生徒処置の原案を決めます。この会議には、生徒部長や担任はオブザーバーとして討議には参加できますが、票決権はありません。
生徒がなんらかの問題を起こした時には、その事実関係の取調べには担任があたるという規定があります。その内容は、補導委員会に報告され、五人の委員が、「生徒処置規定」に基づいて、生徒処置の原案を決めます。この会議には、生徒部長や担任はオブザーバーとして討議には参加できますが、票決権はありません。
この、生徒部が生徒処置の票決に参加できないという制度は、極めて異例の制度のようです。これは、生徒部(補導部あるいは指導部という名の所が多い)というところが、生徒を取り締まるのではなく、生徒の側に立って生徒指導の企画を行うという考え方を示したものです。
ほとんどの高校では、補導部というのは「学校警察」のように考えられているのですが、わがカツラ高校では、警察はなく、処罰機関として補導委員会がある。そういうことなのだと、ぼくは考えていました。京都教育というのが、ひところ有名で、他府県から、視察・見学の先生方が次々とやってきました。生徒部で、いまいったような仕組みを聞いて、
「へえ、変ってますねえ」とか「素晴らしい制度ですね」とかコメントしたものでした。
そういうことですから、この「ホテル事件」でも当然、それぞれの生徒の担任が取調べに当ることになります。ただ、問題生徒が、いくつかのクラスに分散していた場合には、担任の連絡係を兼ねて、生徒部の教師が、事情聴取に加わることになっていました。
それで、生徒部に属しており、カウンセラーみたいなことをやっていたぼくは、この係になった訳です。
ぼくが、カウソセリングというものに興味をもったのは、ずっと昔、学生時代にさかのぼるようです。山岳部のリーダーで少数精鋭主義を唱えてつっ走っていた頃が終り、リーダーを後輩にゆずり、OBとなって、「年寄り」みたいな立場になると、下級生の相談にいかに対応するかという問題に直面したからです。
この立場は、教師としてのぼくにも共通した状況ともいえました。ぼくは、カウンセリングの本を買い集め勉強を始めました。相談に来る生徒、いわゆるクライエントはいくらでもありましたし、参考書通り、面談をテープにとって、後で分析することもできました。
カウンセリングという、アメリカでできた治療法は、いわゆるノンディレクティブ・メソッド、非指示的方法によって、自己分析を助けるというものでした。このノンディレクティブ・カウンセリングでは、カウンセラーは、クライエントの前では、絶対に、価値判断を示していけないし、自分の感情を出してもいけない。
「これから死にます」といわれても「やめなさい」というべきではない。「あなたに抱かれたい。ねたい」などとといわれたとしても、「なんかこう、大変感情が高ぶっているんですネ」などと、その状況を反射する。
相手を無限に受容し、完全に密着しつつ、かつ厳然として一定の距離を保つ、一つの鏡のような状態に自分を保つカウンセリングという作業は、なかなか大変なことでした。
♣♣♣♣
六〇年代の半ば前後には、カウンセリングという言葉だけは、かなり教育現場へ持込まれたとはいえ、一般的には、ほとんど理解されてはいませんでした。まあ、この状況は今も変っていませんが……。
だいたい個人的な指導という考え方自体に強く反対する人達が多かったようです。「一人の悩みはみんなの悩み」といううたい文句がいつもでてくるのです。
ある職員会議の時、またしても、そういううたい文句が高らかに述べられたので、ぼくは少し腹が立ち、一言ひやかしのつもりで、
「もしかりに、自分のペニスが小さいと思い悩んでる生徒がいたとして、そうした短少コンプレックスは、クラス全体の悩みとして解決できるでしょうか」
と発言し、大方の失笑を買ってしまったのでした。
カウンセリングに興味を持っている教師などは、一人いるかいないかという状況で、コバヤシ校長との出合いは、ぼくの一生でも極めて印象的だったと今思います。彼は、ぼくが行った高校の、ぼくにとって二人目の校長としてやって来たのですが、就任しての初めての懇親会で、「君はカウンセリングに興味をもってるそうだネ」と話しかけてきました。どうして分ったんだろう。ぼくはちょっと驚きました。その夜は、二人で夜更けまで、カウンセリングについて語り合いました。「それは技術ではなく思想であり哲学だ」というような結論になったように記憶しています。
組合役員の教師が、この新任校長にケンノミを食わせるべく、勢い込んで、「組合の集会」のための休暇を要求に出掛けたら、「ええ、ええ、もう手配済みです」とやられて面喰ったのだそうです。しばらくして、自衛隊が勧誘ビラを配りにくるというニュースが入り、[来ても断ってくれるように」と交渉すべく、やはり役員達が押しかけたら、「もう電話で断わっときました」という話。いやすごい奴がきたという噂でした。
彼は、何かの折に行き合うと、それとなく、なん年なん組のだれそれという生徒がいて、英語が落ちそうで悩んでるから一度話してやってくれ、という調子で、ぼくがカウンセリングをやることをうながしました。
それにしても、どうして、そんな細かいことを知ってるのだろうと、少し不思議でした。後で分ったのですが、校長室には、いつも、何人かの生徒が押しかけていたのです。事実、その頃の卒業アルバムを見ると、ほぼ半数近くの生徒が、校長室でグループ写真を取っているのです。おそらくそうした生徒にとって、校長室は最も印象深い想い出の場所だったのでしょう。
ぼく自身、あれほどの大校長には、もう出合えないのではないかという気がしています。
♣♣♣♣
さて、「ホテル事件」の調査を依頼されても、ぼくは、その生徒達を取調べる気など全くありませんでした。グループ・カウンセリングという感じで、数回にわたり彼等と会い、自由にしゃべってもらっただけでした。
大変なことをしてしまった。親にも金銭的にだけではなく精神的にも迷惑をかけてしまった。みんな、そういう風にしょげ切ってはいました。しかしそういうことと、この行動の発端となった、「泊り逃げ」が出来るかどうかという問題とは別のことのようでした。彼らはやはり、それは出来ると思ったのでしょう。だって、あの電話から足がついただけなのですから……。誰かが、少し残念そうに、「あの電話さえかけへんかったらなあ……」といったものです。
ぼくの立場としては、それはそれとして、話し合いを続けるうちに、「やっぱり悪いことはせんとこう」という認識が生れてきたらえらく結構なことや。でも、そんなことより、「沙汰あるまで自宅待機」を命じられ、近所の手前、一室に閉じ込められて、半ばノイローゼみたいになっている彼等が元気づくのを期待する方に気を奪われている状態だったのです。
さて、職員会議で報告を求められ、ぼくは出来るだけ正確に彼等の心の状況を説明した積りでした。ところが意外にも、先生方の反応は、「何と不届きな、反省の色が見られんではないか」というものでした。後で分ったのですが、「電話さえかけなければ……」というB君の言葉をチラリとぼくが引用したのが決定的だったそうです。ぼくは、大いにあわてふためき、何とか誤解をとこうとしたのですが、もう後の祭りでした。処分は、えらく重いものになってしまったのです。
教師というヤツラは、何と表面しか見ようとしないものか。うわっ面のつじつまさえ合っとれば、それでいいんか。
自分も教師であるぼくがいうのも変な話なんでしょうが、ぼくに深い教師不信が住みついたとしたら、多分この時からだったように思います。もう決して、聞き知った生徒の心のうちは、教師には云わんぞ。ぼくはそう思い定めたのです。
もしかしたら、ぼくは、カウンセリングというものが、学校という場所では不可能であることを、すでに感じ取っていたのかも知れません。個人の価値観、つまり個人を認める風土の中に、それは成立するはずなのですから……。そして、同時に、アメリカという異質文化の中で生れた非指示的な方法が、この国では、ある限界を持つ場合もあるということもうすうす感じ初めていました。
ただ、ぼくが固く信じたことは、コバヤシ先生もいったように非指示的カウンセリングは一つの思想であり、〈人間は必ず自分自身でよくなり得る存在である〉という信念の上に成り立っているということでした。
そうしたことを若いぼくに確認させてくれた、ぼくのクライエントたちは、多分、ぼくのカウンセラーだったのでしょう。
大阪のある一流ホテルから学校に電話がかかり、「おたくの生徒に、次のような名前の生徒おりますか」と、五人ほどの名前をあげたのです。調べるまでもなく、その名前は、みんな、教師の名前だった。これが、いわゆる「ホテル事件」の発端でした。そのホテルの説明によれば、ことのいきさつは、こんなことでした。
ある日、同志社の学生のなにがしと名乗って、予約電話がかかった。翌日、その学生達が現われると、それぞれの部屋に投宿した。彼等は、その夜、ホテル内のレストランやバーで飲み喰いし、もちろんサイソだけで、です。そして、多分夜が明けてからでしょうが、いずこともなく姿を消してしまった。喰い逃げ、泊り逃げという訳です。
ホテルはすぐ調べました。これといった手掛りがある訳ではなかったのですが、ただひとつ、彼等が、夜、市外通話をした電話番号が記録されていたのです。それがみんな京都だった。ホテルは、その電話番号をダイヤルし、「お宅には、大学生がおいでになりますか」とたずねました。すると、その三つ四つの電話先はほとんど大学生の子供はいなかったけれど、共通して、カツラ高校に行っている女子高生がいるということが分ったのです。
そういう訳で、学校に電話が掛ってきたということだったのです。
学校はすぐ調査を始め、女生徒達のつながりから、泊り逃げ生徒を割り出すのに、ほとんど時間はかかりませんでした。彼等はみんな、ごく普通の、どっちかといえば成績もよい方に属する生徒でした。もう十数年も前のことで、ぼくは、もう彼等の名前さえ憶えていません。
さて、この泊り逃げ計画を思いついたのはAでした。それも、全くの思いつきなのです。彼は、小さい頃から、父親に連れられて、ホテルに泊ることがよくあって、ホテルの仕組みに詳しくなりました。今とちがって、もう十年以上も前のその頃は、ホテルは、なんか特殊な所という感じだったようです。
彼は、友人達と学校の芝生でだべっている時、ホテルという所は、サインだけで飲み喰いできるし、その気にさえなれば、ただで泊れるはずだといったんです。
それを聞いていた連中の意見は二つに分れたそうです。いや、そら無理やで、という者と、彼がそういうからには、やれるのとちがうかな、というグループとに、です。無理や、いややれる、と議論しているうちに、もともと架空の話として楽しんでいたみたいなこの計画は、だんだんと現実株を帯びてきて、可能性をとなえるグループは真剣になったのです。
「よし、これを証明するためには、実際やってみるよりしかたない。やるぞ」そういうことになり、「やれる」グループから何人かがおりて、五人ほどが残ったのです。
♣♣
 生徒がなんらかの問題を起こした時には、その事実関係の取調べには担任があたるという規定があります。その内容は、補導委員会に報告され、五人の委員が、「生徒処置規定」に基づいて、生徒処置の原案を決めます。この会議には、生徒部長や担任はオブザーバーとして討議には参加できますが、票決権はありません。
生徒がなんらかの問題を起こした時には、その事実関係の取調べには担任があたるという規定があります。その内容は、補導委員会に報告され、五人の委員が、「生徒処置規定」に基づいて、生徒処置の原案を決めます。この会議には、生徒部長や担任はオブザーバーとして討議には参加できますが、票決権はありません。この、生徒部が生徒処置の票決に参加できないという制度は、極めて異例の制度のようです。これは、生徒部(補導部あるいは指導部という名の所が多い)というところが、生徒を取り締まるのではなく、生徒の側に立って生徒指導の企画を行うという考え方を示したものです。
ほとんどの高校では、補導部というのは「学校警察」のように考えられているのですが、わがカツラ高校では、警察はなく、処罰機関として補導委員会がある。そういうことなのだと、ぼくは考えていました。京都教育というのが、ひところ有名で、他府県から、視察・見学の先生方が次々とやってきました。生徒部で、いまいったような仕組みを聞いて、
「へえ、変ってますねえ」とか「素晴らしい制度ですね」とかコメントしたものでした。
そういうことですから、この「ホテル事件」でも当然、それぞれの生徒の担任が取調べに当ることになります。ただ、問題生徒が、いくつかのクラスに分散していた場合には、担任の連絡係を兼ねて、生徒部の教師が、事情聴取に加わることになっていました。
それで、生徒部に属しており、カウンセラーみたいなことをやっていたぼくは、この係になった訳です。
ぼくが、カウソセリングというものに興味をもったのは、ずっと昔、学生時代にさかのぼるようです。山岳部のリーダーで少数精鋭主義を唱えてつっ走っていた頃が終り、リーダーを後輩にゆずり、OBとなって、「年寄り」みたいな立場になると、下級生の相談にいかに対応するかという問題に直面したからです。
この立場は、教師としてのぼくにも共通した状況ともいえました。ぼくは、カウンセリングの本を買い集め勉強を始めました。相談に来る生徒、いわゆるクライエントはいくらでもありましたし、参考書通り、面談をテープにとって、後で分析することもできました。
カウンセリングという、アメリカでできた治療法は、いわゆるノンディレクティブ・メソッド、非指示的方法によって、自己分析を助けるというものでした。このノンディレクティブ・カウンセリングでは、カウンセラーは、クライエントの前では、絶対に、価値判断を示していけないし、自分の感情を出してもいけない。
「これから死にます」といわれても「やめなさい」というべきではない。「あなたに抱かれたい。ねたい」などとといわれたとしても、「なんかこう、大変感情が高ぶっているんですネ」などと、その状況を反射する。
相手を無限に受容し、完全に密着しつつ、かつ厳然として一定の距離を保つ、一つの鏡のような状態に自分を保つカウンセリングという作業は、なかなか大変なことでした。
♣♣♣♣
六〇年代の半ば前後には、カウンセリングという言葉だけは、かなり教育現場へ持込まれたとはいえ、一般的には、ほとんど理解されてはいませんでした。まあ、この状況は今も変っていませんが……。
だいたい個人的な指導という考え方自体に強く反対する人達が多かったようです。「一人の悩みはみんなの悩み」といううたい文句がいつもでてくるのです。
ある職員会議の時、またしても、そういううたい文句が高らかに述べられたので、ぼくは少し腹が立ち、一言ひやかしのつもりで、
「もしかりに、自分のペニスが小さいと思い悩んでる生徒がいたとして、そうした短少コンプレックスは、クラス全体の悩みとして解決できるでしょうか」
と発言し、大方の失笑を買ってしまったのでした。
カウンセリングに興味を持っている教師などは、一人いるかいないかという状況で、コバヤシ校長との出合いは、ぼくの一生でも極めて印象的だったと今思います。彼は、ぼくが行った高校の、ぼくにとって二人目の校長としてやって来たのですが、就任しての初めての懇親会で、「君はカウンセリングに興味をもってるそうだネ」と話しかけてきました。どうして分ったんだろう。ぼくはちょっと驚きました。その夜は、二人で夜更けまで、カウンセリングについて語り合いました。「それは技術ではなく思想であり哲学だ」というような結論になったように記憶しています。
組合役員の教師が、この新任校長にケンノミを食わせるべく、勢い込んで、「組合の集会」のための休暇を要求に出掛けたら、「ええ、ええ、もう手配済みです」とやられて面喰ったのだそうです。しばらくして、自衛隊が勧誘ビラを配りにくるというニュースが入り、[来ても断ってくれるように」と交渉すべく、やはり役員達が押しかけたら、「もう電話で断わっときました」という話。いやすごい奴がきたという噂でした。
彼は、何かの折に行き合うと、それとなく、なん年なん組のだれそれという生徒がいて、英語が落ちそうで悩んでるから一度話してやってくれ、という調子で、ぼくがカウンセリングをやることをうながしました。
それにしても、どうして、そんな細かいことを知ってるのだろうと、少し不思議でした。後で分ったのですが、校長室には、いつも、何人かの生徒が押しかけていたのです。事実、その頃の卒業アルバムを見ると、ほぼ半数近くの生徒が、校長室でグループ写真を取っているのです。おそらくそうした生徒にとって、校長室は最も印象深い想い出の場所だったのでしょう。
ぼく自身、あれほどの大校長には、もう出合えないのではないかという気がしています。
♣♣♣♣
さて、「ホテル事件」の調査を依頼されても、ぼくは、その生徒達を取調べる気など全くありませんでした。グループ・カウンセリングという感じで、数回にわたり彼等と会い、自由にしゃべってもらっただけでした。
大変なことをしてしまった。親にも金銭的にだけではなく精神的にも迷惑をかけてしまった。みんな、そういう風にしょげ切ってはいました。しかしそういうことと、この行動の発端となった、「泊り逃げ」が出来るかどうかという問題とは別のことのようでした。彼らはやはり、それは出来ると思ったのでしょう。だって、あの電話から足がついただけなのですから……。誰かが、少し残念そうに、「あの電話さえかけへんかったらなあ……」といったものです。
ぼくの立場としては、それはそれとして、話し合いを続けるうちに、「やっぱり悪いことはせんとこう」という認識が生れてきたらえらく結構なことや。でも、そんなことより、「沙汰あるまで自宅待機」を命じられ、近所の手前、一室に閉じ込められて、半ばノイローゼみたいになっている彼等が元気づくのを期待する方に気を奪われている状態だったのです。
さて、職員会議で報告を求められ、ぼくは出来るだけ正確に彼等の心の状況を説明した積りでした。ところが意外にも、先生方の反応は、「何と不届きな、反省の色が見られんではないか」というものでした。後で分ったのですが、「電話さえかけなければ……」というB君の言葉をチラリとぼくが引用したのが決定的だったそうです。ぼくは、大いにあわてふためき、何とか誤解をとこうとしたのですが、もう後の祭りでした。処分は、えらく重いものになってしまったのです。
教師というヤツラは、何と表面しか見ようとしないものか。うわっ面のつじつまさえ合っとれば、それでいいんか。
自分も教師であるぼくがいうのも変な話なんでしょうが、ぼくに深い教師不信が住みついたとしたら、多分この時からだったように思います。もう決して、聞き知った生徒の心のうちは、教師には云わんぞ。ぼくはそう思い定めたのです。
もしかしたら、ぼくは、カウンセリングというものが、学校という場所では不可能であることを、すでに感じ取っていたのかも知れません。個人の価値観、つまり個人を認める風土の中に、それは成立するはずなのですから……。そして、同時に、アメリカという異質文化の中で生れた非指示的な方法が、この国では、ある限界を持つ場合もあるということもうすうす感じ初めていました。
ただ、ぼくが固く信じたことは、コバヤシ先生もいったように非指示的カウンセリングは一つの思想であり、〈人間は必ず自分自身でよくなり得る存在である〉という信念の上に成り立っているということでした。
そうしたことを若いぼくに確認させてくれた、ぼくのクライエントたちは、多分、ぼくのカウンセラーだったのでしょう。
18.バクチ事件のてんまつ
♣
あれはいつ頃のことだったか。浅間山荘事件があって、連合赤軍のリンチ事件が報じられた頃でしたから、一九七二年くらいだったかな。たしか、ホームルーム日記に、一人の赤軍シンパの生徒が、ひどいショックを受けたと書いていたのを億えていますから……。
とにかく、世の中、えらく騒然としていました。ぼくは、二年生のクラスを担任していました。教室は、木造校舎のはしっこの二階でした。どうも端のクラスというのはさわがしくなるようです。
永くおんなじ学校にいたりするとふと気づくのではないかと思うのですが、年が変って生徒が替っても、ある教室のクラスの雰囲気が、非常によく似ている、ということがままあります。どうやら、人間集団は、その居場所に極めて強い影響を受けるのではないかという気がするのです。これはなにも学校のクラスに限ったことではないようです。例えば、家族にしても、木造家屋に住んでいる人たちが、ビルに替れば、もしかしたら性格まで変ってくるのではないだろうか。
さて、あの「はしっこの教室」には、その場所に、そうさせる何かがあったのか。いつもにぎやかで、少なくとも、お行儀のよいクラスとはいえませんでした。
ぼくは、その頃、生徒に強制することをできるだけ少なくしたい、かなうことならゼロにしたいと考えていました。なにかを試みるのが好きなぼくとしては、ちょっとした実験をやっているような気分だったのです。
授業では、情緒的な圧迫感を与えないように気を配っていました。試験の点数など、特にきかれでもしない限り全然知らせませんでした。出欠も取りません。でも、欠席が特に増えたという訳でもなかった。
担任のクラスでは、生徒が昼のショート・ホームルームをさぼっても、出席を強要しませんでした。そのかわり、伝達事項を教室に掲示して、適当な時に、見るように云い渡しておきました。ぼくは当時、カナタイプに凝っていたので、掲示の文はひらがなでカナタイプで打つことにしました。これは、なかなかいいタイプの練習でもあったのです。
こういうやり方でも、決定的な不都合はなんにも生じなかったのですが、一つ困った問題が起ってきたのです。教室がどんどん汚なくなったのです。
「教室が汚れています。そうじするように、委員の人は方法を考えて下さい」
ぼくは何度もそういいましたが、委員達は、一向に当番を決めようともしなかったのです。教室は紙屑だらけになりました。
週一回のロング・ホームルームの時に、ぼくは屑箱をささげて、机の間をぐるぐる回りました。「みなさん、回りのゴミを拾って、ここに入れて下さい」
それで大分きれいになりますが、一日、二日で元の木阿弥でした。もう、臭いまでしてきていました。いろんな先生からの苦情も強烈でしたが、ぼくは、
「もう少しガマソして下さい。少し考えることがありますので……」とお願いしたり、相手によっては、「はあ、そうですネ」と無視したりしていました。
♣♣
二ヶ月もした頃、生徒もたまりかねたのか、掃除をしようといいだした。ホームルームで方法を決めるそうです。ぼくはホッとしました。でも、あんまり表情には出さないで、討議はみんなにまかして、引き上げたのです。
翌日の放課後、教室にゆくと、教室はみちがえるようにキレイになっていました。それでも、四、五人の女生徒が掃除中でした。男の子が一人も見あたりません。ははあ、男女交代でやることにしたのか、ぼくはそう思い、
「今日は女の番ケ」
と、ききました。すると一人が、
「いいえ、掃除は女子だけでやることになったん」
と、すました順で答えたのです。
「なんでや」
「多数決で、そう決まったんやもん。しかたないもん」
と、別の一人が、少しフクレッ面で答えました。少しあっ気にとられ、聞きだした事の次第は、まあ次のようなことでした。
一人の男子生徒が、掃除は女子がやることにすべぎだと提案した。彼は提案理由を、こう述べたといいます。
「みんな、家へ帰ってみ、掃除はお母さんがやってる。つまり掃除は女の仕事やないか」
もちろん女子側は、「そんな無茶な」と猛反対した。ところが、女子生徒の人数はクラスの三分の一ほどです。多数決で、簡単に押し切られてしまったのだそうです。
そんなアホな。無茶苦茶な話ではないか。
「お前らそんな。ソージするな。そら多数決の暴力や。拒否せえ」
ほんとに止めてもええのかいなあ、という顔をしている彼女等に、ぼくはしたり顔に説明したものです。あんなあ、民主主義イコール多数決とちゃうのやぞ。多数決原理というのは、もともと多数が強いのに決ってる中で、少数意見をどう取り入れようかという精神なんや。こんな雑な説明で分ったとは思えなかったのですが、とにかく、「明日からは止めます」ということになったのです。
翌日、放課後、散人の男子生徒が、血相をかえてやって来ました。
センセ、けしからんやないか。ワシらがクラス討議をして決めた全体の決定をくつがえすのか。多数決で決まったことを守らんでもええのか。すごい剣幕です。
「守る必要ないわい。それは多数決の暴力じゃ」
そういった時、フトぼくの頭にひらめき、
「あんなあ、生徒を男と女になんで分けるねん。ワシの頭には、男生徒も女生徒もないんや。みんな同じクラスの生徒や。そやし、あんな決定は何のことか分らん」
♣♣♣
掃除は普通に行われるようになり、まあ、毎日点検に出掛けて出欠をとるような担任のクラスに較べたら少しは汚ないかも知れないけど、並の教室程度にはなったようでした。
夏休みが済んで二学期が始まり、もうそろそろ秋風も吹き始めた頃、一つの事件が起こりました。一人の生徒が家出をしたのが発端でした。
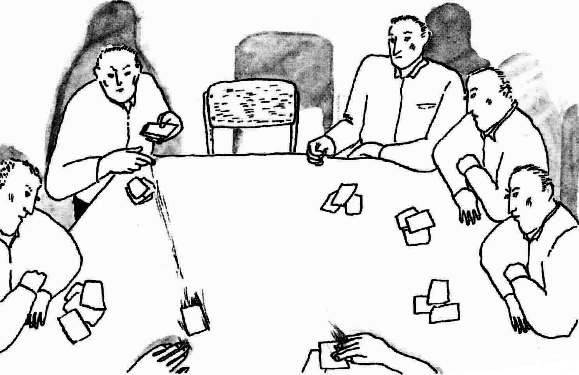 その生徒は祖父母に養育されていることは分っていたし、何か家庭の問題が原因だろうとぼくは推測しました。でも、それは、ぼくにとって、あんまり関係のない事に思えたし、依頼もないのに、どうこうする必要もないと思ってほっといたのです。まあそのうちに帰ってきよるやろ、あいつの事やから……。
その生徒は祖父母に養育されていることは分っていたし、何か家庭の問題が原因だろうとぼくは推測しました。でも、それは、ぼくにとって、あんまり関係のない事に思えたし、依頼もないのに、どうこうする必要もないと思ってほっといたのです。まあそのうちに帰ってきよるやろ、あいつの事やから……。
一週間ほどして、彼は警察に保護されたのですが、そこで重大な事実が明らかになったのです。
家出をした彼は、京都駅構内の格好の物置きをねぐらとして、そこに寝起きしていたのですが、落ちていたカメラを拾い、それを持って、河原町を歩いているところを補導され、そのカメラが盗難届けの出ているものだった。そこで取調べが始まり、その中で家出の原因が明らかになったのです。彼はクラスの教室で賭けポーカーをやって、負けがこんで、支払いに窮して家出したという訳です。えらいことです。関係ないどころの話ではなくなりました。ぼくは早速、その五、六人のばくちグループと話し合いました。
みんな友達なのですが、「アホなやっちゃ、家出しても済むことやない」という者もいれば、「警察でしゃべるとはケシカラン裏切りや」といきまく奴もいました。「あいつも可哀そうやで、家いってみ、あのバアさん、なんやらいう宗教にこったはるやろ。あいつに向いたら、二言目には、『あなたは神の子なんです』。あれではタマランと思うわ」
「それで、負けはなんぼになってんのや」
と、ぼくはたずね、みんながいった額を合計したら、なんと八万円をこえていました。
「へええ、なんでまたそんなぎょうさんになったんや」
「あいつ、負けを取り返そう思うて、どんどん点をあげよったしやろ」
いずれにしろ困った事態になったと思いました。こういう状況では、友達の手前、彼はもう学校へは来れないだろう。事実、家庭では、すでに私学への転校の用意をしているそうです。別の問題は、学校側の対応です。こういう場合、担任は、その生徒の処置を補導委員会に報告するのが普通です。でも、もし補導委員会に渡したら、この生徒が、学校に来れなくなることは、もっと明らかでした。
ぼくはあんまり相性のよくない校長に、この件は、ぼくが解決してみる積りですと言明しました。
♣♣♣♣
解決は、ばくち仲間共が、彼に「気にせんと来いや」といってやることしかない。でもこれは仲々大変なことです。これは強制してできることではありません。彼等は、「前に負けた時は、ワシはアイツにちゃんと払ったんや」などといってるんですから……。
とにかく、ぼくは、放課後にホームルームを招集したのです。いつも、ボケーッとしてのんべんだらりのぼくが真剣な顔付きしているからか、クラスはシーンとしていました。
ぼくは経過を説明し、「担任として、ぼくは彼が学校を止めるような事態は、なんとしても回避したいと考えている。この方向で、みんなで解決法を考え出してくれ」と依頼しました。
やがて一人の生徒が、「バクチはもともと悪いことや。みんなが反省したら、それでしまいや。彼は来たらええんや」
ぼくは黙って聞いていました。普通の場合、ぼぐはクラスの討議には席をはずすことにしていました。ぼくがいると自由な意見がでないと思ったからで、経過は後で誰かに聞くことにしていたのです。だから、クラスの一隅で、ぼくが耳を傾けているということ自体、異常なことでした。
すぐに別の一人が、「バクチがなんで悪いね、大人はみんなやっとる」と発言しました。すると「それは、違うと思います。賭博は法律で禁じられているはずです」と女生徒がいいました。「ニナガワはんは競輪を認めとるやないか」という反論がでて、ぼくは思わず苦笑してしまいました。
こんな具合にけっこう発言は活溌でしたが、当事者たちは終始沈黙を保っていました。誰かが、「彼は、負け込んだお金を払わなくてもいいはずだ。それで友情にひびが入るということもないはずだ」と発言したとき、別の一人が憤然として立ち、
「賭けが悪いとかいいとか、そんな問題とちゃうんじゃ。負けたら払わんならんもんなんじゃ。そういうことになってるねん。女房質に入れても……ということもあるんや」
みんなあっ気に取られ、シーンとなったのです。何人かは、ぼくの意見を読み取ろうとぼくの顔を見ました。ぼくは、
「人間の集団には、その集団のモラル、仁義があることは認めるし、それを悪いとは思わない。しかしこの場合、学校を止めねばならない瀬戸際に立ってる奴の立場で考えたい」
と述べました。
翌日、夕方、ぼくは、ばくちグループを学校の近くのキッサ店に集めました。
「あいつ学校止めよってもいいんか」
「もともと正当な金でもないし、もらおとは思ってません」
そういったのは、いちばん多額の貨しのある男でした。それにつられたように、次々と連鎖反応的に、「わしかてかまへん」とみんながうなずき、ぼくは、「ほな、電話するし、直接、そういうたれよ」
すぐに現われた彼に、連中はみんな、もうすっかり金のことはあきらめがついたのか、
「お前、気にすんな。わしら別にどうも思わへんぞ。学校へ来いや」
みんなから、肩をたたかれ、彼は消え入りそうな顔をしながら、それでも、うれしそうでした。ほんとにあの時は、ぼくもうれしかった。
彼等はみんな何事もなかったように卒業してゆきました。
たしかに、今現在、おんなじ事件が起こったとしたら、とてもこんな具合にはゆかないだろうとは思います。全てに、時代の流れと背景がある。
ただ、ぼくが思うのは、もしぼくが、あのクラスで、「掃除をせえ」というやり方をしていたら、ああいう感じの解決はできなかっただろうということ、これは多分確かなことだと思うのです。
あれはいつ頃のことだったか。浅間山荘事件があって、連合赤軍のリンチ事件が報じられた頃でしたから、一九七二年くらいだったかな。たしか、ホームルーム日記に、一人の赤軍シンパの生徒が、ひどいショックを受けたと書いていたのを億えていますから……。
とにかく、世の中、えらく騒然としていました。ぼくは、二年生のクラスを担任していました。教室は、木造校舎のはしっこの二階でした。どうも端のクラスというのはさわがしくなるようです。
永くおんなじ学校にいたりするとふと気づくのではないかと思うのですが、年が変って生徒が替っても、ある教室のクラスの雰囲気が、非常によく似ている、ということがままあります。どうやら、人間集団は、その居場所に極めて強い影響を受けるのではないかという気がするのです。これはなにも学校のクラスに限ったことではないようです。例えば、家族にしても、木造家屋に住んでいる人たちが、ビルに替れば、もしかしたら性格まで変ってくるのではないだろうか。
さて、あの「はしっこの教室」には、その場所に、そうさせる何かがあったのか。いつもにぎやかで、少なくとも、お行儀のよいクラスとはいえませんでした。
ぼくは、その頃、生徒に強制することをできるだけ少なくしたい、かなうことならゼロにしたいと考えていました。なにかを試みるのが好きなぼくとしては、ちょっとした実験をやっているような気分だったのです。
授業では、情緒的な圧迫感を与えないように気を配っていました。試験の点数など、特にきかれでもしない限り全然知らせませんでした。出欠も取りません。でも、欠席が特に増えたという訳でもなかった。
担任のクラスでは、生徒が昼のショート・ホームルームをさぼっても、出席を強要しませんでした。そのかわり、伝達事項を教室に掲示して、適当な時に、見るように云い渡しておきました。ぼくは当時、カナタイプに凝っていたので、掲示の文はひらがなでカナタイプで打つことにしました。これは、なかなかいいタイプの練習でもあったのです。
こういうやり方でも、決定的な不都合はなんにも生じなかったのですが、一つ困った問題が起ってきたのです。教室がどんどん汚なくなったのです。
「教室が汚れています。そうじするように、委員の人は方法を考えて下さい」
ぼくは何度もそういいましたが、委員達は、一向に当番を決めようともしなかったのです。教室は紙屑だらけになりました。
週一回のロング・ホームルームの時に、ぼくは屑箱をささげて、机の間をぐるぐる回りました。「みなさん、回りのゴミを拾って、ここに入れて下さい」
それで大分きれいになりますが、一日、二日で元の木阿弥でした。もう、臭いまでしてきていました。いろんな先生からの苦情も強烈でしたが、ぼくは、
「もう少しガマソして下さい。少し考えることがありますので……」とお願いしたり、相手によっては、「はあ、そうですネ」と無視したりしていました。
♣♣
二ヶ月もした頃、生徒もたまりかねたのか、掃除をしようといいだした。ホームルームで方法を決めるそうです。ぼくはホッとしました。でも、あんまり表情には出さないで、討議はみんなにまかして、引き上げたのです。
翌日の放課後、教室にゆくと、教室はみちがえるようにキレイになっていました。それでも、四、五人の女生徒が掃除中でした。男の子が一人も見あたりません。ははあ、男女交代でやることにしたのか、ぼくはそう思い、
「今日は女の番ケ」
と、ききました。すると一人が、
「いいえ、掃除は女子だけでやることになったん」
と、すました順で答えたのです。
「なんでや」
「多数決で、そう決まったんやもん。しかたないもん」
と、別の一人が、少しフクレッ面で答えました。少しあっ気にとられ、聞きだした事の次第は、まあ次のようなことでした。
一人の男子生徒が、掃除は女子がやることにすべぎだと提案した。彼は提案理由を、こう述べたといいます。
「みんな、家へ帰ってみ、掃除はお母さんがやってる。つまり掃除は女の仕事やないか」
もちろん女子側は、「そんな無茶な」と猛反対した。ところが、女子生徒の人数はクラスの三分の一ほどです。多数決で、簡単に押し切られてしまったのだそうです。
そんなアホな。無茶苦茶な話ではないか。
「お前らそんな。ソージするな。そら多数決の暴力や。拒否せえ」
ほんとに止めてもええのかいなあ、という顔をしている彼女等に、ぼくはしたり顔に説明したものです。あんなあ、民主主義イコール多数決とちゃうのやぞ。多数決原理というのは、もともと多数が強いのに決ってる中で、少数意見をどう取り入れようかという精神なんや。こんな雑な説明で分ったとは思えなかったのですが、とにかく、「明日からは止めます」ということになったのです。
翌日、放課後、散人の男子生徒が、血相をかえてやって来ました。
センセ、けしからんやないか。ワシらがクラス討議をして決めた全体の決定をくつがえすのか。多数決で決まったことを守らんでもええのか。すごい剣幕です。
「守る必要ないわい。それは多数決の暴力じゃ」
そういった時、フトぼくの頭にひらめき、
「あんなあ、生徒を男と女になんで分けるねん。ワシの頭には、男生徒も女生徒もないんや。みんな同じクラスの生徒や。そやし、あんな決定は何のことか分らん」
♣♣♣
掃除は普通に行われるようになり、まあ、毎日点検に出掛けて出欠をとるような担任のクラスに較べたら少しは汚ないかも知れないけど、並の教室程度にはなったようでした。
夏休みが済んで二学期が始まり、もうそろそろ秋風も吹き始めた頃、一つの事件が起こりました。一人の生徒が家出をしたのが発端でした。
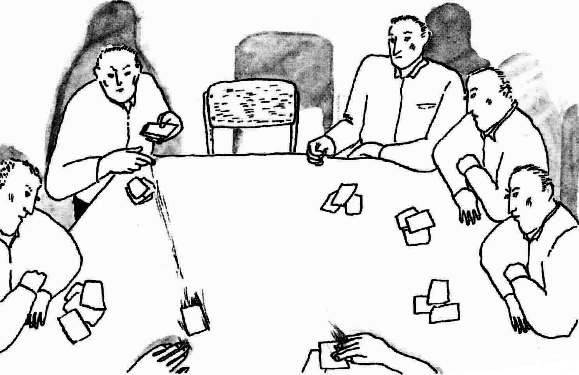 その生徒は祖父母に養育されていることは分っていたし、何か家庭の問題が原因だろうとぼくは推測しました。でも、それは、ぼくにとって、あんまり関係のない事に思えたし、依頼もないのに、どうこうする必要もないと思ってほっといたのです。まあそのうちに帰ってきよるやろ、あいつの事やから……。
その生徒は祖父母に養育されていることは分っていたし、何か家庭の問題が原因だろうとぼくは推測しました。でも、それは、ぼくにとって、あんまり関係のない事に思えたし、依頼もないのに、どうこうする必要もないと思ってほっといたのです。まあそのうちに帰ってきよるやろ、あいつの事やから……。一週間ほどして、彼は警察に保護されたのですが、そこで重大な事実が明らかになったのです。
家出をした彼は、京都駅構内の格好の物置きをねぐらとして、そこに寝起きしていたのですが、落ちていたカメラを拾い、それを持って、河原町を歩いているところを補導され、そのカメラが盗難届けの出ているものだった。そこで取調べが始まり、その中で家出の原因が明らかになったのです。彼はクラスの教室で賭けポーカーをやって、負けがこんで、支払いに窮して家出したという訳です。えらいことです。関係ないどころの話ではなくなりました。ぼくは早速、その五、六人のばくちグループと話し合いました。
みんな友達なのですが、「アホなやっちゃ、家出しても済むことやない」という者もいれば、「警察でしゃべるとはケシカラン裏切りや」といきまく奴もいました。「あいつも可哀そうやで、家いってみ、あのバアさん、なんやらいう宗教にこったはるやろ。あいつに向いたら、二言目には、『あなたは神の子なんです』。あれではタマランと思うわ」
「それで、負けはなんぼになってんのや」
と、ぼくはたずね、みんながいった額を合計したら、なんと八万円をこえていました。
「へええ、なんでまたそんなぎょうさんになったんや」
「あいつ、負けを取り返そう思うて、どんどん点をあげよったしやろ」
いずれにしろ困った事態になったと思いました。こういう状況では、友達の手前、彼はもう学校へは来れないだろう。事実、家庭では、すでに私学への転校の用意をしているそうです。別の問題は、学校側の対応です。こういう場合、担任は、その生徒の処置を補導委員会に報告するのが普通です。でも、もし補導委員会に渡したら、この生徒が、学校に来れなくなることは、もっと明らかでした。
ぼくはあんまり相性のよくない校長に、この件は、ぼくが解決してみる積りですと言明しました。
♣♣♣♣
解決は、ばくち仲間共が、彼に「気にせんと来いや」といってやることしかない。でもこれは仲々大変なことです。これは強制してできることではありません。彼等は、「前に負けた時は、ワシはアイツにちゃんと払ったんや」などといってるんですから……。
とにかく、ぼくは、放課後にホームルームを招集したのです。いつも、ボケーッとしてのんべんだらりのぼくが真剣な顔付きしているからか、クラスはシーンとしていました。
ぼくは経過を説明し、「担任として、ぼくは彼が学校を止めるような事態は、なんとしても回避したいと考えている。この方向で、みんなで解決法を考え出してくれ」と依頼しました。
やがて一人の生徒が、「バクチはもともと悪いことや。みんなが反省したら、それでしまいや。彼は来たらええんや」
ぼくは黙って聞いていました。普通の場合、ぼぐはクラスの討議には席をはずすことにしていました。ぼくがいると自由な意見がでないと思ったからで、経過は後で誰かに聞くことにしていたのです。だから、クラスの一隅で、ぼくが耳を傾けているということ自体、異常なことでした。
すぐに別の一人が、「バクチがなんで悪いね、大人はみんなやっとる」と発言しました。すると「それは、違うと思います。賭博は法律で禁じられているはずです」と女生徒がいいました。「ニナガワはんは競輪を認めとるやないか」という反論がでて、ぼくは思わず苦笑してしまいました。
こんな具合にけっこう発言は活溌でしたが、当事者たちは終始沈黙を保っていました。誰かが、「彼は、負け込んだお金を払わなくてもいいはずだ。それで友情にひびが入るということもないはずだ」と発言したとき、別の一人が憤然として立ち、
「賭けが悪いとかいいとか、そんな問題とちゃうんじゃ。負けたら払わんならんもんなんじゃ。そういうことになってるねん。女房質に入れても……ということもあるんや」
みんなあっ気に取られ、シーンとなったのです。何人かは、ぼくの意見を読み取ろうとぼくの顔を見ました。ぼくは、
「人間の集団には、その集団のモラル、仁義があることは認めるし、それを悪いとは思わない。しかしこの場合、学校を止めねばならない瀬戸際に立ってる奴の立場で考えたい」
と述べました。
翌日、夕方、ぼくは、ばくちグループを学校の近くのキッサ店に集めました。
「あいつ学校止めよってもいいんか」
「もともと正当な金でもないし、もらおとは思ってません」
そういったのは、いちばん多額の貨しのある男でした。それにつられたように、次々と連鎖反応的に、「わしかてかまへん」とみんながうなずき、ぼくは、「ほな、電話するし、直接、そういうたれよ」
すぐに現われた彼に、連中はみんな、もうすっかり金のことはあきらめがついたのか、
「お前、気にすんな。わしら別にどうも思わへんぞ。学校へ来いや」
みんなから、肩をたたかれ、彼は消え入りそうな顔をしながら、それでも、うれしそうでした。ほんとにあの時は、ぼくもうれしかった。
彼等はみんな何事もなかったように卒業してゆきました。
たしかに、今現在、おんなじ事件が起こったとしたら、とてもこんな具合にはゆかないだろうとは思います。全てに、時代の流れと背景がある。
ただ、ぼくが思うのは、もしぼくが、あのクラスで、「掃除をせえ」というやり方をしていたら、ああいう感じの解決はできなかっただろうということ、これは多分確かなことだと思うのです。
17.一人旅は顔つきまで変える
♣
朝寝坊して、昼前に出発し、岩を登って遊んでいたら、日が暮れました。岩場の下山路を手探ぐりで降って、テント場に帰りついたら七時でした。昨夜から、ぼくは、ここ、大原のコンピラの岩場に来ています。敬老の日で連休になる土曜日から、高校山岳部の連中が十五人程で合宿を計画したのです。岩登りですから、ほっとく訳にもゆかず、付添ってきました。
この連載原稿に追われていたのですが、数日前から、中国登山協会親善訪日団が来洛して、レセプショソやらパーティーやら昼食会やらと、ニーハオ、カンペー、シェシェの繰り返しです。とても原稿書きどころではありませんでした。ぼくは、原稿用紙持参で、コンピラに来たんです。
暗闇のテント場に帰り着くと、早速、ザイル二巻きを積み重ねて椅子を作りました。持参した丸い大型ゴミ箱を前に据え、ベニヤ板を置くと、机ができ上り。
太い杉の木に張り渡した細引きに、ブタンガスのランプをぶら下げました。見上げると、亭亭とそびえたつ北山杉が、うす白く浮かび、さらに目をこらすと、黒々と茂った木棺のはるかその奥に、星が数個またたいているのがなんとか見てとれます。
 生徒達は、ビーフシチューを作り始めたようです。テントに帰って来るなり花尻橋の方に向かったOBが、生ビールを買ってきました。つまみは、ぼくが持ってきた魚そーめん、酢だこに高知名産の「酒盗」。
生徒達は、ビーフシチューを作り始めたようです。テントに帰って来るなり花尻橋の方に向かったOBが、生ビールを買ってきました。つまみは、ぼくが持ってきた魚そーめん、酢だこに高知名産の「酒盗」。
原稿書きは、しばらく中断して、ビールを飲むことにします。
谷の瀬音がかすかにきこえ、虫のすだく声が澄んで聞こえてきます。あるともつかないかすかな風が、頬をなぜています。なんとも気分がよい。
岩登りの疲れがあったのか、少しの生ビールは、急激に回り、ぼくは眠り込んでしまったようでした。少し湿った山土は、ひんやりとして心地よく、なんだか大地の霊気が、身体にしみ通って、全細胞が甦えるような気がする。やっぱり人間は、少し小石のあるゴチゴチとした地面に寝ないと、おかしくなるんではないか。フワフワの蒲団や、スプリングのよく利いたベッドなどに寝ていたら、頭までふやけてしまうのではなかろうか。なんだかそんな気がして来ます。
だからぼくは、山に登ることよりも、山で寝ることをすすめている訳です。山岳部員などは、テントから通学したらよい。
本多勝一との『極限の民族』やベトナム取材で有名な、朝日新聞の編集委員、藤木高嶺さんは、旧制中学の頃、六甲の岩場のテントから通学を姶めたのだそうです。父親は山登りで有名な九三氏ですから文句はいわなかったのですが、テントの一人暮らしが1ヶ月に及ぶ頃、たまりかねた母親が担任に相談したらしい。ある日の夕方、肉と酒を土産に山に登って来た担任の教師は、
「藤木君、一晩どうかね、ぼくを泊めてくれんか」
♣♣
その担任の教師が持参した肉で酒を汲み交し、二人は、そのまま眠りました。翌朝、その先生は、
「どうや、テントたたむの手伝うよ」
と、いいました。「お母さんが心配してる。いっぺん帰ったら……」といわれて、藤木さんは、ようやく山を下ることにしたのだそうです。
まあ、テントでの一人住いなどということは、そうした生活技術を身につけている山岳部員でも、そう簡単にやれることでないのかも知れません。そこで、ぼくは、生徒に一人旅をすすめている。多分親は心配して反対するだろうから、その対策を立てること。特に女の場合は、なかなか大変なようで、ハイミスのおばちゃんでさえ、「親が心配して……」などといっているのを聞くと、なんだかけったいな気分になります。ぼくは、適当にごまかせ、嘘も方便、とけっこうけしからんことを、かなり堂々と述べております。
いつだったか、一人の生徒が、夏休み前、テント生活について、質問にやってきました。彼は、自転車に乗って、東海道を走り、東京まで行く積りなのだそうです。日程については別にして、テソトやコンロ等の装備について、相談に乗ったのです。何回目かに来た時、ぼくは、フト思い付いて、
 「旗たてて走れ。京都———東京と書いた幟たてるんや」
「旗たてて走れ。京都———東京と書いた幟たてるんや」
と、いいました。
このアイデアはよかったらしく、遊園地などで休んでいると、買物帰りのオバさんなどが、「がんばりなさいよ」と激励し、お菓子やアイスクリーム等をくれた。そういうことが各地であったそうです。食糧に関しては、各地のスーパーで買う。生鮮野菜と米等は、都会からできるだけ離れた田舎の農家で頼む。これも頂戴することが多かったようです。だいたい田舎の人ほど親切なのです。
今回のコンビラの合宿でも、一人の生徒が米を持ってくるのを忘れ、大原の農家で、分けて下さいと頼んだら、十合(この頃の生徒は、一升のことを十合、一升五合は十五合という)もくれたのだそうです。
話を元に戻して、彼が鈴鹿峠を走り下り、愛知県に入った時、日が暮れ、ちょうどあった交番で、テント場について相談します。すると、その巡査は、「高校生が他府県ヘー人で旅行するとは不届きだ」と頭ごなしにしかりつけた。「なんだか関所役人という感じでした」
彼はあてどなく、町をさまよっていると、高校があって、柔道のかけ声が聞えました。柔道部員の彼は、そこにゆき、自己紹介すると、合宿中の部員達は大歓迎し、そこに泊って飯も食わしてもらったといいます。
こうした話は、彼が、ぼくの授業を取っていたので、一時間つぶして報告会をやってもらった時に聞いたのです。一番苦しかったのは、箱根越えだったそうです。
「帰り、新幹線がすぐトンネルに入り、あっという間に出る。この上を汗をたらして越えたのか。そう思うと、とても複雑な気分になりました」
と彼は報告を結びました。
♣♣♣
同じ年の二学期の末期、別の生徒が現われ、冬の北海道旅行の計画を打ち明けました。旅行といっても、彼の計画は、自転車で走るというのです。あの頃は、よほど自転車がはやりだったらしい。
それにしても、雪の上を自転車で走れるのかいな。ぼくは心配になりました。でも彼は、大丈夫だと答えました。その生徒がぼくに聞きたかったのは、雪の中でどうやって寝るか、ということでした。なんでも、ほとんど車の通らない道の峠越えが、予定コースにあるのだそうです。
もちろん装備についていろいろアドバイスしたのですが、ぼくが最も強調したのは、最後は装備ではない、ということでした。最終的にはオノレ白身の身体や。だから身体を寒さに慣らすこと。
ぼくが示した方法は、夜、ベランダで寝る。そしてどんどん蒲団を薄くする。さらには、早朝、桂川の土手を走る。ランニングシャツとショートパンツで、自転車で走ったらいいのではないか。
しばらくして廊下ですれちがったら、「やってますよ」ということでした。それ切り会わず、冬休みになり、ぼくも彼のことは忘れていました。
三学期が始まった日、彼が現われ、「行って来ました」とケロリとしています。予定通り完走した。一日、やはりあの峠越えが大変で、吹雪の吹きっさらしのバス停の片屋根ベンチで一夜を過ごしたと語りました。シートにくるまっていたのだが、やはり、少々はこわかったそうです。
 この他にも四国一周を目指した奴もいるし、古タイヤチューブのいかだで保津峡を下った連中もいる。
この他にも四国一周を目指した奴もいるし、古タイヤチューブのいかだで保津峡を下った連中もいる。
こうした生徒を見ていると、計画をやりとげた後は、なにか前とちがってくるような気がするのです。ぼくの勝手な先入観によるものでは、どうもないようです。やっぱり、単純にいって、どことなくしっかりしてくる。なんだか、顔つきまで違っています。
東海道の生徒の場合、おそらく彼は、あの旅において、何十人という見知らぬ人達とかなり印象的な出会いを経験したはずです。そういう出合いを通じて、ある人間観みたいなものを得始めたのではないだろうか。また、毎日遭遇する出来事の一つ一つに、自分自身の判断を下さねばならないということがあって、自分の判断の限界が分ってきたという意味も含めて、判断力に自信がついたはづです。
北海道の生徒の場合、もっとシビアな状態で、判断力の自信を得たといえるでしょう。そうであれば、顔つきが変ってきても、何の不思議もありません。
それにしても、近ごろ、こうした旅をする生徒がまったくいなくなりました。
家と学校を決り切った時間に往復する。そういう単調な、他律的な、管理された空間の世界では、何の発見もないし、何の自覚も得ることはむづかしい。子供は幼稚園児のまま高校、大学へと進む。それが、今日の「若者の幼児化」の実態ではないかという気がします。
♣♣♣♣
大分前のことですが、いまいった、生徒の冒険旅行みたいな話を文部省の登山研修所で話したことがありました。一人の研修生の教師が質問して、
「もし何かの事故が起こったら、どうされるんですか」
つまり、事故が起こったら、それは止めさせなかったぼくの責任で、どう責任をとるのか、というのです。
そこでぼくは、彼に「山での事故は不可抗力的に起こることもある」ことを認めてもらってから、「例えば、あなたが同行している合宿で事故が起こったら、あなたはどう責任をとりますか」と切り返しました。彼はやや考えてから、
「おそらく一生、良心の苛責に悩むと思います」
ぼくは、イライラしてしまい、「それで責任をとったことになるんかなあ」と言いました。
教師は、「そんなことでは責任がもてない」などという具合に、どうも二言目には責任、責任というけれど、ぼくに云わすれば、もともと、責任などなんにも取れないのです。
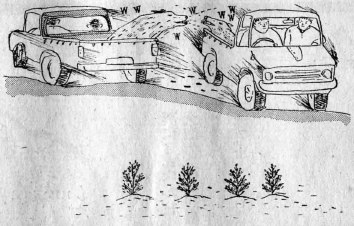 この時は、このあと、研修生の先生方が二派に分れてかなり議論を闘わせました。いまかりに、研修所で、ぼくが同じ話をしたとしても、おそらく、あんまり反応はないのではないか。「へええ、そんな生徒もいたのか」てなもんで、それだけでしまいなのではないか。どうもそんな気がします。これはちょうど、今日この頃の生徒の状況とおなじことです。
この時は、このあと、研修生の先生方が二派に分れてかなり議論を闘わせました。いまかりに、研修所で、ぼくが同じ話をしたとしても、おそらく、あんまり反応はないのではないか。「へええ、そんな生徒もいたのか」てなもんで、それだけでしまいなのではないか。どうもそんな気がします。これはちょうど、今日この頃の生徒の状況とおなじことです。
考えてみれば、教師も、その前は生徒であり学生、若者であったのだから、当り前のことなのかも知れません。
文部省登山研修所には、もう二十年近く前の開設当時の第一回研修から、ずっと講師をしていましたから、色々と面白いことがありました。最初の頃は、講師も、研修生と一緒に朝の国旗掲揚に参加しなければならなかった。数年のうちにだんだん出て行かなくなり、二人目の所長の時からは、出向く必要がなくなりました。
ところが、この所長は、研修生の評価をしろといいだした。最も強硬に反対したのは、ぼくと、東大の中根千枝門下のカノさんの二人でした。数日間の山登りを一緒にしただけで評価などできる訳がないではないか、とぼく達は主張し、所長は、いや記録を残すためだけですからとがんばりました。東京の若い大学山岳部OBの講師達の中には、「それはいい。評価用紙をちらつかせて、しごくか」などと、冗談にしても、アホみたいなことをいっている者もいました。
さんざんもめたあげく、結論としては、原則としてオール3。特に目立ち、自信をもって判定できる点についてのみ、4と2をつけるということで合意に達しました。でも、これも次の所長の時からなくなりました。
最初の頃は、ぼくはずっと、大学山岳部リーダー対象のクラス専門だったのですが、途中から、高校山岳部顧門のクラスも持つようになったのです。その最初の時、イトー専門職が、彼もここに来るまでは高校の教師だったのですが、小声でぼくに耳うちし、
「いちばん何にもできないのに、口だけ達者なのが、高校教師のクラスなんです」
ぼくはなんだか、自分のことを云われたような気がしないでもなかったのです。
朝寝坊して、昼前に出発し、岩を登って遊んでいたら、日が暮れました。岩場の下山路を手探ぐりで降って、テント場に帰りついたら七時でした。昨夜から、ぼくは、ここ、大原のコンピラの岩場に来ています。敬老の日で連休になる土曜日から、高校山岳部の連中が十五人程で合宿を計画したのです。岩登りですから、ほっとく訳にもゆかず、付添ってきました。
この連載原稿に追われていたのですが、数日前から、中国登山協会親善訪日団が来洛して、レセプショソやらパーティーやら昼食会やらと、ニーハオ、カンペー、シェシェの繰り返しです。とても原稿書きどころではありませんでした。ぼくは、原稿用紙持参で、コンピラに来たんです。
暗闇のテント場に帰り着くと、早速、ザイル二巻きを積み重ねて椅子を作りました。持参した丸い大型ゴミ箱を前に据え、ベニヤ板を置くと、机ができ上り。
太い杉の木に張り渡した細引きに、ブタンガスのランプをぶら下げました。見上げると、亭亭とそびえたつ北山杉が、うす白く浮かび、さらに目をこらすと、黒々と茂った木棺のはるかその奥に、星が数個またたいているのがなんとか見てとれます。
 生徒達は、ビーフシチューを作り始めたようです。テントに帰って来るなり花尻橋の方に向かったOBが、生ビールを買ってきました。つまみは、ぼくが持ってきた魚そーめん、酢だこに高知名産の「酒盗」。
生徒達は、ビーフシチューを作り始めたようです。テントに帰って来るなり花尻橋の方に向かったOBが、生ビールを買ってきました。つまみは、ぼくが持ってきた魚そーめん、酢だこに高知名産の「酒盗」。原稿書きは、しばらく中断して、ビールを飲むことにします。
谷の瀬音がかすかにきこえ、虫のすだく声が澄んで聞こえてきます。あるともつかないかすかな風が、頬をなぜています。なんとも気分がよい。
岩登りの疲れがあったのか、少しの生ビールは、急激に回り、ぼくは眠り込んでしまったようでした。少し湿った山土は、ひんやりとして心地よく、なんだか大地の霊気が、身体にしみ通って、全細胞が甦えるような気がする。やっぱり人間は、少し小石のあるゴチゴチとした地面に寝ないと、おかしくなるんではないか。フワフワの蒲団や、スプリングのよく利いたベッドなどに寝ていたら、頭までふやけてしまうのではなかろうか。なんだかそんな気がして来ます。
だからぼくは、山に登ることよりも、山で寝ることをすすめている訳です。山岳部員などは、テントから通学したらよい。
本多勝一との『極限の民族』やベトナム取材で有名な、朝日新聞の編集委員、藤木高嶺さんは、旧制中学の頃、六甲の岩場のテントから通学を姶めたのだそうです。父親は山登りで有名な九三氏ですから文句はいわなかったのですが、テントの一人暮らしが1ヶ月に及ぶ頃、たまりかねた母親が担任に相談したらしい。ある日の夕方、肉と酒を土産に山に登って来た担任の教師は、
「藤木君、一晩どうかね、ぼくを泊めてくれんか」
♣♣
その担任の教師が持参した肉で酒を汲み交し、二人は、そのまま眠りました。翌朝、その先生は、
「どうや、テントたたむの手伝うよ」
と、いいました。「お母さんが心配してる。いっぺん帰ったら……」といわれて、藤木さんは、ようやく山を下ることにしたのだそうです。
まあ、テントでの一人住いなどということは、そうした生活技術を身につけている山岳部員でも、そう簡単にやれることでないのかも知れません。そこで、ぼくは、生徒に一人旅をすすめている。多分親は心配して反対するだろうから、その対策を立てること。特に女の場合は、なかなか大変なようで、ハイミスのおばちゃんでさえ、「親が心配して……」などといっているのを聞くと、なんだかけったいな気分になります。ぼくは、適当にごまかせ、嘘も方便、とけっこうけしからんことを、かなり堂々と述べております。
いつだったか、一人の生徒が、夏休み前、テント生活について、質問にやってきました。彼は、自転車に乗って、東海道を走り、東京まで行く積りなのだそうです。日程については別にして、テソトやコンロ等の装備について、相談に乗ったのです。何回目かに来た時、ぼくは、フト思い付いて、
 「旗たてて走れ。京都———東京と書いた幟たてるんや」
「旗たてて走れ。京都———東京と書いた幟たてるんや」と、いいました。
このアイデアはよかったらしく、遊園地などで休んでいると、買物帰りのオバさんなどが、「がんばりなさいよ」と激励し、お菓子やアイスクリーム等をくれた。そういうことが各地であったそうです。食糧に関しては、各地のスーパーで買う。生鮮野菜と米等は、都会からできるだけ離れた田舎の農家で頼む。これも頂戴することが多かったようです。だいたい田舎の人ほど親切なのです。
今回のコンビラの合宿でも、一人の生徒が米を持ってくるのを忘れ、大原の農家で、分けて下さいと頼んだら、十合(この頃の生徒は、一升のことを十合、一升五合は十五合という)もくれたのだそうです。
話を元に戻して、彼が鈴鹿峠を走り下り、愛知県に入った時、日が暮れ、ちょうどあった交番で、テント場について相談します。すると、その巡査は、「高校生が他府県ヘー人で旅行するとは不届きだ」と頭ごなしにしかりつけた。「なんだか関所役人という感じでした」
彼はあてどなく、町をさまよっていると、高校があって、柔道のかけ声が聞えました。柔道部員の彼は、そこにゆき、自己紹介すると、合宿中の部員達は大歓迎し、そこに泊って飯も食わしてもらったといいます。
こうした話は、彼が、ぼくの授業を取っていたので、一時間つぶして報告会をやってもらった時に聞いたのです。一番苦しかったのは、箱根越えだったそうです。
「帰り、新幹線がすぐトンネルに入り、あっという間に出る。この上を汗をたらして越えたのか。そう思うと、とても複雑な気分になりました」
と彼は報告を結びました。
♣♣♣
同じ年の二学期の末期、別の生徒が現われ、冬の北海道旅行の計画を打ち明けました。旅行といっても、彼の計画は、自転車で走るというのです。あの頃は、よほど自転車がはやりだったらしい。
それにしても、雪の上を自転車で走れるのかいな。ぼくは心配になりました。でも彼は、大丈夫だと答えました。その生徒がぼくに聞きたかったのは、雪の中でどうやって寝るか、ということでした。なんでも、ほとんど車の通らない道の峠越えが、予定コースにあるのだそうです。
もちろん装備についていろいろアドバイスしたのですが、ぼくが最も強調したのは、最後は装備ではない、ということでした。最終的にはオノレ白身の身体や。だから身体を寒さに慣らすこと。
ぼくが示した方法は、夜、ベランダで寝る。そしてどんどん蒲団を薄くする。さらには、早朝、桂川の土手を走る。ランニングシャツとショートパンツで、自転車で走ったらいいのではないか。
しばらくして廊下ですれちがったら、「やってますよ」ということでした。それ切り会わず、冬休みになり、ぼくも彼のことは忘れていました。
三学期が始まった日、彼が現われ、「行って来ました」とケロリとしています。予定通り完走した。一日、やはりあの峠越えが大変で、吹雪の吹きっさらしのバス停の片屋根ベンチで一夜を過ごしたと語りました。シートにくるまっていたのだが、やはり、少々はこわかったそうです。
 この他にも四国一周を目指した奴もいるし、古タイヤチューブのいかだで保津峡を下った連中もいる。
この他にも四国一周を目指した奴もいるし、古タイヤチューブのいかだで保津峡を下った連中もいる。こうした生徒を見ていると、計画をやりとげた後は、なにか前とちがってくるような気がするのです。ぼくの勝手な先入観によるものでは、どうもないようです。やっぱり、単純にいって、どことなくしっかりしてくる。なんだか、顔つきまで違っています。
東海道の生徒の場合、おそらく彼は、あの旅において、何十人という見知らぬ人達とかなり印象的な出会いを経験したはずです。そういう出合いを通じて、ある人間観みたいなものを得始めたのではないだろうか。また、毎日遭遇する出来事の一つ一つに、自分自身の判断を下さねばならないということがあって、自分の判断の限界が分ってきたという意味も含めて、判断力に自信がついたはづです。
北海道の生徒の場合、もっとシビアな状態で、判断力の自信を得たといえるでしょう。そうであれば、顔つきが変ってきても、何の不思議もありません。
それにしても、近ごろ、こうした旅をする生徒がまったくいなくなりました。
家と学校を決り切った時間に往復する。そういう単調な、他律的な、管理された空間の世界では、何の発見もないし、何の自覚も得ることはむづかしい。子供は幼稚園児のまま高校、大学へと進む。それが、今日の「若者の幼児化」の実態ではないかという気がします。
♣♣♣♣
大分前のことですが、いまいった、生徒の冒険旅行みたいな話を文部省の登山研修所で話したことがありました。一人の研修生の教師が質問して、
「もし何かの事故が起こったら、どうされるんですか」
つまり、事故が起こったら、それは止めさせなかったぼくの責任で、どう責任をとるのか、というのです。
そこでぼくは、彼に「山での事故は不可抗力的に起こることもある」ことを認めてもらってから、「例えば、あなたが同行している合宿で事故が起こったら、あなたはどう責任をとりますか」と切り返しました。彼はやや考えてから、
「おそらく一生、良心の苛責に悩むと思います」
ぼくは、イライラしてしまい、「それで責任をとったことになるんかなあ」と言いました。
教師は、「そんなことでは責任がもてない」などという具合に、どうも二言目には責任、責任というけれど、ぼくに云わすれば、もともと、責任などなんにも取れないのです。
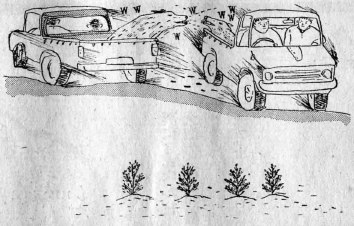 この時は、このあと、研修生の先生方が二派に分れてかなり議論を闘わせました。いまかりに、研修所で、ぼくが同じ話をしたとしても、おそらく、あんまり反応はないのではないか。「へええ、そんな生徒もいたのか」てなもんで、それだけでしまいなのではないか。どうもそんな気がします。これはちょうど、今日この頃の生徒の状況とおなじことです。
この時は、このあと、研修生の先生方が二派に分れてかなり議論を闘わせました。いまかりに、研修所で、ぼくが同じ話をしたとしても、おそらく、あんまり反応はないのではないか。「へええ、そんな生徒もいたのか」てなもんで、それだけでしまいなのではないか。どうもそんな気がします。これはちょうど、今日この頃の生徒の状況とおなじことです。考えてみれば、教師も、その前は生徒であり学生、若者であったのだから、当り前のことなのかも知れません。
文部省登山研修所には、もう二十年近く前の開設当時の第一回研修から、ずっと講師をしていましたから、色々と面白いことがありました。最初の頃は、講師も、研修生と一緒に朝の国旗掲揚に参加しなければならなかった。数年のうちにだんだん出て行かなくなり、二人目の所長の時からは、出向く必要がなくなりました。
ところが、この所長は、研修生の評価をしろといいだした。最も強硬に反対したのは、ぼくと、東大の中根千枝門下のカノさんの二人でした。数日間の山登りを一緒にしただけで評価などできる訳がないではないか、とぼく達は主張し、所長は、いや記録を残すためだけですからとがんばりました。東京の若い大学山岳部OBの講師達の中には、「それはいい。評価用紙をちらつかせて、しごくか」などと、冗談にしても、アホみたいなことをいっている者もいました。
さんざんもめたあげく、結論としては、原則としてオール3。特に目立ち、自信をもって判定できる点についてのみ、4と2をつけるということで合意に達しました。でも、これも次の所長の時からなくなりました。
最初の頃は、ぼくはずっと、大学山岳部リーダー対象のクラス専門だったのですが、途中から、高校山岳部顧門のクラスも持つようになったのです。その最初の時、イトー専門職が、彼もここに来るまでは高校の教師だったのですが、小声でぼくに耳うちし、
「いちばん何にもできないのに、口だけ達者なのが、高校教師のクラスなんです」
ぼくはなんだか、自分のことを云われたような気がしないでもなかったのです。
- HOME Archives: August 2007