- HOME Archives: August 2007
連載を終えて
 「いやいやまあまあ」連載をおえて(京都新聞1980年10月15日)
「いやいやまあまあ」連載をおえて(京都新聞1980年10月15日)予期しない反応が
「いやいやまあまあ」などという、なんやらつかまえ所のないタイトルの連載が終わって、数えてみればまだ十日ほどなのに、なんだか、あれはもう、ずっと前のことのような気がしている。
「大変だったでしょう」とねぎらってくれる人がいる。たしかに大変だったのがも知れないが、当の本人は、人が思うほど感じていなかったみたい。その「大変さ」が予想できる質のものであったからだと思う。もともと、人の物言いなどを気にしていたら、なんにも書けはしないのだ。
とはいえ、全く予期しない反応は気になった。たとえば、あの連載に登場した一人の昔の生徒が、そこを読んでごはんも喉に通らなくなったそうだ。彼女の友人が、十何年ぶりかに電話をかけてきたついでに、チラリとそういう彼女の反応を伝えた。それを聞いたとたん、ぼくの胃がキリキリと痛みだし、約一週間、おかゆを食べる破目になったりした。ぼくは、出来るだけありのまま書こうとしてきたし、いってみれば、フィクションみたいなものを入れないことを心意気としている。そうした勝手ないきがりの当然の報いとしては、まだ軽い方だったのだろう。
だれかの首がとぶぞ
連載が始まってすぐ、「これはまた、何とも破天荒な企画や」と告げた人がいた。そういわれてみれば、ああした欄にああいったものが載ったのは全国でも、初めてのことらしかった。おまけに、書いている男が、ぼくのような、まあ山登りの世界ではちょっとは知られているといった程度のヤツだったのだから・・・。彼が後につづけて「だれかの首がとぶぞ」などといったのも、あながち思いつきの誇張でもなかったようだ。
そうだとすれば、そこには、ぼくが自分を鼓舞する気もあって、「こんなもの」という顔をしていればいるほど、担当者たちのプレッシャーは強まるという図式があったといえるかも知れない。本当に大度だったと思う。
だから、「いやいやまあまあ」に対するおほめやねぎらいの言葉は、まずおし戴いて頂いてから、次に京都新聞にお渡したい気持ちだ。特に、ぼくを見つ出し、書かせることにした人達に・・・。それにカットの山本容子さんを忘れてはならない。
カットは、とにかくよかった。
「いやあ、あれは、まず企画の勝利で、カットの素敵さだけでもってるんですよ」などとぼくがいってたのは、あながち通りいっぺんの謙遜ではない、けっこう本気だったといえる。
 なぜ教育が問題か
なぜ教育が問題かところで、今日、どうして「教育」がそれほど問題となるのだろうか。
この極めて高度に発達した現代産業社会では、家庭・学校・企業が、整然と配置されている。その分業的配置は、それ自体、一つの規律と規範を生みだしているといえるようだ。
ところが、この現代社会自体が、先行き不安の材料となっている。世界各所に渦教派やテロ集団がひそみ、公害が発生し、エネルギーが残り少ないといわれ、株価が大変動し、ガス爆発が起こり、地震パニックがささやかれる。政治家は信用できない。
全ては信用できない。カネだけはまあ信用できる。そうした、先の見えない、ちょうど、雪原で霧にまかれたみたいな状態に、ぼくたちはあるようだ。誰か、自信ありげな奴が、こっちだと叫べばつい尾いてゆきたくなる。いや、引き返すのが一番いいような気もする。
山では、こうした時には、視界がきくまで、じっと待つのが、生きのびる唯一の方法なのだが、世の中、山みたいに単純ではない。こうした不安やイライラが、教育というか、「学校」に向けられるのだろう。ちょっとばかり、エラソにいわしてもらえば、今こそ「学校」は冷静さを要求されているのだろう。
女性論も書けそう
これまでにぼくは人から、「山以外のものを書いてみませんか。たとえば、女性論などは・・・」などといわれることが、ままあった。で、ぼくは「いやあ、それは、まあ身体がいうこときかんようになってからの話ですよ」と答えていた。
でも、この連載が済んだら、ちょっと気分が変わってきたようだ。結婚論や女性論も書けるぞ、という気になってきた。これは、実際に書くかどうかは別として、たいした収穫であったと思う。
さて、かなり多くの人が、「どうして終わったのか」という、すぐには意味の取れないような質問を発した。ここに、明言すると、あれは予定通りの回数で終わったので、別に中断させられたのではない。ある手紙にあったように、どこかの圧力ではない。
たしかに、ぼくとしても、いいたいことの半分も書けなかった、という気がしないでもない。
<″いやいやまあまあ″が単行本となって日本全国にカムバックすることは百恵ちゃんのカムバックより確実無比のことと拝察いたしております。その時には是非加筆して下さいますよう・・・>と、ファンレターにはあった。
いずれ、書き足して単行本にすることが、ちょうとしんどい気もしているけれど、「いやいやまあまあ」を愛読して下さった諸氏に感謝を示す方法だと考えてはいる。(府立桂高校教諭)
「おわりはたて前で」ではなくて
「いやいやまあまあ」って、なんやらヘンなタイトルでしょう。でも、ぼくは、けっこう気に入っているのです。
担当記者の学芸部のクマさんは、
「ええっと、タイトルはやっぱり、オートバイを使いたいんで、〈ナナハン先生行状記〉とか〈ナナハン先生奮戦す〉とか……」
と、ちょっと口ごもりながらいいました。
「それもう、そんなんちょっと古いですョ」
とぼく、
「それに、ぼくのバイクは、ナナハンとちごて、ロクハンです。」
「はあん」
と、クマさんは、いやにがっかりした表情になったので、ぼくは少し気の毒になり、
「いやいや、ロクハンもナナハンも似たよなもんですよ」
「でもやっぱり、ロクハン先生よりナナハン先生の方が語呂がよいみたい……」
「まあまあ、よろしいやんか。まだ時間はありますし。なんか、デスクがいうたはったみ たいにパリイッとした奴、考えて下さい」
とぼくは、相手に押しつけることにしました。それをいち早く察したのか、クマさんは、
「センセイも考えて下さい。私も考えますから……」
そごでぼくは、ちょっと言ってみようか、という気になり、
「ちょっとあるんですョ。あのう、イヤイヤマアマアちゅうのんは、どうです」
「はあ?いや、いや、まあまあ、ねえ。なんか、もひとつ、はっきりしませんねえ」
「そうです。そのはっきりしんところがいいのとちがいますか」
このタイトル、ぜんぜん気に入られへんかったみたい。おかしいなあ、けっこうええはずやがなあ。 ‘
ラトックⅠ峰から帰ってきてしぼらくした秋口、ぼくたちビアフォ・カラコルム登攀隊は、京都で登頂報告会をやりました。報告会といっても、そんな普通のやり方ではなくて、朝日新聞、朝日放送を始めとする大口スポンサーだけを招待してのパーティです。場所はぼくが教師になったばかりの頃の教え子のケンシロウが、自分の店のクラブを開放してくれました。やり方といい、場所といい、それはえらくカッコウよかったのです。
このパーティに、やはりスポンサーだったキンシ正宗が、でっかい「こもかぶり」を寄贈してくれたのです。みんながんばって、マスで飲んだのだけれど、そんな三時間やそこらでは、とてもラチ、いやタルなどあきませんでした。
しかたなくぼくは、この巨大な「こもかぶり」を家に持帰り、床の間にでんと据えたのです。早く片付けないと、どんどん発酵が進んで駄目になるそうです。ぼくは、いろんな人を誘い、様ざまな人達が樽酒を飲みに、家にやってきました。
以前に桂高校にいて、その時からの付合いのN先生がやってきました。彼は、酔払うといつも、「おい、ナオキ」とぼくのことを呼ぶ癖があります。たとえば、ぼくの出版パーティなどで、彼が酔払ったとする。まあいつでもそうなのですが……。すると彼はぼくの悪口、本人はちっともそんな気はないらしいのですが、きいてる者にはそう聞こえるようなことをべらべらとしゃべる。東京の連中が、「あの人、高田さんと、どういう関係なのですか」ときいたそうです。
さて、彼は樽酒を一合ますでキューッ、キュッと一升近くを飲むと、例によって弁舌をふるい始めました。ほとんどしゃべり切っておいてもらってから、例によって、ぼくがチョコッ、チョコッと質問します。すると、
「いやいや、ちがいますよ。カーターはねえ……」
あるいはまた、
「いやいや、そうなんや、その通りやで」
そして、ぼくが、時に感心して、つまり、彼はぼくにできない見方や分析をすることがあって、「センセ、すごいなあ。その見方はおもろいで……」とゆうと、
「いやいや、まあまあそういうこっちゃ、ハッハッハァ」
いやまあびっくり。彼の場合、センテンスの冒頭はいつも〈いやいや〉とくるのです。こんなことは始めてでした。キンシ正宗の樽を飲んだ途端に、そんな具合になったのか。周りのみんなも、〈いやいや〉が耳につきだし、クスクス笑うのもいました。とまあ、そんな具合だったのです。でも、まだまだ樽の酒は減ってはいませんでした。
その何日か後、誰と一緒だったか忘れてしまいましたが、ぼく達は、まだ飽きもせず、もうかなり少なくなった酒を味わっていました。どういう話だったか、やっぱりこれも忘れていますが、ともかくぼくは急に腹が立ってきて、カッカして、
「けしからんやないか、そんなこと、だいたいやねえ……」
とやりだした時、いつの間にそこに来ていたのか、斜め後に立っていた中学生の息子が、ぼくの肩に手を置くと、
「まあまあまあまあ」
みんなは笑うし、ぼくもガックリして、苦笑しながら、「いやいや」などといっていたのです。
この〈まあまあ〉は、すでに冬のスキーの時、一緒だったグループで、すでにちょっと流行りかけていたようなのです。
〈いやいや〉に〈まあまあ〉。両方とも、何となくしまらない。けれど、なんとなくユーモラスで、それに、その時の状況で、何とでも使えるみたいなところが面白い。考えてみれば、この時、ぼくは、〈いやいやまあまあ〉というタイトルを決めたらしいのです。決めたとはいっても、絶対にいいと思った訳では決してなくて、なんとなく、まあまあやなあと思っただけなんです。だから、これにしますともなんとも言いませんでした。
新聞社は、いろいろ考えて、いくつかのタイトルを提示しました。でも、そのどれもぼくの気に入りませんでした。これならどうです、といって、クマさんが示した「ロクハン先生の山と谷」というのは、別に悪くもなかったけれど、よしそれにしようという気もしなかった。ぼくが考えた「月とスッポンポンの教育論」というのは、デスクや部長の、ふざけすぎてるという意見で没になったのだそうです。というような次第で、最終的には、「いやいやまあまあ」が、しつこく生き残ったという訳です。
さて、この単行本は、いまの話の新聞連載に何話かをつけ足したものなのですが、タイトルは、やっぱり問題となりました。ミネルヴァ書房のテラウチさんは、最初に会った時、 「この題は、なんとなく漠然としてますんで……。なんかいい題を考えなくては……。いい題を考えてみます」
といい、ぼくは、
「そうですネ、お願いします」
と答えていたのです。
何ヶ月かして今年になって、会うと、彼は突然なんだか複雑な顔をして、
「こんなことは初めてです」
といいます。ぼくは何のことやら分らず、
「はあ、何のことです」
「いやいや、タイトルですよ。これまで、あかんと一旦思ったものはあかんかったのに、どうしたことか、〈いやいやまあまあ〉が何となくいいように思えてきたんです。なんとなく変な気分なんですが……」
「へええ、そうですか。それでは〈いやいやまあまあ〉でゆくということですか」
と、ぼくは、なんだかホッとしたような気分でたづねました。
「そうします。いやあ、考えてみると、ぼくも、けっこう、いやいや、まあまあでやっとるんですねえ」
と彼は答え、ぼくは何となくカンくるい、黙ったままだったのです。
以上のような訳で、今、みなさんは、この『いやいやまあまあ』を手にされておる、ということです。
ただこの本は、テレビドラマみたいに、「実在するいかなる団体・個人とも関係ありません」という訳ではなく、みんなホントです。正確にいうと、ぼくは、ホントの積りです。自分自身も含めて、できるだけホントを書こうと努めました。ただ、ぼくの思い違いが、いちいち確かめませんでしたので、あるいはいくらかあるかも知れません。その際の責任の一切は、ぼく自身にあります。
多分、教育関係で、こうした種類の本がでたのは最初のことかも知れません。新聞連載が始まってしばらくすると、いくつかの団体から講演の依頼がありました。ぼくが面白いと思ったのは、ぼくの話を所望したのは、全て若い人達だったということでした。
連載が終った頃、奥丹の教員組合の青年部から、やはり講演の依頼がありました。「青年教師の集い」というのが、一泊二目であるのだそうです。
「いやあ、ほんとの話、センセイ相手にしゃべれるような教師じゃないんですよ、ぼくは」
正直いってぼくはあんまり気が進まなかったし、おまけに、本文で、若い教師のことをあんまりよく書いてないのです。面白くもないという気分でした。ところが相手はしつこく頼み込むし、聞いてみると、会場が、岩滝の公民館だというのです。岩滝といえば、ぼくの出生の地で、話にしか知らない土地です。「是非前夜からおいで下さい。若い連中が喜こびますから……」という話にのってぼくはOKしたのです。
ところが何日かして、家に、断わりの電話がポツリとあって、ぼく自身へ直接には何のコメントもないまま、この話はキャンセルされました。ふうん、どっちかからの庄力やろなあ。ぼくはそう思っただけです。そして同時に、やっぱり、ぼくが書いた通り、若い奴はあかんなあ。ぼくはなんだかホッともしたのでした。
いやいや。とはいえ、『いやいやまあまあ』は単なる読み物です。まあまあうまい具合に僕をおだてて、こんなものを書かせた新聞社のクマさん、それにこうした勝手な書き物を本にして頂いた「ミネルヴァ書房」さんとテラウチさん、素敵なさし絵と表紙で花をそえて頂いた山本容子さんに心より感謝しております。
といっても、これはほんとに「本音」でして、「おわりにたて前で」という訳では決してありません。重ねて御礼を申し上げます。
メーデーの日の夕
担当記者の学芸部のクマさんは、
「ええっと、タイトルはやっぱり、オートバイを使いたいんで、〈ナナハン先生行状記〉とか〈ナナハン先生奮戦す〉とか……」
と、ちょっと口ごもりながらいいました。
「それもう、そんなんちょっと古いですョ」
とぼく、
「それに、ぼくのバイクは、ナナハンとちごて、ロクハンです。」
「はあん」
と、クマさんは、いやにがっかりした表情になったので、ぼくは少し気の毒になり、
「いやいや、ロクハンもナナハンも似たよなもんですよ」
「でもやっぱり、ロクハン先生よりナナハン先生の方が語呂がよいみたい……」
「まあまあ、よろしいやんか。まだ時間はありますし。なんか、デスクがいうたはったみ たいにパリイッとした奴、考えて下さい」
とぼくは、相手に押しつけることにしました。それをいち早く察したのか、クマさんは、
「センセイも考えて下さい。私も考えますから……」
そごでぼくは、ちょっと言ってみようか、という気になり、
「ちょっとあるんですョ。あのう、イヤイヤマアマアちゅうのんは、どうです」
「はあ?いや、いや、まあまあ、ねえ。なんか、もひとつ、はっきりしませんねえ」
「そうです。そのはっきりしんところがいいのとちがいますか」
このタイトル、ぜんぜん気に入られへんかったみたい。おかしいなあ、けっこうええはずやがなあ。 ‘
ラトックⅠ峰から帰ってきてしぼらくした秋口、ぼくたちビアフォ・カラコルム登攀隊は、京都で登頂報告会をやりました。報告会といっても、そんな普通のやり方ではなくて、朝日新聞、朝日放送を始めとする大口スポンサーだけを招待してのパーティです。場所はぼくが教師になったばかりの頃の教え子のケンシロウが、自分の店のクラブを開放してくれました。やり方といい、場所といい、それはえらくカッコウよかったのです。
このパーティに、やはりスポンサーだったキンシ正宗が、でっかい「こもかぶり」を寄贈してくれたのです。みんながんばって、マスで飲んだのだけれど、そんな三時間やそこらでは、とてもラチ、いやタルなどあきませんでした。
しかたなくぼくは、この巨大な「こもかぶり」を家に持帰り、床の間にでんと据えたのです。早く片付けないと、どんどん発酵が進んで駄目になるそうです。ぼくは、いろんな人を誘い、様ざまな人達が樽酒を飲みに、家にやってきました。
以前に桂高校にいて、その時からの付合いのN先生がやってきました。彼は、酔払うといつも、「おい、ナオキ」とぼくのことを呼ぶ癖があります。たとえば、ぼくの出版パーティなどで、彼が酔払ったとする。まあいつでもそうなのですが……。すると彼はぼくの悪口、本人はちっともそんな気はないらしいのですが、きいてる者にはそう聞こえるようなことをべらべらとしゃべる。東京の連中が、「あの人、高田さんと、どういう関係なのですか」ときいたそうです。
さて、彼は樽酒を一合ますでキューッ、キュッと一升近くを飲むと、例によって弁舌をふるい始めました。ほとんどしゃべり切っておいてもらってから、例によって、ぼくがチョコッ、チョコッと質問します。すると、
「いやいや、ちがいますよ。カーターはねえ……」
あるいはまた、
「いやいや、そうなんや、その通りやで」
そして、ぼくが、時に感心して、つまり、彼はぼくにできない見方や分析をすることがあって、「センセ、すごいなあ。その見方はおもろいで……」とゆうと、
「いやいや、まあまあそういうこっちゃ、ハッハッハァ」
いやまあびっくり。彼の場合、センテンスの冒頭はいつも〈いやいや〉とくるのです。こんなことは始めてでした。キンシ正宗の樽を飲んだ途端に、そんな具合になったのか。周りのみんなも、〈いやいや〉が耳につきだし、クスクス笑うのもいました。とまあ、そんな具合だったのです。でも、まだまだ樽の酒は減ってはいませんでした。
その何日か後、誰と一緒だったか忘れてしまいましたが、ぼく達は、まだ飽きもせず、もうかなり少なくなった酒を味わっていました。どういう話だったか、やっぱりこれも忘れていますが、ともかくぼくは急に腹が立ってきて、カッカして、
「けしからんやないか、そんなこと、だいたいやねえ……」
とやりだした時、いつの間にそこに来ていたのか、斜め後に立っていた中学生の息子が、ぼくの肩に手を置くと、
「まあまあまあまあ」
みんなは笑うし、ぼくもガックリして、苦笑しながら、「いやいや」などといっていたのです。
この〈まあまあ〉は、すでに冬のスキーの時、一緒だったグループで、すでにちょっと流行りかけていたようなのです。
〈いやいや〉に〈まあまあ〉。両方とも、何となくしまらない。けれど、なんとなくユーモラスで、それに、その時の状況で、何とでも使えるみたいなところが面白い。考えてみれば、この時、ぼくは、〈いやいやまあまあ〉というタイトルを決めたらしいのです。決めたとはいっても、絶対にいいと思った訳では決してなくて、なんとなく、まあまあやなあと思っただけなんです。だから、これにしますともなんとも言いませんでした。
新聞社は、いろいろ考えて、いくつかのタイトルを提示しました。でも、そのどれもぼくの気に入りませんでした。これならどうです、といって、クマさんが示した「ロクハン先生の山と谷」というのは、別に悪くもなかったけれど、よしそれにしようという気もしなかった。ぼくが考えた「月とスッポンポンの教育論」というのは、デスクや部長の、ふざけすぎてるという意見で没になったのだそうです。というような次第で、最終的には、「いやいやまあまあ」が、しつこく生き残ったという訳です。
さて、この単行本は、いまの話の新聞連載に何話かをつけ足したものなのですが、タイトルは、やっぱり問題となりました。ミネルヴァ書房のテラウチさんは、最初に会った時、 「この題は、なんとなく漠然としてますんで……。なんかいい題を考えなくては……。いい題を考えてみます」
といい、ぼくは、
「そうですネ、お願いします」
と答えていたのです。
何ヶ月かして今年になって、会うと、彼は突然なんだか複雑な顔をして、
「こんなことは初めてです」
といいます。ぼくは何のことやら分らず、
「はあ、何のことです」
「いやいや、タイトルですよ。これまで、あかんと一旦思ったものはあかんかったのに、どうしたことか、〈いやいやまあまあ〉が何となくいいように思えてきたんです。なんとなく変な気分なんですが……」
「へええ、そうですか。それでは〈いやいやまあまあ〉でゆくということですか」
と、ぼくは、なんだかホッとしたような気分でたづねました。
「そうします。いやあ、考えてみると、ぼくも、けっこう、いやいや、まあまあでやっとるんですねえ」
と彼は答え、ぼくは何となくカンくるい、黙ったままだったのです。
以上のような訳で、今、みなさんは、この『いやいやまあまあ』を手にされておる、ということです。
ただこの本は、テレビドラマみたいに、「実在するいかなる団体・個人とも関係ありません」という訳ではなく、みんなホントです。正確にいうと、ぼくは、ホントの積りです。自分自身も含めて、できるだけホントを書こうと努めました。ただ、ぼくの思い違いが、いちいち確かめませんでしたので、あるいはいくらかあるかも知れません。その際の責任の一切は、ぼく自身にあります。
多分、教育関係で、こうした種類の本がでたのは最初のことかも知れません。新聞連載が始まってしばらくすると、いくつかの団体から講演の依頼がありました。ぼくが面白いと思ったのは、ぼくの話を所望したのは、全て若い人達だったということでした。
連載が終った頃、奥丹の教員組合の青年部から、やはり講演の依頼がありました。「青年教師の集い」というのが、一泊二目であるのだそうです。
「いやあ、ほんとの話、センセイ相手にしゃべれるような教師じゃないんですよ、ぼくは」
正直いってぼくはあんまり気が進まなかったし、おまけに、本文で、若い教師のことをあんまりよく書いてないのです。面白くもないという気分でした。ところが相手はしつこく頼み込むし、聞いてみると、会場が、岩滝の公民館だというのです。岩滝といえば、ぼくの出生の地で、話にしか知らない土地です。「是非前夜からおいで下さい。若い連中が喜こびますから……」という話にのってぼくはOKしたのです。
ところが何日かして、家に、断わりの電話がポツリとあって、ぼく自身へ直接には何のコメントもないまま、この話はキャンセルされました。ふうん、どっちかからの庄力やろなあ。ぼくはそう思っただけです。そして同時に、やっぱり、ぼくが書いた通り、若い奴はあかんなあ。ぼくはなんだかホッともしたのでした。
いやいや。とはいえ、『いやいやまあまあ』は単なる読み物です。まあまあうまい具合に僕をおだてて、こんなものを書かせた新聞社のクマさん、それにこうした勝手な書き物を本にして頂いた「ミネルヴァ書房」さんとテラウチさん、素敵なさし絵と表紙で花をそえて頂いた山本容子さんに心より感謝しております。
といっても、これはほんとに「本音」でして、「おわりにたて前で」という訳では決してありません。重ねて御礼を申し上げます。
メーデーの日の夕
23.教師はみんな特高かな
♣
ひところ、子供の自殺が相次いで起り、新聞誌上を賑わわしたことがありました。この頃では、あんまり多くないようで、あれはやっぱり、一時的な流行だったのかなと思う。
あの頃、自殺を防ごう、ということで、自殺防止のキャンペーンがありました。それによれば、自殺の前には、必ずサインがあるというか、前ぶれが現われる。たとえば、急に無口になるとか、死について興味をもって、それに関した本を読みだす……とか。だから、それらを素早くキャッチして、自殺を防ごう、というんです。
 なんだか、けったいな気分でした。だって本人が、死にたいと本当に思っているのなら、どんなことをしてでも死ぬでしょう。問題は、なぜ生きる望みをなくしたのか、ということであるはずで、どうして止めようか、ではないように思ったんです。
なんだか、けったいな気分でした。だって本人が、死にたいと本当に思っているのなら、どんなことをしてでも死ぬでしょう。問題は、なぜ生きる望みをなくしたのか、ということであるはずで、どうして止めようか、ではないように思ったんです。
その頃、中学生だった娘が、新聞を見ながら、突然、「私が自殺したらどうする」ときいたものです。
「どうするて、死んだらしまいやがな」
と、ぼくは素っとぼけて答えました。
「もし死んだら、どう思う」
と、おっかぶせて娘はきき、ぼくは、なお、
「どう思うかなあ。そんなこと考えたこともないし、まあその時にならんと分らんな。お前死にたい思とんのか。もし死のう思ってたら、止めようもないがな」
と、ぼくは、わざと素気なく答えていました。すると娘は、憤然として、あきれたように、
「それでも親か」
といったものでした。
彼女が、小学生だった頃、ぼくは、高校生の女の子二人と娘・息子の四人を連れて、信州ヘスキーに行ったことがありました。みんなで滑っているうちに、娘の姿が見当らなくなったのです。いくら周りを見回しても、どこにもいません。もしかしたら、もう滑るのがいやになっいて宿に帰ったのかも知れない。確かめるために、宿まで見に戻ろうか、と一瞬考えました。でも、よし宿に帰っていたら、それはそれで、もう安全です。小学校三年にもなっているのに、どうして勝手に帰ったのか、となじるのも変な具合だという気もしました。もし帰っていなかったら、ぼくは余計にイライラし、見つけた時にどなりつけることになるだろう。どっちにしても面白くない。
こんなことを、素早く考え、かなり心配だったけど、ほっとこうと決めたんです。ものの20分もしないうちに、ゲレンデで一人楽しそうに滑っている娘を、ぼくは見出していたのです。
去年のこと、家族で、やはりスキーにいった時、一番下の五歳の娘を、彼女はそり滑り専門でスキーができないので、ゲレンデのレストハウスに待たして、みんなで滑っていました。突然アナウンスがあり、
「タカダさん、お子達が迷子になっておられます、至急レストハウスにお戻り下さい」
いったい何事かと、ぶっとばして、レストハウスに戻ったら、娘は一人ポツンとストーブにあたっておりました。「おねえちゃんが三人、話しかけてきて、名前をきいた」というのです。
多分、一人置いとかれて、淋しくてベソでもかいていたのでしょう。それにしても、何とおせっかいな奴がいるもんだ。ぼくは頭にきて、娘に、
「お前が、ベソかいてるから間違われるんじゃ。バカモン」
と、どなりつけたのです。
♣♣
この頃では、自殺にかわって、校内暴力や家庭内暴力や非行や暴走族などが大流行のようです。
校内暴力というのは、どうやら中学の専売特許で、高校にはあんまりないみたい。ただ高校にも家庭内暴力はあるらしい。教室で、そうした話をすると、身に憶えがあるという感じの反応を示す生徒が多いのです。ぼくは、話のついでに、「親かて信用できへんぞ。晩ねていて、気がついたら首にひもが巻きついてるかも知れんぞ。そうされるような仕打ちはしてへんか」などとおどかしたりします。生徒はみんなショックで、少々考え込んでしまうようです。
それから、いわゆる非行や暴走族というのも、ごくありふれた出来ごとのようです。
それにしても〈非行〉ということばには、どうも少なからずある抵抗を感じてしまいます。〈非行少年〉は、いつかの時代の〈非国民〉に似て、中味の吟味はそっちのけの、レッテルのはりつけという気がしてしまうのです。そうすると、教師はみんな特高かな。まあ、ぼくは、そういう時代は、話でしか知らないのですが……。
「いいことはいい悪いことは悪いと云おう」などと叫ぶ教師がいる。なにをいうとるんか、という気がします。きまっとるやないか、そんなこと。問題は、いいか悪いか分らん部分なんです。明確に分る部分について、これまで知らんふりしていたとしたら、それは論外。分らん部分までをも、勝手にどっちかに決めて、それを押しつけて強要したら、それは権力的な強制でしかないのではなかろうか。そんな気がします。
ここに、〈高校生の意識調査〉というデータがあります。一九六九年の暮の朝日新聞にのったもので、平均的都立高校を対象に、回答回収総数七九二、五九問のアンケートによる調査です。それによれば、
教師に多いタイプ———表面だけとりつくろう偽善者。月給めあてだけのサラリーマン。規則ばかり押しつける役人根性。一方、生徒が教師に求めているのは信念で、うわべをとりつくろわない生の人間性といったものである、となっています。
六九年といえば、いまから十二年前、ひと昔以上も前なのですが、生徒が見た教師の姿は今もあんまり変らんのではないか、という気がします。いや、まだ、あの頃は、生徒は、それなりに真剣に教師を見つめ、批判した。そこには、まだ希望があったのかも知れません。だから彼等は、教師にある信頼をもって学園紛争を起こしたのかも知れない。ぼくにはそう思えます。ところがいまや、もうそんなもんではない。
教師は教師。うまい具合に立回り、睨まれんように……。腹立ててもしやあない。むかつくだけ、勉強の防げになるし……。それにしても、つっぱってるワルの連中は、アホや。あれはなんにも得にならんのに。けど、気持はよう分る。
教師と生徒の距離はもう宇宙的にひらいてしまったのかも知れません。
♣♣♣
教室で、四十数人の生徒を前にして、ぼくは教壇に立っています。小さな空間に、それらはぎっしりと詰め込まれた感じで、四十数個の顔が、二次元的に拡がっており、みんな無表情で、なんだか仮面の配列の様です。
その時、教師の顔も、ただ無意味に、パクパクと口を開け閉めする奇妙な仮面——生徒の眼には、きっとそう映っているのでしょう。
一つの教室空間に配列された生徒には、共通点といえば、もしかしたら、生活年齢が同じである、という一つことしかない。そういえるかも知れません。みんながみんな親がちがう。家もちがう。家の職業もちがう。育ちがちがう。家の喰い物の好みもちがう。
一つ一つの顔の後には、それらを生みだした一組の男女があり、その後にはまたその男女を生みだした二組のしわくちゃの男女がいて、その後にはまた……。そして、それらはみんなみんな、異なった顔で、異なった生い立ちと生活史をもっていて……。
そうした妄想みたいなものが一瞬、ぼくの頭に拡がると、教室はモザイクみたいに顔でうずまってしまい、ぼくはただ呆然と立ちすくんでしまいます。時として、そういうことがあるのです。
考えてみるまでもなく、生徒一人ひとりはみんなちがう。ことさらにいうまでもなく、そんなことは誰でも分っているはずです。ただ学校というととろは、そんな認識やたて前とは無関係に、生徒という名の画一化されたものを対象に組立てられたシステムであるかのようです。
生徒の画一化が問題だとなげきながら、教師達は、その問題を解決するために、自からの集団を画一化しようとしたりする。なんともけったいな話です。
もともと、日本の大衆教育制度は、富国強兵を目標に、軍隊の部品としての兵卒を作るために組立てられた。敗戦後の民主主義教育で、戦前の教育理念は完全に否定はされたものの、富国強兵にとってかわった高度成長のかけ声のもと、学校は産業兵士の生産工場であったのではないだろうか。
そのなかで、教師は、個性の尊重という空念仏を唱えながら、生徒ともども、ただひたすら、画一化してきたといえなくもない。
♣♣♣♣
どこの国でも、どの時代であっても、もともと若者は不安定で激しやすく暴力的なものだと思うのです。
ぼく自身だって、少々身に憶えもあります。ただ昔は、いまみたいに、すぐ新聞種になったり、警察が入ってきたり、というようなことはなかったのですが……。
だから、「あれは、いつかの学園紛争が、もっと若い層に移行したようなもんだ」という見解も一理あるという気もします。また、若者は暴力的なもので、そうした時期を通過して大人になるのだから、[まあ、いってみればはしかみたいなもんだ。伝染性もあるし……」などといわれると、なるほど、とも思います。
たしかに、いまの世の中、若者には極めて住みずらい状況になっているようです。目本はいまや大国、大人の、いや老年の国で、暴力に対する許容度が全くない。もしかりに、いまの時代に信長がいたとしたら、大犯罪人になっていたでしょうし、勤王の志士たちはみんな少年院送り、なんてことになったかも知れません。
だいたいいまの世の中、若者だけに限らず、みんな住みずらく息苦しいのかも知れません。まあ、すこし前は、その息苦しさの原因を見極めたら、それをどうにかできそうな気がした。ところがいまや、だいたいあんまりよく見極めがつかないし、なんやらよく分らない。分ったところでどうにもならんという気がしてしまう。ええいとばかり、いちばん手近なところに衝動的につき当り発散するという世の中みたい。
とすれば、校内暴力も、社会状況の反映ということになるのかしらん。
いまぼくの高校も平穏の限りだけれど、ひと昔前には、けっこう校内暴力みたいなこともありました。あんまりなぐられそうにもなかったけれど、オヤジや上級生に、散々なぐられたり、けんかしたりした経験のあるぼくは、なぐられたかて死なへんし、と思っていました。生徒だって、セクトの内ゲバじゃあるまいし、殺す気など全くないはずです。
先頃の新聞で、英国の教員組合が、生徒による傷害に備えて、全員保険に加入したということを知って、さすがだなあ、と変なところで感心してしまいました。
これからも分るように、校内暴力というようなものは、日本だけに限らず、先進国といわれる国に共通ですし、非行は中国でも問題になっている。
社会のひずみは、いちばん純な弱い部分に病理的に表われるのかも知れません。そうだとしても、この病める文明諸国を一気に治療するなんてことは、ちょっと誰にもできそうにありません。それこそ、カール・セーガンさんじゃないけれど、そうした危機を切りぬけた他の銀河系の宇宙人にでも聞いてみないと分るもんじゃないようです。
学者からオバチャンまで、みんな一家言あり、いろいろとおっしゃる。そのどれも正しいという気はします。しかし、それでどうなるもんでもない、という気もする。
♣♣♣♣♣
いまや世の中、教育教育と大変なさわぎ。新聞・テレビ、週刊誌と、アスコミあげてなんだかブームの感じさえします。まあ、それだからこそ、ぼくなんぞが、新聞に、教育論を書かされるような破目にもなったのでしょうが……。
でも考えてみれば、教育は、戦後ずっと、問題とされてきたように思うんです。日本国が、保守・革新と二大陣営に分れて対立抗争するなかで、教育は、その陣取合戦のフィールドであったのかも知れません。これは当然のことであって、次の時代を担う若者を育てるのが教育なのですから、両陣営は、自分達のイメージする人間を造ろうとして、教育で争った。教育を制するものは日本を制する、と云われたのかどうか知りませんが、とにかく、そんな風だった。そうした状況がつづくうちに、教育の荒廃が叫ばれだします。これは、政治が教育を政争の具にした当然の報いだ、という人もいました。もう十年以上も前の話です。
その頃の状況から考えれば、今の様子は、もう荒廃なんてもんではない。無いのです。教育なんて何にもない。そんな気がしてきます。
管理は教育ではないし、犬に芸を仕込むような訓練も教育とははづれる。
こういう状況になったのは、でも、教師が好んでそうした訳では決してないし、親が放任したからでもないのではないか。教師が総ざんげして良くなる問題ではないし、『父よ母よ』と呼びかけて解決する訳でもない。「人の子も叱ろう」とスローガンをかかげても、基本的には大して変らない。
誰が悪いというものではなく、こういう方向に、どうしようもなく時代が動いてきてしまったというべきなのでしょう。何かが悪いとしたら、旧い状況で出来たシステムをそのまま守っているのが悪いのかも知れません。
高校の頃、漢文で「性善説」「性悪説」を習いました。ぼくには「性善説」のほうがピンときたようで、〈孺子(ジュシ)のまさに井(セイ)に入らんとするを見れば、人みな怵惕惻隠(ジュッテキソクイン)の心あり〉なんていうのは、いまでも憶えています。(注:子供が井戸に落ちたら、誰でも驚き慌て可哀想だと思うというのが、この漢文の意で、「性善説」はここから始まる)
ところで、教師はみんな性は善なる人ばかりなんでしょうが、いまや、「性善説」を信じる教師はあたかもいないみたいです。管理と処罰がシステムとして強化されてくると、処罰の平等が問題となって、主義主張を別にして生徒を疑ってかからざるを得なくなる。夜更けの路上では、少年補導員の町内会のオジサンが、大学生をとっつかまえて、警官の職務質問みたいなことをやり、「ウソつけ、高校生やろ」などとやりだす。
教育というのは、騙されるのを承知したうえで、許容はせずに受容し、相手を信ずるというところにしか成立しないのではないかと、ぼくにはそう思えるのです。
いま、人みなイライラし、世の中の仕組みはとてつもなく複雑で、そうであるが故に、人は単純明快なものにあこがれ、また単純に反応しようとするかのようです。
やがていつの日か、学校は、今からは想像もつかない位、変るかも知れません。そして、その時、社会のシステムもやっぱり、今とはちがったものになっているでしょう。
ひところ、子供の自殺が相次いで起り、新聞誌上を賑わわしたことがありました。この頃では、あんまり多くないようで、あれはやっぱり、一時的な流行だったのかなと思う。
あの頃、自殺を防ごう、ということで、自殺防止のキャンペーンがありました。それによれば、自殺の前には、必ずサインがあるというか、前ぶれが現われる。たとえば、急に無口になるとか、死について興味をもって、それに関した本を読みだす……とか。だから、それらを素早くキャッチして、自殺を防ごう、というんです。
 なんだか、けったいな気分でした。だって本人が、死にたいと本当に思っているのなら、どんなことをしてでも死ぬでしょう。問題は、なぜ生きる望みをなくしたのか、ということであるはずで、どうして止めようか、ではないように思ったんです。
なんだか、けったいな気分でした。だって本人が、死にたいと本当に思っているのなら、どんなことをしてでも死ぬでしょう。問題は、なぜ生きる望みをなくしたのか、ということであるはずで、どうして止めようか、ではないように思ったんです。その頃、中学生だった娘が、新聞を見ながら、突然、「私が自殺したらどうする」ときいたものです。
「どうするて、死んだらしまいやがな」
と、ぼくは素っとぼけて答えました。
「もし死んだら、どう思う」
と、おっかぶせて娘はきき、ぼくは、なお、
「どう思うかなあ。そんなこと考えたこともないし、まあその時にならんと分らんな。お前死にたい思とんのか。もし死のう思ってたら、止めようもないがな」
と、ぼくは、わざと素気なく答えていました。すると娘は、憤然として、あきれたように、
「それでも親か」
といったものでした。
彼女が、小学生だった頃、ぼくは、高校生の女の子二人と娘・息子の四人を連れて、信州ヘスキーに行ったことがありました。みんなで滑っているうちに、娘の姿が見当らなくなったのです。いくら周りを見回しても、どこにもいません。もしかしたら、もう滑るのがいやになっいて宿に帰ったのかも知れない。確かめるために、宿まで見に戻ろうか、と一瞬考えました。でも、よし宿に帰っていたら、それはそれで、もう安全です。小学校三年にもなっているのに、どうして勝手に帰ったのか、となじるのも変な具合だという気もしました。もし帰っていなかったら、ぼくは余計にイライラし、見つけた時にどなりつけることになるだろう。どっちにしても面白くない。
こんなことを、素早く考え、かなり心配だったけど、ほっとこうと決めたんです。ものの20分もしないうちに、ゲレンデで一人楽しそうに滑っている娘を、ぼくは見出していたのです。
去年のこと、家族で、やはりスキーにいった時、一番下の五歳の娘を、彼女はそり滑り専門でスキーができないので、ゲレンデのレストハウスに待たして、みんなで滑っていました。突然アナウンスがあり、
「タカダさん、お子達が迷子になっておられます、至急レストハウスにお戻り下さい」
いったい何事かと、ぶっとばして、レストハウスに戻ったら、娘は一人ポツンとストーブにあたっておりました。「おねえちゃんが三人、話しかけてきて、名前をきいた」というのです。
多分、一人置いとかれて、淋しくてベソでもかいていたのでしょう。それにしても、何とおせっかいな奴がいるもんだ。ぼくは頭にきて、娘に、
「お前が、ベソかいてるから間違われるんじゃ。バカモン」
と、どなりつけたのです。
♣♣
この頃では、自殺にかわって、校内暴力や家庭内暴力や非行や暴走族などが大流行のようです。
校内暴力というのは、どうやら中学の専売特許で、高校にはあんまりないみたい。ただ高校にも家庭内暴力はあるらしい。教室で、そうした話をすると、身に憶えがあるという感じの反応を示す生徒が多いのです。ぼくは、話のついでに、「親かて信用できへんぞ。晩ねていて、気がついたら首にひもが巻きついてるかも知れんぞ。そうされるような仕打ちはしてへんか」などとおどかしたりします。生徒はみんなショックで、少々考え込んでしまうようです。
それから、いわゆる非行や暴走族というのも、ごくありふれた出来ごとのようです。
それにしても〈非行〉ということばには、どうも少なからずある抵抗を感じてしまいます。〈非行少年〉は、いつかの時代の〈非国民〉に似て、中味の吟味はそっちのけの、レッテルのはりつけという気がしてしまうのです。そうすると、教師はみんな特高かな。まあ、ぼくは、そういう時代は、話でしか知らないのですが……。
「いいことはいい悪いことは悪いと云おう」などと叫ぶ教師がいる。なにをいうとるんか、という気がします。きまっとるやないか、そんなこと。問題は、いいか悪いか分らん部分なんです。明確に分る部分について、これまで知らんふりしていたとしたら、それは論外。分らん部分までをも、勝手にどっちかに決めて、それを押しつけて強要したら、それは権力的な強制でしかないのではなかろうか。そんな気がします。
ここに、〈高校生の意識調査〉というデータがあります。一九六九年の暮の朝日新聞にのったもので、平均的都立高校を対象に、回答回収総数七九二、五九問のアンケートによる調査です。それによれば、
教師に多いタイプ———表面だけとりつくろう偽善者。月給めあてだけのサラリーマン。規則ばかり押しつける役人根性。一方、生徒が教師に求めているのは信念で、うわべをとりつくろわない生の人間性といったものである、となっています。
六九年といえば、いまから十二年前、ひと昔以上も前なのですが、生徒が見た教師の姿は今もあんまり変らんのではないか、という気がします。いや、まだ、あの頃は、生徒は、それなりに真剣に教師を見つめ、批判した。そこには、まだ希望があったのかも知れません。だから彼等は、教師にある信頼をもって学園紛争を起こしたのかも知れない。ぼくにはそう思えます。ところがいまや、もうそんなもんではない。
教師は教師。うまい具合に立回り、睨まれんように……。腹立ててもしやあない。むかつくだけ、勉強の防げになるし……。それにしても、つっぱってるワルの連中は、アホや。あれはなんにも得にならんのに。けど、気持はよう分る。
教師と生徒の距離はもう宇宙的にひらいてしまったのかも知れません。
♣♣♣
教室で、四十数人の生徒を前にして、ぼくは教壇に立っています。小さな空間に、それらはぎっしりと詰め込まれた感じで、四十数個の顔が、二次元的に拡がっており、みんな無表情で、なんだか仮面の配列の様です。
その時、教師の顔も、ただ無意味に、パクパクと口を開け閉めする奇妙な仮面——生徒の眼には、きっとそう映っているのでしょう。
一つの教室空間に配列された生徒には、共通点といえば、もしかしたら、生活年齢が同じである、という一つことしかない。そういえるかも知れません。みんながみんな親がちがう。家もちがう。家の職業もちがう。育ちがちがう。家の喰い物の好みもちがう。
一つ一つの顔の後には、それらを生みだした一組の男女があり、その後にはまたその男女を生みだした二組のしわくちゃの男女がいて、その後にはまた……。そして、それらはみんなみんな、異なった顔で、異なった生い立ちと生活史をもっていて……。
そうした妄想みたいなものが一瞬、ぼくの頭に拡がると、教室はモザイクみたいに顔でうずまってしまい、ぼくはただ呆然と立ちすくんでしまいます。時として、そういうことがあるのです。
考えてみるまでもなく、生徒一人ひとりはみんなちがう。ことさらにいうまでもなく、そんなことは誰でも分っているはずです。ただ学校というととろは、そんな認識やたて前とは無関係に、生徒という名の画一化されたものを対象に組立てられたシステムであるかのようです。
生徒の画一化が問題だとなげきながら、教師達は、その問題を解決するために、自からの集団を画一化しようとしたりする。なんともけったいな話です。
もともと、日本の大衆教育制度は、富国強兵を目標に、軍隊の部品としての兵卒を作るために組立てられた。敗戦後の民主主義教育で、戦前の教育理念は完全に否定はされたものの、富国強兵にとってかわった高度成長のかけ声のもと、学校は産業兵士の生産工場であったのではないだろうか。
そのなかで、教師は、個性の尊重という空念仏を唱えながら、生徒ともども、ただひたすら、画一化してきたといえなくもない。
♣♣♣♣
どこの国でも、どの時代であっても、もともと若者は不安定で激しやすく暴力的なものだと思うのです。
ぼく自身だって、少々身に憶えもあります。ただ昔は、いまみたいに、すぐ新聞種になったり、警察が入ってきたり、というようなことはなかったのですが……。
だから、「あれは、いつかの学園紛争が、もっと若い層に移行したようなもんだ」という見解も一理あるという気もします。また、若者は暴力的なもので、そうした時期を通過して大人になるのだから、[まあ、いってみればはしかみたいなもんだ。伝染性もあるし……」などといわれると、なるほど、とも思います。
たしかに、いまの世の中、若者には極めて住みずらい状況になっているようです。目本はいまや大国、大人の、いや老年の国で、暴力に対する許容度が全くない。もしかりに、いまの時代に信長がいたとしたら、大犯罪人になっていたでしょうし、勤王の志士たちはみんな少年院送り、なんてことになったかも知れません。
だいたいいまの世の中、若者だけに限らず、みんな住みずらく息苦しいのかも知れません。まあ、すこし前は、その息苦しさの原因を見極めたら、それをどうにかできそうな気がした。ところがいまや、だいたいあんまりよく見極めがつかないし、なんやらよく分らない。分ったところでどうにもならんという気がしてしまう。ええいとばかり、いちばん手近なところに衝動的につき当り発散するという世の中みたい。
とすれば、校内暴力も、社会状況の反映ということになるのかしらん。
いまぼくの高校も平穏の限りだけれど、ひと昔前には、けっこう校内暴力みたいなこともありました。あんまりなぐられそうにもなかったけれど、オヤジや上級生に、散々なぐられたり、けんかしたりした経験のあるぼくは、なぐられたかて死なへんし、と思っていました。生徒だって、セクトの内ゲバじゃあるまいし、殺す気など全くないはずです。
先頃の新聞で、英国の教員組合が、生徒による傷害に備えて、全員保険に加入したということを知って、さすがだなあ、と変なところで感心してしまいました。
これからも分るように、校内暴力というようなものは、日本だけに限らず、先進国といわれる国に共通ですし、非行は中国でも問題になっている。
社会のひずみは、いちばん純な弱い部分に病理的に表われるのかも知れません。そうだとしても、この病める文明諸国を一気に治療するなんてことは、ちょっと誰にもできそうにありません。それこそ、カール・セーガンさんじゃないけれど、そうした危機を切りぬけた他の銀河系の宇宙人にでも聞いてみないと分るもんじゃないようです。
学者からオバチャンまで、みんな一家言あり、いろいろとおっしゃる。そのどれも正しいという気はします。しかし、それでどうなるもんでもない、という気もする。
♣♣♣♣♣
いまや世の中、教育教育と大変なさわぎ。新聞・テレビ、週刊誌と、アスコミあげてなんだかブームの感じさえします。まあ、それだからこそ、ぼくなんぞが、新聞に、教育論を書かされるような破目にもなったのでしょうが……。
でも考えてみれば、教育は、戦後ずっと、問題とされてきたように思うんです。日本国が、保守・革新と二大陣営に分れて対立抗争するなかで、教育は、その陣取合戦のフィールドであったのかも知れません。これは当然のことであって、次の時代を担う若者を育てるのが教育なのですから、両陣営は、自分達のイメージする人間を造ろうとして、教育で争った。教育を制するものは日本を制する、と云われたのかどうか知りませんが、とにかく、そんな風だった。そうした状況がつづくうちに、教育の荒廃が叫ばれだします。これは、政治が教育を政争の具にした当然の報いだ、という人もいました。もう十年以上も前の話です。
その頃の状況から考えれば、今の様子は、もう荒廃なんてもんではない。無いのです。教育なんて何にもない。そんな気がしてきます。
管理は教育ではないし、犬に芸を仕込むような訓練も教育とははづれる。
こういう状況になったのは、でも、教師が好んでそうした訳では決してないし、親が放任したからでもないのではないか。教師が総ざんげして良くなる問題ではないし、『父よ母よ』と呼びかけて解決する訳でもない。「人の子も叱ろう」とスローガンをかかげても、基本的には大して変らない。
誰が悪いというものではなく、こういう方向に、どうしようもなく時代が動いてきてしまったというべきなのでしょう。何かが悪いとしたら、旧い状況で出来たシステムをそのまま守っているのが悪いのかも知れません。
高校の頃、漢文で「性善説」「性悪説」を習いました。ぼくには「性善説」のほうがピンときたようで、〈孺子(ジュシ)のまさに井(セイ)に入らんとするを見れば、人みな怵惕惻隠(ジュッテキソクイン)の心あり〉なんていうのは、いまでも憶えています。(注:子供が井戸に落ちたら、誰でも驚き慌て可哀想だと思うというのが、この漢文の意で、「性善説」はここから始まる)
ところで、教師はみんな性は善なる人ばかりなんでしょうが、いまや、「性善説」を信じる教師はあたかもいないみたいです。管理と処罰がシステムとして強化されてくると、処罰の平等が問題となって、主義主張を別にして生徒を疑ってかからざるを得なくなる。夜更けの路上では、少年補導員の町内会のオジサンが、大学生をとっつかまえて、警官の職務質問みたいなことをやり、「ウソつけ、高校生やろ」などとやりだす。
教育というのは、騙されるのを承知したうえで、許容はせずに受容し、相手を信ずるというところにしか成立しないのではないかと、ぼくにはそう思えるのです。
いま、人みなイライラし、世の中の仕組みはとてつもなく複雑で、そうであるが故に、人は単純明快なものにあこがれ、また単純に反応しようとするかのようです。
やがていつの日か、学校は、今からは想像もつかない位、変るかも知れません。そして、その時、社会のシステムもやっぱり、今とはちがったものになっているでしょう。
22.ほんとの教育者てあるんか
♣
学生の時、春の穂高に登っての帰り路、松本駅にたどり着き、京都までの切符を買うと十円しか残りませんでした。夜行は出たあとで、ここのベンチでの夜明かしを決め、その十円でアンパンをひとつ買いました。両の手で、包み込むような気持で、それを喰べようとした時です。一人の男が、ジッとこっちを見ているのに気付いたのです。どうみても、それはルンペンでした。
ちょっとかじったのですが、その男はまだぼくのアンパンを見つめていました。なんだか申し訳ないような気分になって、ぼくは、パンを半分割って、彼に与えたのです。
これがきっかけで、彼はぼくに色んな話をしました。驚いたことに、彼は国立、いわゆる帝大出なのでした。哲学科だそうで、カントやヘーゲルなどがポンポンとびだしました。その人生哲学や世相批判は、社会の枠外からの視点にたってのものであるためか、なかなか面白かった。
当時の山登りの服装というのは、今に較べれば、なんともくすんだもので、帰りともなれば、服はボロボロ、髭ボウボウで、ちょっと見にはルンペンさながらでした。おまけに、帰りの金など無いことがままあり、なじみの旅館のオバチャンに借りたり、駅前の派出所に頼みこんだり、どっちかといえば乞食みたいなもんでした。
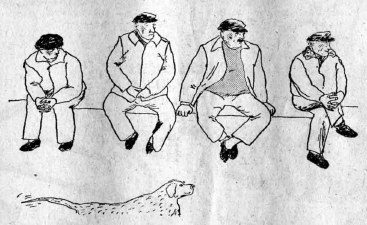 その所為か、よくルンペンに話しかけられることがあったのです。あの時、御在所岳で岩登りをしての帰りもそうでした。ぼく達は名古屋駅まで帰り着き、テレビ塔の下で寝るべく、歩いていったのです。そしたら、一人のルンペンが、「駅の方がいい、一諸にゆこう」と誘うので、また駅まで引返した訳です。
その所為か、よくルンペンに話しかけられることがあったのです。あの時、御在所岳で岩登りをしての帰りもそうでした。ぼく達は名古屋駅まで帰り着き、テレビ塔の下で寝るべく、歩いていったのです。そしたら、一人のルンペンが、「駅の方がいい、一諸にゆこう」と誘うので、また駅まで引返した訳です。
この男も、なかなか面白かった。彼は、朝鮮人で、戦時中、北海道の炭坑で強制労働に従事させられていた。真冬に、そこを脱走した時の九死に一生の恐しい体験を克明に語りました。彼はこういいました。
「人間鍛錬すれば、何でも出来る。オレはいまどんなに寒い真冬でも、新聞紙一枚で、アスファルトにごろ寝できるよ」
ぼくは、ただ感心していました。
こうした経験は、ぼくに、人は外見だけでは判断できないもんだ、ということを教えたようでした。
二回目のカラコルムに行った時、スワット・ヒマラヤの山中で、羊と共に暮らす山人達からも、多くの事を学びました。なによりも、物質的に全く恵まれない彼らの、その卑屈さの全くない誇り高さに、腹立たしさを覚えながらも感服し、やがて、感化を受けたのです。
——学校よりも、あらゆるタイプの人間のそろっている実社会こそが真の意味での
もっとも有効な教育の場所といえよう。実社会での結合・敵対等の一切の人間関係を
通じて、万人は万人に対する教育者としての役割を知らないうちにはたしているので
ある(家永三郎)——
♣♣
数年前、シンナーの悪習から抜けられず、とうとう病院に入れられた生徒がいました。彼が退院してきて、ぼくの授業に出てきた日、出欠をとって初めて彼がいるのに気付き、 「オッ、出てきたんか。それでどんな具合やった」
と、声をかけたのです。
「学校とおんなじことですよ。テレビが見れるだけいいくらいや。それにしても、今の学校も教師もひどすぎる」
と、勢い込んで、彼は不平を鳴らしつづけました。彼はぼくとの問答の中で、学校や教師はどうあってほしいかという例として、何度も何べんも、テレビの「学園もの」を引きあいに出しました。クラスの全員は、シンとして、彼とぼくとのやりとりを聞いていたのです。
「そらお前、テレビの見すぎやで。あんなもん、お話にすぎんのじゃ」
と、ぼくは断言しました。でも、その時、彼は期待が大きすぎるのだ。学校や教師に多くを望みすぎるのだ。そんな気がしたのです。そして、もしかしたら、彼はそうした現実と自分の幻想とのギャップにもだえ、シンナーを吸うことによって、空想の世界に遊ぶのではなかろうか。そんなことを考えたのでした。
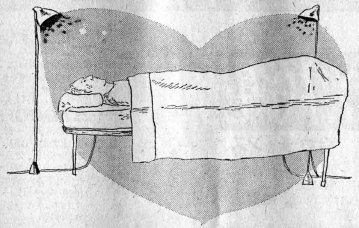 ぼく自身、自分の学校生活をふり返ってみて、彼のような発想は、全くなかった。ぼくにとって、教師とは、のっけから、多分に偽善的であらねばならぬ職業についている人に過ぎなかった。
ぼく自身、自分の学校生活をふり返ってみて、彼のような発想は、全くなかった。ぼくにとって、教師とは、のっけから、多分に偽善的であらねばならぬ職業についている人に過ぎなかった。
だから、人事院総裁だった佐藤達夫氏の次のような言葉などは、とても、まともに受取れない。なんだかあっ気にとられる。
——教育基本法の第一条は、教育の目的として、「教育は人格の完成をめざし……
自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わねばならない」と定め
ている。私が学校に通ったころは、むろんこのような法律のできるずっと前のことだ
ったけれども、小・中学校時代に私の教わった先生たちは、どの一人を思いだしてみ
ても、まさに、この理想にそった教育をしてくれたといっていい。これはほんとうに
幸いだったと思っている——
ほんまかいなあと思う。ほんとにそう信じ込める人がいたらそれこそ幸せだなあという気がします。これに較べれば、ゴールドブレンドのコマーシャルの、指揮者・岩城宏之などは、まことに心安まることをいっている。
——ぼくはいろんな人が[わが尊敬する師」などと生涯かけて尊敬し、お慕いなさ
れているのを読んだりしても、どうもピンと来ないのだ。そういう偉大な真の教育者
にめぐりあった運のよい人をうらやましいとは思う。でも百パーセント尊敬され得る
人、および百パーセント人をあがめる人の両方を、ぼくは信じない。(中略)少年時
代にぼくにおとな不信の精神を植えつけてくれた教育者でもあったおとなたちに、感
謝しないでもない——
どうやら、〈良い教師はない。よい生徒があるばかりだ(山根銀二)〉ということになるらしい。
♣♣♣
ぼくはよく人から、「ほんとに学校の先生なんですか」とか、「とても先生には見えません」などといわれます。まことにケッタイな話なのですが、そういわれると、なんだかホッとしたりする。
ところが、まれに「やはりタカダさんは先生なんてすねえ。安心しました」などと、その真意をつかみかねるようなことを云われることがある。なんだか、ガックリきて、ドッと疲れるような感じなのです。
ずっと昔、まだ車が少々珍しかった頃、ぼくは、新車の定期整備に工場に行きました。一人の中年のオッサンが、親しげに話しかけて来たのです。彼も整備に来たらしい。
「どうでっか。車の調子は。ああ、そうですか。私のも調子は上々でっせ。これ買うてよかった思うてます」
彼は矢つぎ早に話し、ぼくは適当に合槌を打っていました。そのうちに彼は、
「お商売は、なにやったはりますねん」
それ来た、とぼくは思いました。ぼくの一番いやな質問です。ところが、人は直ぐにこの問いを発する。ぼくは、やや言い澱んで、
「教師です」
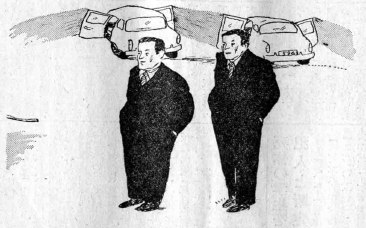 とたんに、そのオッサンの顔が引きつった。「はあ、そうですか」とかなんとか、モゾモゾいいながら、すうっと、向こうに行ってしまったのです。
とたんに、そのオッサンの顔が引きつった。「はあ、そうですか」とかなんとか、モゾモゾいいながら、すうっと、向こうに行ってしまったのです。
その時、ぼくは、そのオッサンの、学校生活での暗い過去を見たような気がしたのです。彼は、おそらく「いい生徒」ではなかったでしょうし、成績がよかったはずはありません。もしかしたら、教師にいじめ抜かれたのかも知れない。そうでもなければ、あの、彼の顔面をよぎった一瞬の、怖れと嫌悪の入り混った表情の説明がつかない。そんな気がしたのです。なんだか後めたいような、いやな気分でした。
劇作家の唐十郎はこう書く。
ーー教育者として私の前に現われた人の顔は、いつも血の気が薄く見えたもんだ。
まるで昼間に現われた吸血鬼のような。それは、場を間違えて少年たちの前をうろつ
く、知性の仮面をかぶった肉体の敗残者だった。(中略)教育者が現われるところは、
教室かブックの上であり、教える側と教わる側という位置は絶対に転換しないために、
それは、暴力的な設定でさえある。バカがゴマンと教育されるのも、その位置の不動
の約束に原因があるのだろう。だから私は、教室の住人である教育者を信奉しなかっ
たことを幸福に思う——
またグラフィックデザイナーの横尾忠則はこう書きます。
——私は「教育」という言葉を間くだけで鳥ハダが立つくらい、この言葉がきらい
だ。何故かこの言葉の裏には、強制的に人間を支配しようとする政治的なサディステ
ィックな力が隠されているようで、近よるのがおそろしい感じがする。人間が人間
を、「教育」という言葉を借りて所有しようとする非人間的な行為が、どうも好きに
なれない——
♣♣♣♣
大学の専攻生の頃、NHKの「歌のおばさん」をふとんの中できいてから出掛けるのが常でした。それで、昼前に校門に向かって歩いてゆくと、よくK教授と一緒になりました。門を入って校舎のビルの手前まで来ると、彼は、
「タカダ、ちょっと先に行って、向うにコンキンさんがいないか見てくれ」
コンキンさんというのは学長のことで、K教授の厳格な恩師なのです。
角を曲った所で、ぼくが振返って、OKサインをすると、彼はスタスタと追付いてきて、「なあ君、世の中はこういう風にやるんや」と云ったものでした。
ぼくの専攻講座のノダマン先生は、毎日、夜遅くまで実験に没頭しながら、いつも、
「ワシは職人や」といっていた。
高校の時、京大を出たばかりの英語教師のナカニシさんは、授業中誰かにリーダーを読ましておいて、ぼくのそばに来ると、小声で、
「タカダ、今晩飲もか」
と、誘うのが常でした。
こうした先生方は、特に何かをぼくに教えようとしたことはなかったみたいです。どっちかというと、ぼくが勝手に学んだ、というか盗んだのだろう。ただし、彼等が何かを身をもって示してくれていたから盗めたのかも知れないという気はします。
ところで、ぼくはいま教師という仕事をやってゼニをもらっているのだけれど、「理想の教師像」は、などとたずねられると、ハタと困ってしまいます。万人が万人の教師だという立場からすれば、それは「理想的人間像」みたいなことになって、もっと困る。はっきりしていることは、教師は必ずしも、教育者ではないということ位です。
 ——ほんとうの教育者というのがもしあるとしたら、それは円満具足、完璧な″理想像″的存在ではなく、どちらかといえば圭角のある、つまりデコボコな、どこやらに不可解なところを持った、だから教育される側からすれば抵抗を感じ、従って抵抗せざるを得ないところの、しかし抵抗しているうちにいつの間にか、こちらの自発性が引き出されて来ているという、そうした存在であるのだろうと私には考えられる。そのことをいい換えれば、一人の完全無欠な先生のイメージは私の記憶の中に浮かんでこない代りに、あの変な先生、この変な先生という記憶、そういう変な先生がたの記憶の総合、あるいはそこにあった共通項というものをもとに、私にとっての″ほんとうの教育者″のイメージは形づくられる——
——ほんとうの教育者というのがもしあるとしたら、それは円満具足、完璧な″理想像″的存在ではなく、どちらかといえば圭角のある、つまりデコボコな、どこやらに不可解なところを持った、だから教育される側からすれば抵抗を感じ、従って抵抗せざるを得ないところの、しかし抵抗しているうちにいつの間にか、こちらの自発性が引き出されて来ているという、そうした存在であるのだろうと私には考えられる。そのことをいい換えれば、一人の完全無欠な先生のイメージは私の記憶の中に浮かんでこない代りに、あの変な先生、この変な先生という記憶、そういう変な先生がたの記憶の総合、あるいはそこにあった共通項というものをもとに、私にとっての″ほんとうの教育者″のイメージは形づくられる——
この、劇作家・木下順二の見解は、まあ、なんだかもっともフィットするような気がしています。
学生の時、春の穂高に登っての帰り路、松本駅にたどり着き、京都までの切符を買うと十円しか残りませんでした。夜行は出たあとで、ここのベンチでの夜明かしを決め、その十円でアンパンをひとつ買いました。両の手で、包み込むような気持で、それを喰べようとした時です。一人の男が、ジッとこっちを見ているのに気付いたのです。どうみても、それはルンペンでした。
ちょっとかじったのですが、その男はまだぼくのアンパンを見つめていました。なんだか申し訳ないような気分になって、ぼくは、パンを半分割って、彼に与えたのです。
これがきっかけで、彼はぼくに色んな話をしました。驚いたことに、彼は国立、いわゆる帝大出なのでした。哲学科だそうで、カントやヘーゲルなどがポンポンとびだしました。その人生哲学や世相批判は、社会の枠外からの視点にたってのものであるためか、なかなか面白かった。
当時の山登りの服装というのは、今に較べれば、なんともくすんだもので、帰りともなれば、服はボロボロ、髭ボウボウで、ちょっと見にはルンペンさながらでした。おまけに、帰りの金など無いことがままあり、なじみの旅館のオバチャンに借りたり、駅前の派出所に頼みこんだり、どっちかといえば乞食みたいなもんでした。
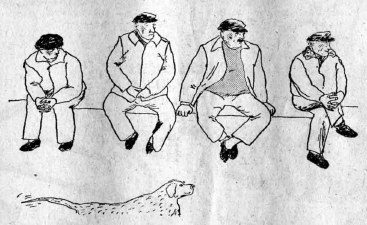 その所為か、よくルンペンに話しかけられることがあったのです。あの時、御在所岳で岩登りをしての帰りもそうでした。ぼく達は名古屋駅まで帰り着き、テレビ塔の下で寝るべく、歩いていったのです。そしたら、一人のルンペンが、「駅の方がいい、一諸にゆこう」と誘うので、また駅まで引返した訳です。
その所為か、よくルンペンに話しかけられることがあったのです。あの時、御在所岳で岩登りをしての帰りもそうでした。ぼく達は名古屋駅まで帰り着き、テレビ塔の下で寝るべく、歩いていったのです。そしたら、一人のルンペンが、「駅の方がいい、一諸にゆこう」と誘うので、また駅まで引返した訳です。この男も、なかなか面白かった。彼は、朝鮮人で、戦時中、北海道の炭坑で強制労働に従事させられていた。真冬に、そこを脱走した時の九死に一生の恐しい体験を克明に語りました。彼はこういいました。
「人間鍛錬すれば、何でも出来る。オレはいまどんなに寒い真冬でも、新聞紙一枚で、アスファルトにごろ寝できるよ」
ぼくは、ただ感心していました。
こうした経験は、ぼくに、人は外見だけでは判断できないもんだ、ということを教えたようでした。
二回目のカラコルムに行った時、スワット・ヒマラヤの山中で、羊と共に暮らす山人達からも、多くの事を学びました。なによりも、物質的に全く恵まれない彼らの、その卑屈さの全くない誇り高さに、腹立たしさを覚えながらも感服し、やがて、感化を受けたのです。
——学校よりも、あらゆるタイプの人間のそろっている実社会こそが真の意味での
もっとも有効な教育の場所といえよう。実社会での結合・敵対等の一切の人間関係を
通じて、万人は万人に対する教育者としての役割を知らないうちにはたしているので
ある(家永三郎)——
♣♣
数年前、シンナーの悪習から抜けられず、とうとう病院に入れられた生徒がいました。彼が退院してきて、ぼくの授業に出てきた日、出欠をとって初めて彼がいるのに気付き、 「オッ、出てきたんか。それでどんな具合やった」
と、声をかけたのです。
「学校とおんなじことですよ。テレビが見れるだけいいくらいや。それにしても、今の学校も教師もひどすぎる」
と、勢い込んで、彼は不平を鳴らしつづけました。彼はぼくとの問答の中で、学校や教師はどうあってほしいかという例として、何度も何べんも、テレビの「学園もの」を引きあいに出しました。クラスの全員は、シンとして、彼とぼくとのやりとりを聞いていたのです。
「そらお前、テレビの見すぎやで。あんなもん、お話にすぎんのじゃ」
と、ぼくは断言しました。でも、その時、彼は期待が大きすぎるのだ。学校や教師に多くを望みすぎるのだ。そんな気がしたのです。そして、もしかしたら、彼はそうした現実と自分の幻想とのギャップにもだえ、シンナーを吸うことによって、空想の世界に遊ぶのではなかろうか。そんなことを考えたのでした。
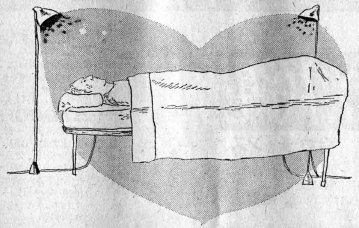 ぼく自身、自分の学校生活をふり返ってみて、彼のような発想は、全くなかった。ぼくにとって、教師とは、のっけから、多分に偽善的であらねばならぬ職業についている人に過ぎなかった。
ぼく自身、自分の学校生活をふり返ってみて、彼のような発想は、全くなかった。ぼくにとって、教師とは、のっけから、多分に偽善的であらねばならぬ職業についている人に過ぎなかった。だから、人事院総裁だった佐藤達夫氏の次のような言葉などは、とても、まともに受取れない。なんだかあっ気にとられる。
——教育基本法の第一条は、教育の目的として、「教育は人格の完成をめざし……
自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わねばならない」と定め
ている。私が学校に通ったころは、むろんこのような法律のできるずっと前のことだ
ったけれども、小・中学校時代に私の教わった先生たちは、どの一人を思いだしてみ
ても、まさに、この理想にそった教育をしてくれたといっていい。これはほんとうに
幸いだったと思っている——
ほんまかいなあと思う。ほんとにそう信じ込める人がいたらそれこそ幸せだなあという気がします。これに較べれば、ゴールドブレンドのコマーシャルの、指揮者・岩城宏之などは、まことに心安まることをいっている。
——ぼくはいろんな人が[わが尊敬する師」などと生涯かけて尊敬し、お慕いなさ
れているのを読んだりしても、どうもピンと来ないのだ。そういう偉大な真の教育者
にめぐりあった運のよい人をうらやましいとは思う。でも百パーセント尊敬され得る
人、および百パーセント人をあがめる人の両方を、ぼくは信じない。(中略)少年時
代にぼくにおとな不信の精神を植えつけてくれた教育者でもあったおとなたちに、感
謝しないでもない——
どうやら、〈良い教師はない。よい生徒があるばかりだ(山根銀二)〉ということになるらしい。
♣♣♣
ぼくはよく人から、「ほんとに学校の先生なんですか」とか、「とても先生には見えません」などといわれます。まことにケッタイな話なのですが、そういわれると、なんだかホッとしたりする。
ところが、まれに「やはりタカダさんは先生なんてすねえ。安心しました」などと、その真意をつかみかねるようなことを云われることがある。なんだか、ガックリきて、ドッと疲れるような感じなのです。
ずっと昔、まだ車が少々珍しかった頃、ぼくは、新車の定期整備に工場に行きました。一人の中年のオッサンが、親しげに話しかけて来たのです。彼も整備に来たらしい。
「どうでっか。車の調子は。ああ、そうですか。私のも調子は上々でっせ。これ買うてよかった思うてます」
彼は矢つぎ早に話し、ぼくは適当に合槌を打っていました。そのうちに彼は、
「お商売は、なにやったはりますねん」
それ来た、とぼくは思いました。ぼくの一番いやな質問です。ところが、人は直ぐにこの問いを発する。ぼくは、やや言い澱んで、
「教師です」
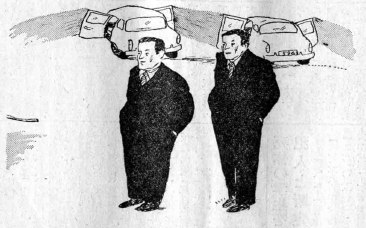 とたんに、そのオッサンの顔が引きつった。「はあ、そうですか」とかなんとか、モゾモゾいいながら、すうっと、向こうに行ってしまったのです。
とたんに、そのオッサンの顔が引きつった。「はあ、そうですか」とかなんとか、モゾモゾいいながら、すうっと、向こうに行ってしまったのです。その時、ぼくは、そのオッサンの、学校生活での暗い過去を見たような気がしたのです。彼は、おそらく「いい生徒」ではなかったでしょうし、成績がよかったはずはありません。もしかしたら、教師にいじめ抜かれたのかも知れない。そうでもなければ、あの、彼の顔面をよぎった一瞬の、怖れと嫌悪の入り混った表情の説明がつかない。そんな気がしたのです。なんだか後めたいような、いやな気分でした。
劇作家の唐十郎はこう書く。
ーー教育者として私の前に現われた人の顔は、いつも血の気が薄く見えたもんだ。
まるで昼間に現われた吸血鬼のような。それは、場を間違えて少年たちの前をうろつ
く、知性の仮面をかぶった肉体の敗残者だった。(中略)教育者が現われるところは、
教室かブックの上であり、教える側と教わる側という位置は絶対に転換しないために、
それは、暴力的な設定でさえある。バカがゴマンと教育されるのも、その位置の不動
の約束に原因があるのだろう。だから私は、教室の住人である教育者を信奉しなかっ
たことを幸福に思う——
またグラフィックデザイナーの横尾忠則はこう書きます。
——私は「教育」という言葉を間くだけで鳥ハダが立つくらい、この言葉がきらい
だ。何故かこの言葉の裏には、強制的に人間を支配しようとする政治的なサディステ
ィックな力が隠されているようで、近よるのがおそろしい感じがする。人間が人間
を、「教育」という言葉を借りて所有しようとする非人間的な行為が、どうも好きに
なれない——
♣♣♣♣
大学の専攻生の頃、NHKの「歌のおばさん」をふとんの中できいてから出掛けるのが常でした。それで、昼前に校門に向かって歩いてゆくと、よくK教授と一緒になりました。門を入って校舎のビルの手前まで来ると、彼は、
「タカダ、ちょっと先に行って、向うにコンキンさんがいないか見てくれ」
コンキンさんというのは学長のことで、K教授の厳格な恩師なのです。
角を曲った所で、ぼくが振返って、OKサインをすると、彼はスタスタと追付いてきて、「なあ君、世の中はこういう風にやるんや」と云ったものでした。
ぼくの専攻講座のノダマン先生は、毎日、夜遅くまで実験に没頭しながら、いつも、
「ワシは職人や」といっていた。
高校の時、京大を出たばかりの英語教師のナカニシさんは、授業中誰かにリーダーを読ましておいて、ぼくのそばに来ると、小声で、
「タカダ、今晩飲もか」
と、誘うのが常でした。
こうした先生方は、特に何かをぼくに教えようとしたことはなかったみたいです。どっちかというと、ぼくが勝手に学んだ、というか盗んだのだろう。ただし、彼等が何かを身をもって示してくれていたから盗めたのかも知れないという気はします。
ところで、ぼくはいま教師という仕事をやってゼニをもらっているのだけれど、「理想の教師像」は、などとたずねられると、ハタと困ってしまいます。万人が万人の教師だという立場からすれば、それは「理想的人間像」みたいなことになって、もっと困る。はっきりしていることは、教師は必ずしも、教育者ではないということ位です。
 ——ほんとうの教育者というのがもしあるとしたら、それは円満具足、完璧な″理想像″的存在ではなく、どちらかといえば圭角のある、つまりデコボコな、どこやらに不可解なところを持った、だから教育される側からすれば抵抗を感じ、従って抵抗せざるを得ないところの、しかし抵抗しているうちにいつの間にか、こちらの自発性が引き出されて来ているという、そうした存在であるのだろうと私には考えられる。そのことをいい換えれば、一人の完全無欠な先生のイメージは私の記憶の中に浮かんでこない代りに、あの変な先生、この変な先生という記憶、そういう変な先生がたの記憶の総合、あるいはそこにあった共通項というものをもとに、私にとっての″ほんとうの教育者″のイメージは形づくられる——
——ほんとうの教育者というのがもしあるとしたら、それは円満具足、完璧な″理想像″的存在ではなく、どちらかといえば圭角のある、つまりデコボコな、どこやらに不可解なところを持った、だから教育される側からすれば抵抗を感じ、従って抵抗せざるを得ないところの、しかし抵抗しているうちにいつの間にか、こちらの自発性が引き出されて来ているという、そうした存在であるのだろうと私には考えられる。そのことをいい換えれば、一人の完全無欠な先生のイメージは私の記憶の中に浮かんでこない代りに、あの変な先生、この変な先生という記憶、そういう変な先生がたの記憶の総合、あるいはそこにあった共通項というものをもとに、私にとっての″ほんとうの教育者″のイメージは形づくられる——この、劇作家・木下順二の見解は、まあ、なんだかもっともフィットするような気がしています。
21.「四ない運動」は思考の暴走かも
♣
もう十年近くも前、初めてバイクに乗り始めた頃、ぼくは面白いことに気付きました。その当時はまだ、自動販売機などまずなかった。それでバイクでタバコ屋に乗りつけ、タバコを買おうとする。すると、タバコ屋のオバチャンが、まず例外はないといっていいくらい、なんともぞんざいなロのきき方をするんです。
初めの頃は、なぜそうなのか分らず面喰らう仕末で、腹を立てていたのですが、そのうちに、原因がバイクにあるらしいことが分りました。いかにもうさん臭げな対応をされると、ぼくも少しひがんで、この人は、バイクに乗る人間に対してなんか差別意識のような偏見をもってるのではなかろうか、などと考えたものです。
あるいは、もしかして、ぼくが、えらく若僧に見られたのかも知れません。オートバイには、まさかスーツで乗る訳にもゆきませんから、それなりの服装になるし、ヘルメットなどかぶっていると、年など判別できなくなるようなのです。それにしても、年が若いからぞんざいな応待をするというのも、やっぱりあんまり程度のいい話ではありません。程度悪いオバはんや、ぼくはひそかにそう思ってうっぷん晴しをしていたものです。
考えてみれば、こうした嫌悪感を表に出した拒否反応みたいな眼差しは、もっと以前にも、たしか経験した記憶がありました。それは、まだ学生の頃、山登りにゆく途中、汽車の中などで、出会ったものでした。その頃、山の大量遭難が新聞の社会面をにぎわわし、山登りは反社会的なものとして糾弾されており、最低のスポーツなどとこきおろされていたのです。群馬県や富山県などでは、冬期の登山禁止条例まで制定する騒ぎでした。まあいってみれば、いまの暴走族みたいに捉えられていたのかも知れません。
でも、当方のぼくたちとしては、若気の至りか浅はかさか、なにいうとんねん、お前ら素人に何が分るか、てなもんでした。むしろ、そうした社会的な圧迫があり、白眼視されることで、より一層結束し、もっと山にのめり込むみたいな心情が生れていました。
この頃では、えらく状況が変ってきたようで、山の遭難があっても、昔ほど騒がれないようです。山登りでは死ぬこともある、と遭難死が当り前みたいになって、みんな慣れてきたのでしょうか。
そして、この頃では、バイクでタバコ屋へ行っても、昔みたいな応待をされることは、ほとんどない。それほど、バイクが普通のものになってきて、オバチャンの偏見がなくなってきたのか。ミニバイクが大はやりで、家庭の主婦が、道路を暴走し初めたからなのか。ほんとの話、オバチャンの中には、暴走族みたいに蛇行走行はしないにしても、飛び出し等の信号無視に等しいような全く常識を逸した暴走みたいなことをやる人も多いのです。
♣♣
 時代も時代だったのですが、ぼくが、自動車に興味をもったのは、大学を卒業して少したってからのことでした。それまでは、全くといっていいくらい関心がなかったようです。今の若者からすれば、えらいおくてということになる。
時代も時代だったのですが、ぼくが、自動車に興味をもったのは、大学を卒業して少したってからのことでした。それまでは、全くといっていいくらい関心がなかったようです。今の若者からすれば、えらいおくてということになる。
母親が四輪免許の教習に通い始め、クランクコースがどうの、幅寄せが難しいだの話しても、「ふうん」「へえ」てなものでした。ところが、ブルーバードがガレージに入った時から、急に様子が変ったようでした。
夜中、少々の興味を覚え、ドアを開け運転席に座ってみました。プンと独特のぼくがまだ知らない不思議な匂いが鼻をつき、計器類が青白く浮かんでいます。衝動的に、ぼくは、動かしてみたくなりました。オフクロは、駄目だめと、キーを渡してくれませんでした。
翌日、勤めからの帰り、ぼくは教習所にゆき、一時間の教習を申し込みました。云われた通り、ギヤを入れ、そっとクラッチをつなぐと、ずんぐりと大きい車体がスルスルと動きだしたのです。ぼくはただもう夢中で、ドキドキし、ウキウキしながら、何回も何回も周回コースを回り、ちょうど、遊園地で電気自動車に乗った子供みたいな気分でした。そして、ようし免許を取るぞ、と心に決めたのです。
その頃は新車を買うと、販売店のサービスで、教習チケットがついていました。つまり、このチケットがあれば、ある指定された教習所にゆくと、府の試験場で合格するまで、無料で練習ができるのです。
ぼくは、母親から、このチケットをもらうと、デルタ自動車教習所へ出掛けた訳です。
ぼくの担当になった教官は、「あんたを教えても、ワシー銭にもならんのや。このチケットでは……」といい、「動かせるんやったら、勝手に走り」と、何ともぶっきら捧この上なしでした。でも、ブチ当りそうになった時には、横でパッとブレーキをかけ、「殺さんといてや」などといっていました。なんでも彼の話によれば、彼は特攻隊帰りなのだそうです。そういえば、何となくニヒルな感じでした。
何回か通ううちに、ぼくはもう、かなり自在に車を操れるようになり、けっこうスイスイと走っていました。ふと気がつくと、鼾が聞こえ、見ると彼が傍で眠っているのでした。ぼくを信頼しないことには、眠れるはずがないのです。その頃すでに教師で、毎日生徒を教えていたぼくには、彼のように、自由にやらせることが、口やかましく教えることより難しいことが分りかけていたのでしょうか。その時ぼくは、一種奇妙な感動を覚えていたようです。
時には、急にむくりと起きあがり、「あの車、追いかけよや。ええ女の子がのっとる」
などと、ぼくをけしかけることもありました。
こういう次第で、ぼくは実に楽しく練習して、免許を手にしたのです。
♣♣♣
一緒に洗車している時などは、ぼくたち母子は、あたかも親しい友達か仲間のようでした。ところが、いざ、どちらが車を使うかという段になると、二人はたちまち仇敵の如くに変化するのが常でした。一応、母親の車ですから優先権は認めているものの、空いている時には使わせるという約束もありました。駄目だと云われても納得できないときがままあったのです。
車にしろ、バイクにしろ、スキーにしろ、岩攀りにしろ、そうした緊張を強いられるスポーツには、ある麻薬的魅力があるようです。ぼくはどうしても乗りたくて、どうや、これでも貸せんか、などと母親の腕をねじあげたこともあります。ちょっとした家庭内暴力だった。
勤め先に車でゆくと、フジタ先生が「その年で車に乗るのは早すぎる」とコメントしました。彼の持論によれば、車は、バイクを完全にマスターした後に乗るべきなのだそうです。彼は大のバイク好きで、毎日、京都から亀岡までバイクで通勤していました。彼がしつこく勧めるので、いやいやながら、彼のバイクのケツに乗せてもらって、京都まで帰ったこともありました。でも、いっこう、バイクに乗りたいとは思いませんでした。
桂高校に替った時、ちょうど、ここでは、生徒の四輪通学が禁止された時でした。コスゲ先生が、学校新聞に、「四輪通学禁止に思う」を書いています。
授業中にモーターバイクのメカニズムの話をした時の生徒達の生き生きした表情が極めて印象的であったこと。ダイムラー・ベンツは子供の時、与えられるすべての玩具を分解しないと納得しなかった。若い間にメカニズムに親しむことが、真の科学する心を育てる、などなどが述べてあります。お寺を巡ることが文化的であり、キカイには弱くて……などと恥づかし気もなくうそぶき、それが教養ある態度だと思っているアホな大人や教師が批判されています。
そして、この文章は、「いつか、この学校に四輪やバイクで集まり、昔は学校も禁止した時代があったなあと語り合える日が来ることを信じる」と結んでありました。
でも、コスゲ先生の予想に反し、その後、バイク通学も禁止され、さらにバイクに乗ることが禁止されました。それでも止まらないとなって、次は免許を取ることさえ禁止された訳です。
日本のあちこちで、「乗らない」「取らない」「買わせない」の〈三ない運動〉が初まります。そして、これが〈四ない運動〉になる。「同乗しない」がつけ加わった訳です。さらに〈プラス一ない運動〉(神奈川県)までゆく。プラス一は、「子供の要求に負けない」なのだそうで、そのうちに、〈十ない〉位までゆくんじゃないかな。ほんとに、世の中どうかしているという気がします。
♣♣♣♣
もう十年ほども前、ちょっとしたキッカケで、ぼくは単車に興味を持ち、W1(ダブルワン)という二〇〇kgを超えるでかい奴を買ってしまいました。それまでは、全く興味がないどころか、むしろ謙いだったのですから、自分でも不思議です。
免許に関しては、普通免許に自動二輪免許が自動的に付いていたから問題ありません。でも、運転の方は、なにしろ、生れて始めて二輪にまたがったのですから大変でした。約一ヶ月間、毎日、夜、二・三時間の、それこそ血のにじむような練習をしたものです。そうはいっても、そんなつらいものではなく、ただもう面白くて夢中になって乗っていた、といった方が当っているかも知れませんが……。それで完全に乗りこなせるようになったかというと、そうではなく、やはり、今から考えれば、二・三年かかってようやく、なんとか乗れるという程度になったのではないかと思うんです。
やはりバイクというのは、四輪に較べると、比較にならない位難しいものです。四輪はこけるということがないけれど、二輪は止ったら倒れるんですから……。それに身体を露出しているから、危険この上ない乗り物です。
しかし同時に、どうしようもなく魅力的で、すてきで、なにか人をとりこにする乗り物であることも事実です。ただどこがそんなにいいのかを問われて、納得ゆく説明をすることは、山登りの魅力を説明することより、もっと難しいような気がしています。
ごく最近、急に最新型がほしくなって、ぼくは二台目の二輪を買いました。いわゆるナナハンです。学校に乗ってゆくと、まだ発売間もなく、ほとんど走っていないこともあってか、生徒が群がって触っています。
触るといっても、レバーを握ったりアクセルを回したりといった感じのものではない。全身をすりつけるというか、脇にはさみこむというか……、その仕草は、見ていて、なんか異様な感じを受けました。
ぼくが、大学で山登りを始め、冬山に行こうとした時、母親は猛反対し、道具を買うお金をくれないどころか、山靴をどこかに隠してしまいました。ぼくは、だから、肉屋のデッチのアルバイトをして靴を買ったものです。
何年かたつと、もうオフクロもあきらめ、「誰にほめてもらう訳でもないのに、よくつらい目に会いに山にゆくねえ」などとひやかしをいったりしだしていた頃のことです。ある時、ぼくは予定より数日早く下山し、夜中に帰宅したのです。遅れることはあっても、予定より早く帰るなどということはまずなかった。それで、家に入り、よく眠っている母親を起こそうかどうしようかと、枕元に立って思案していたのです。そのとき突然、オフクロがむくりと起き上り、フトソの上にペタリと座ると、両手で顔をおおって、激しく泣き出したのです。ぼくは、びっくりして突っ立ったままでした。彼女は、てっきり、ぼくが夢枕に立ったと思ったのだそうです。この時始めて母親が息子の身の上をどれほど案じているかを、ぼくは身を刺すように理解できたのです。
しかし、それで山登りを止めようなどとは、全く考えませんでした。
♣♣♣♣♣
危険なことをやりながら成長するのが若者です。本人が承知でやろうとしていることを、危険だから止めなさいといくらいっても、それは通じない。いくら止めても、やり技こうとするのが若者です。
親のいうことをなんでもハイハイときくような奴の方がむしろ問題です。大人のいうことを素直にきく若者ばかりだったら、世の中に進歩はない。
バイクに乗らないよう子供を説得できなくて、学校に泣きつく。時には、お金を出してやっておきながら、学校で禁止してくれなどという。そういう態度に、自分は結構喜こんで読んでいるくせに、悪書追放運動に賛成する、どうしようもなく主体性のない大人の姿が重なってしまいます。
学校は学校で、そんな学校外のこと、本人の責任で、本人次第でしょうと突っぱねればいいものを、そういうことは云えない世の中、禁止を打ちだす。ところが違反者続出、手を焼いて免許を取りあげたら、生徒は、紛失したと偽りの申告をして再交付を受ける。そこで教師はサツ回りして、再交付の申請をしているかどうかを定期的に調べるなんてことになった。そしてとうとう、親と教師と警察が一つになって、〈三ない運動〉から〈四ない運動〉の大合唱とあいなった。生徒のかなり多くが、これを汚ないやり方と見ています。
こうした運動は、全くアホみたいに単純明快で、バイクは受験勉強の敵、非行の始まりと決めつけているかのようです。
「この子からバイクを取ったら何にも残りません。どうかバイクを禁止しないでやってほしい」と真剣に教師に頼む母親のいることなど、全く思案の外なのでしょう。
そこに結果されるものは、勝手な親の思い入れに反した断絶と不信感だけである。ぼくには、どうもそう思える。バイクに乗る若者の中のほんの一握りの暴走族のガキどもにふり回されて、大人の思考まで暴走を始めたとしか思えないのです。
とにかく手段を選ばず止めさせる、なんてことが教育的である訳がない。むしろ、前向きに現実をとらえ、それらを教育の素材とすべきではないだろうか。交通安全教育ととり組むことは、自動車・バイクメーカーのお先棒をかつぐことだ、などと考える教師がいたとしたら、それは全くどうしようもない時代錯誤としかいいようがありません。
いま、この夜更け、はるかな街道から、激しい排気音が聞えてきます。やりばのないエネルギーの一瞬の燃焼を賭けて、若者は生死の境界線を疾走しているのでしょう。全くアホなガキどもという気もします。しかし、同時に確信をもっていえることは、彼等は決してビルから飛びおりたり、自閉症になったりはしないし、金属バットをふりおろすこともないだろう、ということです。
もう十年近くも前、初めてバイクに乗り始めた頃、ぼくは面白いことに気付きました。その当時はまだ、自動販売機などまずなかった。それでバイクでタバコ屋に乗りつけ、タバコを買おうとする。すると、タバコ屋のオバチャンが、まず例外はないといっていいくらい、なんともぞんざいなロのきき方をするんです。
初めの頃は、なぜそうなのか分らず面喰らう仕末で、腹を立てていたのですが、そのうちに、原因がバイクにあるらしいことが分りました。いかにもうさん臭げな対応をされると、ぼくも少しひがんで、この人は、バイクに乗る人間に対してなんか差別意識のような偏見をもってるのではなかろうか、などと考えたものです。
あるいは、もしかして、ぼくが、えらく若僧に見られたのかも知れません。オートバイには、まさかスーツで乗る訳にもゆきませんから、それなりの服装になるし、ヘルメットなどかぶっていると、年など判別できなくなるようなのです。それにしても、年が若いからぞんざいな応待をするというのも、やっぱりあんまり程度のいい話ではありません。程度悪いオバはんや、ぼくはひそかにそう思ってうっぷん晴しをしていたものです。
考えてみれば、こうした嫌悪感を表に出した拒否反応みたいな眼差しは、もっと以前にも、たしか経験した記憶がありました。それは、まだ学生の頃、山登りにゆく途中、汽車の中などで、出会ったものでした。その頃、山の大量遭難が新聞の社会面をにぎわわし、山登りは反社会的なものとして糾弾されており、最低のスポーツなどとこきおろされていたのです。群馬県や富山県などでは、冬期の登山禁止条例まで制定する騒ぎでした。まあいってみれば、いまの暴走族みたいに捉えられていたのかも知れません。
でも、当方のぼくたちとしては、若気の至りか浅はかさか、なにいうとんねん、お前ら素人に何が分るか、てなもんでした。むしろ、そうした社会的な圧迫があり、白眼視されることで、より一層結束し、もっと山にのめり込むみたいな心情が生れていました。
この頃では、えらく状況が変ってきたようで、山の遭難があっても、昔ほど騒がれないようです。山登りでは死ぬこともある、と遭難死が当り前みたいになって、みんな慣れてきたのでしょうか。
そして、この頃では、バイクでタバコ屋へ行っても、昔みたいな応待をされることは、ほとんどない。それほど、バイクが普通のものになってきて、オバチャンの偏見がなくなってきたのか。ミニバイクが大はやりで、家庭の主婦が、道路を暴走し初めたからなのか。ほんとの話、オバチャンの中には、暴走族みたいに蛇行走行はしないにしても、飛び出し等の信号無視に等しいような全く常識を逸した暴走みたいなことをやる人も多いのです。
♣♣
 時代も時代だったのですが、ぼくが、自動車に興味をもったのは、大学を卒業して少したってからのことでした。それまでは、全くといっていいくらい関心がなかったようです。今の若者からすれば、えらいおくてということになる。
時代も時代だったのですが、ぼくが、自動車に興味をもったのは、大学を卒業して少したってからのことでした。それまでは、全くといっていいくらい関心がなかったようです。今の若者からすれば、えらいおくてということになる。母親が四輪免許の教習に通い始め、クランクコースがどうの、幅寄せが難しいだの話しても、「ふうん」「へえ」てなものでした。ところが、ブルーバードがガレージに入った時から、急に様子が変ったようでした。
夜中、少々の興味を覚え、ドアを開け運転席に座ってみました。プンと独特のぼくがまだ知らない不思議な匂いが鼻をつき、計器類が青白く浮かんでいます。衝動的に、ぼくは、動かしてみたくなりました。オフクロは、駄目だめと、キーを渡してくれませんでした。
翌日、勤めからの帰り、ぼくは教習所にゆき、一時間の教習を申し込みました。云われた通り、ギヤを入れ、そっとクラッチをつなぐと、ずんぐりと大きい車体がスルスルと動きだしたのです。ぼくはただもう夢中で、ドキドキし、ウキウキしながら、何回も何回も周回コースを回り、ちょうど、遊園地で電気自動車に乗った子供みたいな気分でした。そして、ようし免許を取るぞ、と心に決めたのです。
その頃は新車を買うと、販売店のサービスで、教習チケットがついていました。つまり、このチケットがあれば、ある指定された教習所にゆくと、府の試験場で合格するまで、無料で練習ができるのです。
ぼくは、母親から、このチケットをもらうと、デルタ自動車教習所へ出掛けた訳です。
ぼくの担当になった教官は、「あんたを教えても、ワシー銭にもならんのや。このチケットでは……」といい、「動かせるんやったら、勝手に走り」と、何ともぶっきら捧この上なしでした。でも、ブチ当りそうになった時には、横でパッとブレーキをかけ、「殺さんといてや」などといっていました。なんでも彼の話によれば、彼は特攻隊帰りなのだそうです。そういえば、何となくニヒルな感じでした。
何回か通ううちに、ぼくはもう、かなり自在に車を操れるようになり、けっこうスイスイと走っていました。ふと気がつくと、鼾が聞こえ、見ると彼が傍で眠っているのでした。ぼくを信頼しないことには、眠れるはずがないのです。その頃すでに教師で、毎日生徒を教えていたぼくには、彼のように、自由にやらせることが、口やかましく教えることより難しいことが分りかけていたのでしょうか。その時ぼくは、一種奇妙な感動を覚えていたようです。
時には、急にむくりと起きあがり、「あの車、追いかけよや。ええ女の子がのっとる」
などと、ぼくをけしかけることもありました。
こういう次第で、ぼくは実に楽しく練習して、免許を手にしたのです。
♣♣♣
一緒に洗車している時などは、ぼくたち母子は、あたかも親しい友達か仲間のようでした。ところが、いざ、どちらが車を使うかという段になると、二人はたちまち仇敵の如くに変化するのが常でした。一応、母親の車ですから優先権は認めているものの、空いている時には使わせるという約束もありました。駄目だと云われても納得できないときがままあったのです。
車にしろ、バイクにしろ、スキーにしろ、岩攀りにしろ、そうした緊張を強いられるスポーツには、ある麻薬的魅力があるようです。ぼくはどうしても乗りたくて、どうや、これでも貸せんか、などと母親の腕をねじあげたこともあります。ちょっとした家庭内暴力だった。
勤め先に車でゆくと、フジタ先生が「その年で車に乗るのは早すぎる」とコメントしました。彼の持論によれば、車は、バイクを完全にマスターした後に乗るべきなのだそうです。彼は大のバイク好きで、毎日、京都から亀岡までバイクで通勤していました。彼がしつこく勧めるので、いやいやながら、彼のバイクのケツに乗せてもらって、京都まで帰ったこともありました。でも、いっこう、バイクに乗りたいとは思いませんでした。
桂高校に替った時、ちょうど、ここでは、生徒の四輪通学が禁止された時でした。コスゲ先生が、学校新聞に、「四輪通学禁止に思う」を書いています。
授業中にモーターバイクのメカニズムの話をした時の生徒達の生き生きした表情が極めて印象的であったこと。ダイムラー・ベンツは子供の時、与えられるすべての玩具を分解しないと納得しなかった。若い間にメカニズムに親しむことが、真の科学する心を育てる、などなどが述べてあります。お寺を巡ることが文化的であり、キカイには弱くて……などと恥づかし気もなくうそぶき、それが教養ある態度だと思っているアホな大人や教師が批判されています。
そして、この文章は、「いつか、この学校に四輪やバイクで集まり、昔は学校も禁止した時代があったなあと語り合える日が来ることを信じる」と結んでありました。
でも、コスゲ先生の予想に反し、その後、バイク通学も禁止され、さらにバイクに乗ることが禁止されました。それでも止まらないとなって、次は免許を取ることさえ禁止された訳です。
日本のあちこちで、「乗らない」「取らない」「買わせない」の〈三ない運動〉が初まります。そして、これが〈四ない運動〉になる。「同乗しない」がつけ加わった訳です。さらに〈プラス一ない運動〉(神奈川県)までゆく。プラス一は、「子供の要求に負けない」なのだそうで、そのうちに、〈十ない〉位までゆくんじゃないかな。ほんとに、世の中どうかしているという気がします。
♣♣♣♣
もう十年ほども前、ちょっとしたキッカケで、ぼくは単車に興味を持ち、W1(ダブルワン)という二〇〇kgを超えるでかい奴を買ってしまいました。それまでは、全く興味がないどころか、むしろ謙いだったのですから、自分でも不思議です。
免許に関しては、普通免許に自動二輪免許が自動的に付いていたから問題ありません。でも、運転の方は、なにしろ、生れて始めて二輪にまたがったのですから大変でした。約一ヶ月間、毎日、夜、二・三時間の、それこそ血のにじむような練習をしたものです。そうはいっても、そんなつらいものではなく、ただもう面白くて夢中になって乗っていた、といった方が当っているかも知れませんが……。それで完全に乗りこなせるようになったかというと、そうではなく、やはり、今から考えれば、二・三年かかってようやく、なんとか乗れるという程度になったのではないかと思うんです。
やはりバイクというのは、四輪に較べると、比較にならない位難しいものです。四輪はこけるということがないけれど、二輪は止ったら倒れるんですから……。それに身体を露出しているから、危険この上ない乗り物です。
しかし同時に、どうしようもなく魅力的で、すてきで、なにか人をとりこにする乗り物であることも事実です。ただどこがそんなにいいのかを問われて、納得ゆく説明をすることは、山登りの魅力を説明することより、もっと難しいような気がしています。
ごく最近、急に最新型がほしくなって、ぼくは二台目の二輪を買いました。いわゆるナナハンです。学校に乗ってゆくと、まだ発売間もなく、ほとんど走っていないこともあってか、生徒が群がって触っています。
触るといっても、レバーを握ったりアクセルを回したりといった感じのものではない。全身をすりつけるというか、脇にはさみこむというか……、その仕草は、見ていて、なんか異様な感じを受けました。
ぼくが、大学で山登りを始め、冬山に行こうとした時、母親は猛反対し、道具を買うお金をくれないどころか、山靴をどこかに隠してしまいました。ぼくは、だから、肉屋のデッチのアルバイトをして靴を買ったものです。
何年かたつと、もうオフクロもあきらめ、「誰にほめてもらう訳でもないのに、よくつらい目に会いに山にゆくねえ」などとひやかしをいったりしだしていた頃のことです。ある時、ぼくは予定より数日早く下山し、夜中に帰宅したのです。遅れることはあっても、予定より早く帰るなどということはまずなかった。それで、家に入り、よく眠っている母親を起こそうかどうしようかと、枕元に立って思案していたのです。そのとき突然、オフクロがむくりと起き上り、フトソの上にペタリと座ると、両手で顔をおおって、激しく泣き出したのです。ぼくは、びっくりして突っ立ったままでした。彼女は、てっきり、ぼくが夢枕に立ったと思ったのだそうです。この時始めて母親が息子の身の上をどれほど案じているかを、ぼくは身を刺すように理解できたのです。
しかし、それで山登りを止めようなどとは、全く考えませんでした。
♣♣♣♣♣
危険なことをやりながら成長するのが若者です。本人が承知でやろうとしていることを、危険だから止めなさいといくらいっても、それは通じない。いくら止めても、やり技こうとするのが若者です。
親のいうことをなんでもハイハイときくような奴の方がむしろ問題です。大人のいうことを素直にきく若者ばかりだったら、世の中に進歩はない。
バイクに乗らないよう子供を説得できなくて、学校に泣きつく。時には、お金を出してやっておきながら、学校で禁止してくれなどという。そういう態度に、自分は結構喜こんで読んでいるくせに、悪書追放運動に賛成する、どうしようもなく主体性のない大人の姿が重なってしまいます。
学校は学校で、そんな学校外のこと、本人の責任で、本人次第でしょうと突っぱねればいいものを、そういうことは云えない世の中、禁止を打ちだす。ところが違反者続出、手を焼いて免許を取りあげたら、生徒は、紛失したと偽りの申告をして再交付を受ける。そこで教師はサツ回りして、再交付の申請をしているかどうかを定期的に調べるなんてことになった。そしてとうとう、親と教師と警察が一つになって、〈三ない運動〉から〈四ない運動〉の大合唱とあいなった。生徒のかなり多くが、これを汚ないやり方と見ています。
こうした運動は、全くアホみたいに単純明快で、バイクは受験勉強の敵、非行の始まりと決めつけているかのようです。
「この子からバイクを取ったら何にも残りません。どうかバイクを禁止しないでやってほしい」と真剣に教師に頼む母親のいることなど、全く思案の外なのでしょう。
そこに結果されるものは、勝手な親の思い入れに反した断絶と不信感だけである。ぼくには、どうもそう思える。バイクに乗る若者の中のほんの一握りの暴走族のガキどもにふり回されて、大人の思考まで暴走を始めたとしか思えないのです。
とにかく手段を選ばず止めさせる、なんてことが教育的である訳がない。むしろ、前向きに現実をとらえ、それらを教育の素材とすべきではないだろうか。交通安全教育ととり組むことは、自動車・バイクメーカーのお先棒をかつぐことだ、などと考える教師がいたとしたら、それは全くどうしようもない時代錯誤としかいいようがありません。
いま、この夜更け、はるかな街道から、激しい排気音が聞えてきます。やりばのないエネルギーの一瞬の燃焼を賭けて、若者は生死の境界線を疾走しているのでしょう。全くアホなガキどもという気もします。しかし、同時に確信をもっていえることは、彼等は決してビルから飛びおりたり、自閉症になったりはしないし、金属バットをふりおろすこともないだろう、ということです。
- HOME Archives: August 2007