6.何事であれ現場主義がかんじん
♣
大学の五年生の時、ぼくは、教育実習で、桂高校にいったのです。
少しエラの張った顔で、背のあんまり高くない人の常として、ピンと背筋をのばした先生が、キビキビした、いかにもスポーツマンらしい動きで、ぼくの前に現われました。
指導教官のコスゲ先生でした。ぼくが、
「始めまして。西も東も分りませんが、どうかよろしく」
と、あいさつした時、彼の顔にチラと不快な表情が走ったような気がして、ぼくはしまったと思いました。きっと、彼は、こうした世慣れた云い方がきらいなのかも知れないし、もしかしたら、構えた切口上に聞えたのかも知れない。そう思ったからです。
大学のオリエンテーションで、いやに大袈裟な説明を聞かされ、先輩からも、変な教官にあたると大変だとおどされ、正直いって、ぼくは少々ビビっていたのかも知れません。
ところが、桂高校の化学の準備室は、ぼくの大学の研究室とおんなじ様に木造の老朽で、床がギシギシゆうところまでそっくり。おまけに彼はスキーが趣味だそうで、けっこう話が合いそうでした。そして、ぼくが、山岳部員だと知ると、「それはいい。授業で山の話聞かせてやって下さい」などといったのです。ぼくはホッとしました。
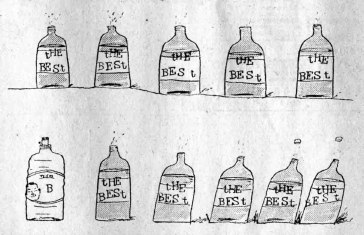 「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。
「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。
二週間の教育実習は、夏休み前の一週間と夏休み後の一週間に分かれていました。だから、前半では、夏山合宿を前にひかえて、ぼくの関心は、ほとんどそっちの方に行ってしまっていたようです。後半では、山ぼけで、ボケーッとしているうちに終ってしまい、特にこれといった印象はありません。
最初の時間、コスゲ先生の模範授業を見学しました。さすがにプロだけのことはあるという感じでした。実にスムーズで、ポイントをおさえていて、明快そのものでした。ただ彼が、何度も、「調べてみると…・‥」と前おきして、法則・結論へ導びくための前提をスパッと云うのが、気になりました。だって、その前提をどう調べるかが大問題で、その方法論を見つけるだけで何年も何十年もかかっているのが科学の歴史なんですから‥‥‥。
でも、もしそんなことを詳しく説明していたら、それだけで、一年間の授業のほとんどが済んでしまうでしょう。ぼくも、いま化学の教師で、彼とおんなじように「調べてみると‥‥‥」 とやっています。
何人かの理科の実習生を代表して公開研究授業をやることになって、ぼくは「調べてみると・‥‥」のない授業をやってやろうと思いました。大勢の教師や、実習生を前にして、ぼくは、ベンゼンのビンを片手に、教科書には全く説明のない「ベンゼンの構造式決定のいきさつ」について、丸まる一時間の授業をやったのでした。
生物の実習生の一人が、「オレの先生、お前の研究授業ばっかりほめよる」とぼやいていましたから、ぼくの研究授業はけっこう評判よかったらしいのです。
♣♣
コスゲ先生は、毎時間、丸椅子をぶら下げて、ぼくと一緒に教室にゆき、後に座って、ぼくの授業を聞いていました。彼は、内容や授業のやり方について後でほとんどコメントしませんでした。気にしたぼくがきいてみても、「あれでいいです」 というだけでした。
ぼくは、自分が本職の教師になり、実習生を受け持つようになって始めて、彼の立派さが分ったように思いました。だいたい、自信のないくだらん教師ほど、やれ声が小さいだとか、まだ黒板の方を向きすぎてますだとか、そんな本質ではない些細なことを口やかましくいう。
さて、「やってやりなさいよ」といわれて、ぼくはよく、授業で山の話をしたものです。
死にそうになった話や、死んだ友人を薪で焼いた話など、生徒は真剣に聴いていました。でも、一番熱心に、一番喜こんで、ぼくの話を聞いていたのは、コスゲ先生ではなかったかと思います。ぼくも気をつけて、クラスが違ってもおんなじ話は二度としないようにしました。
授業が終って、並んで廊下を歩いていると、突然、ぼくに注意を促がし、
「ほれ、あのこ、美人やろ」
といったりしたものです。
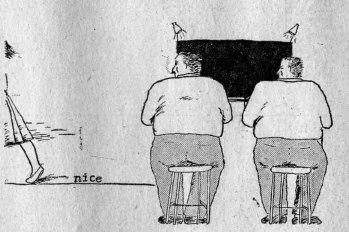 その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。
その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。
無邪気で、可愛いい、全然奥様らしくない奥さんが一緒にいました。化学の助手さんからきいて、彼が熱烈な恋愛の末に結婚したということを、ぼくは知っていました。でも、一向そういう感じでもないなと、ぼくが思っていると、奥さんが、
「この人、可愛いい女生徒には、すごく高いプレゼントしたりするんよ。けど、私には何にもくれないの」
と、ぼくに不平を告げ、コスゲ先生は、
「当り前や、釣った魚に餌やるバカがおるか」
と一笑に付しました。
たしか、二・三回目に行った時だったと思います。大学の文化祭の直ぐ後のことでした。
その頃、ぼくは、短大の女の子に熱をあげていました。もう二年越しだとはいっても、ようやく名前と住所が分った時だったんです。文化祭のフォーク・ダンスでようやく名前だけをきき出し、住所は学生課のオケイちゃんに頼んで調べてもらったのです。
コスゲさんに、この話をすると、
「そこやったら近いで。一緒に見にいこ」
そういうが早いか、ぼくをスクーターに乗せて走り出しました。もう夜でした。その商店みたいな家の前の電柱の蔭から家の中をのぞきながら、コスゲさんは、
「その娘出てきよらんなあ。あれオヤジやろ。こわそうやなあ」
などといっていました。
♣♣♣
福知山から亀岡に勤めが変り、一年ほどした頃から、ぼくはYMCAで英会話の勉強を始めたんです。
海外の山登りは、海外渡航がままならぬ当時としては、ぼくにとって、まだ夢みたいな話ではありました。しかし、どんなことであれ、夢を夢として、夢みているだけでは、それは、所詮夢でしかない。けれど、その夢を実現する為に必要なことを、何でもいいから実行動としてやってさえおれば、その時、それは、単なる夢ではなくなるはずだ。ぼくはそう信じていたのです。
だから、就職してからも、マウンテン・ワールドや、アルパインジャーナルといった年刊の洋書を取寄せて研究していたし、英会話や英文タイプも独習してはおりました。
亀中では、空き時間に、英語の先生の許しを得て借りた、えらく旧式の英文タイプをガチャガチャ、バタバタ叩いていたら、教頭先生が、
「そんなもん練習しとってやんか。えらいなあ」
と、本音とも批難ともつかぬようなことをいったものでした。
英文タイプは、二カ月もせぬうちに、なんとか打てるようになりました。勢いにのって、ついでに邦文タイプもやってやろう、とぼくは、事務室に通ったのですが、こっちの方はえらく困難で、数日もしないうちに諦めてしまったのです。
 一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。
一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。
今にして思えば、やっぱりあれは、畳の上の水練だったということです。数年後に、ぼくは、夢が実現した形で、カラコルムに行くのですが、パキスタンでの一日は、日本での練習の何ケ月にも相当すると思いました。
パキスタン人の多くが、ぼく達が、中・高・大学と十年間も英語を学んでいると聞いて、冗談をいっていると思ったようです。その時にぼくは感じたのですが、ぼく達は、英語ではなくて、英語学を学んだのだということでした。それは、丁度、いくら栄養学を勉強しても料理が作れないのとおんなじなんではないか。そしてさらにいえば、いくらお料理教室の秀才でも、山でめしがうまく作れるとは限らない。ところが、逆に、山でめしを作った経験があれば、街でも、どんな時でも、なんとか喰う物を作るのはたやすい話なんです。
やっぱり、何事であれ、現場主義、実地体験が必須なんではなかろうか、と思うのです。
♣♣♣♣
YMCAに通いだして、数ケ月たった頃だったと思います。その外人会話のクラスは、ぼくの危惧に反して、あんまりうまい奴がいなくて、ぼくは上手な方の数人に入っていました。人間そうなると調子づくもんで、さぼりのぼくとしては、異例に真面目に出席していたようです。
そんなある日、授業が終って、建物の外に出た所で、ぼくは、一人の女の子に再会したのです。もう、一年も会っていなかった。A子さんは、やはりここに通っていて、初級コースに入っているのだそうです。
「むづかして困ってんの、教えて」
懐かしさもあって、ぼくは、彼女と「再会」という名のキッサ店に行きました。いや別にカッコつけた訳ではなく、何となく入ったんです。
中級コースの優等生として、大いにのっていたぼくは、でかい面して、口うつしの発音練習をやりました。うす暗い、そのキッサ店の中で、真剣な表情で、たどたどしく、口をゆがめて後を追う彼女の唇が、奇妙にコケティッシュに映り、ぼくは、キスしたい衝動にかられたのでした。でも、以前とおんなじように、ぼくは真面目な態度で、一緒に帰りの電車に乗りました。
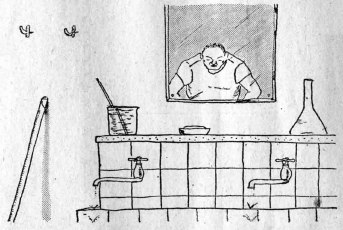 学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。
学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。
昼頃、大学へ行くと、研究室を回って、「すまん、モクくれや」とタバコを集めます。十数本集めた所で、自分の部屋へ帰り、タバコを吸って、やってくる山岳部の後輩とだべっていると直ぐ夕方になってしまいます。その頃になると、いつも決って連れのダンボーが現われ、「よお、タカダ、どや、センターいこか」。センターというのは、ぼくたちの符牒で四条河原町あたりの事でした。
市電で行き着くと、もうその辺りは、通勤帰りのサラリーマンでラッシュでした。
「お前、金あるんやろ」
「ないぞ、お前ある思てた」
「アホか、出よかいうて誘うからあると思うやんケ」
でも、ダンボーは、少しもあわてず、「なんとかなる」と、そのまま、人の流れの中に立っているのです。ものの二〇分としないうちに、彼の知り合いが通りかかり、彼は、二人分のコーヒ代を貸りてしまいます。膳所高のラグビー部のエースだった彼には、沢山の友人がいるんだそうでした。
そこで、ぼく達は、いつものキッサ店にゆき、閉店近くまでねばります。それからまた大学にとって帰り、もう誰もいない、深夜の大学の冷たく光るガラス器具にとりまかれ、水道の滴の音だけが、チョポン、チョポンと異様に響く、少し不気味な感じの実験室で、一人実験を始めるのでした。
さて、あのキッサ店に、ウエイトレスとして、A子さんが現われたのは、もう卒論をまとめ始めていた頃だったと思います。
大学の五年生の時、ぼくは、教育実習で、桂高校にいったのです。
少しエラの張った顔で、背のあんまり高くない人の常として、ピンと背筋をのばした先生が、キビキビした、いかにもスポーツマンらしい動きで、ぼくの前に現われました。
指導教官のコスゲ先生でした。ぼくが、
「始めまして。西も東も分りませんが、どうかよろしく」
と、あいさつした時、彼の顔にチラと不快な表情が走ったような気がして、ぼくはしまったと思いました。きっと、彼は、こうした世慣れた云い方がきらいなのかも知れないし、もしかしたら、構えた切口上に聞えたのかも知れない。そう思ったからです。
大学のオリエンテーションで、いやに大袈裟な説明を聞かされ、先輩からも、変な教官にあたると大変だとおどされ、正直いって、ぼくは少々ビビっていたのかも知れません。
ところが、桂高校の化学の準備室は、ぼくの大学の研究室とおんなじ様に木造の老朽で、床がギシギシゆうところまでそっくり。おまけに彼はスキーが趣味だそうで、けっこう話が合いそうでした。そして、ぼくが、山岳部員だと知ると、「それはいい。授業で山の話聞かせてやって下さい」などといったのです。ぼくはホッとしました。
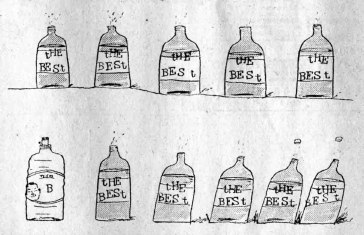 「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。
「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。二週間の教育実習は、夏休み前の一週間と夏休み後の一週間に分かれていました。だから、前半では、夏山合宿を前にひかえて、ぼくの関心は、ほとんどそっちの方に行ってしまっていたようです。後半では、山ぼけで、ボケーッとしているうちに終ってしまい、特にこれといった印象はありません。
最初の時間、コスゲ先生の模範授業を見学しました。さすがにプロだけのことはあるという感じでした。実にスムーズで、ポイントをおさえていて、明快そのものでした。ただ彼が、何度も、「調べてみると…・‥」と前おきして、法則・結論へ導びくための前提をスパッと云うのが、気になりました。だって、その前提をどう調べるかが大問題で、その方法論を見つけるだけで何年も何十年もかかっているのが科学の歴史なんですから‥‥‥。
でも、もしそんなことを詳しく説明していたら、それだけで、一年間の授業のほとんどが済んでしまうでしょう。ぼくも、いま化学の教師で、彼とおんなじように「調べてみると‥‥‥」 とやっています。
何人かの理科の実習生を代表して公開研究授業をやることになって、ぼくは「調べてみると・‥‥」のない授業をやってやろうと思いました。大勢の教師や、実習生を前にして、ぼくは、ベンゼンのビンを片手に、教科書には全く説明のない「ベンゼンの構造式決定のいきさつ」について、丸まる一時間の授業をやったのでした。
生物の実習生の一人が、「オレの先生、お前の研究授業ばっかりほめよる」とぼやいていましたから、ぼくの研究授業はけっこう評判よかったらしいのです。
♣♣
コスゲ先生は、毎時間、丸椅子をぶら下げて、ぼくと一緒に教室にゆき、後に座って、ぼくの授業を聞いていました。彼は、内容や授業のやり方について後でほとんどコメントしませんでした。気にしたぼくがきいてみても、「あれでいいです」 というだけでした。
ぼくは、自分が本職の教師になり、実習生を受け持つようになって始めて、彼の立派さが分ったように思いました。だいたい、自信のないくだらん教師ほど、やれ声が小さいだとか、まだ黒板の方を向きすぎてますだとか、そんな本質ではない些細なことを口やかましくいう。
さて、「やってやりなさいよ」といわれて、ぼくはよく、授業で山の話をしたものです。
死にそうになった話や、死んだ友人を薪で焼いた話など、生徒は真剣に聴いていました。でも、一番熱心に、一番喜こんで、ぼくの話を聞いていたのは、コスゲ先生ではなかったかと思います。ぼくも気をつけて、クラスが違ってもおんなじ話は二度としないようにしました。
授業が終って、並んで廊下を歩いていると、突然、ぼくに注意を促がし、
「ほれ、あのこ、美人やろ」
といったりしたものです。
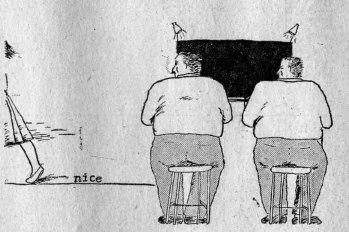 その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。
その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。無邪気で、可愛いい、全然奥様らしくない奥さんが一緒にいました。化学の助手さんからきいて、彼が熱烈な恋愛の末に結婚したということを、ぼくは知っていました。でも、一向そういう感じでもないなと、ぼくが思っていると、奥さんが、
「この人、可愛いい女生徒には、すごく高いプレゼントしたりするんよ。けど、私には何にもくれないの」
と、ぼくに不平を告げ、コスゲ先生は、
「当り前や、釣った魚に餌やるバカがおるか」
と一笑に付しました。
たしか、二・三回目に行った時だったと思います。大学の文化祭の直ぐ後のことでした。
その頃、ぼくは、短大の女の子に熱をあげていました。もう二年越しだとはいっても、ようやく名前と住所が分った時だったんです。文化祭のフォーク・ダンスでようやく名前だけをきき出し、住所は学生課のオケイちゃんに頼んで調べてもらったのです。
コスゲさんに、この話をすると、
「そこやったら近いで。一緒に見にいこ」
そういうが早いか、ぼくをスクーターに乗せて走り出しました。もう夜でした。その商店みたいな家の前の電柱の蔭から家の中をのぞきながら、コスゲさんは、
「その娘出てきよらんなあ。あれオヤジやろ。こわそうやなあ」
などといっていました。
♣♣♣
福知山から亀岡に勤めが変り、一年ほどした頃から、ぼくはYMCAで英会話の勉強を始めたんです。
海外の山登りは、海外渡航がままならぬ当時としては、ぼくにとって、まだ夢みたいな話ではありました。しかし、どんなことであれ、夢を夢として、夢みているだけでは、それは、所詮夢でしかない。けれど、その夢を実現する為に必要なことを、何でもいいから実行動としてやってさえおれば、その時、それは、単なる夢ではなくなるはずだ。ぼくはそう信じていたのです。
だから、就職してからも、マウンテン・ワールドや、アルパインジャーナルといった年刊の洋書を取寄せて研究していたし、英会話や英文タイプも独習してはおりました。
亀中では、空き時間に、英語の先生の許しを得て借りた、えらく旧式の英文タイプをガチャガチャ、バタバタ叩いていたら、教頭先生が、
「そんなもん練習しとってやんか。えらいなあ」
と、本音とも批難ともつかぬようなことをいったものでした。
英文タイプは、二カ月もせぬうちに、なんとか打てるようになりました。勢いにのって、ついでに邦文タイプもやってやろう、とぼくは、事務室に通ったのですが、こっちの方はえらく困難で、数日もしないうちに諦めてしまったのです。
 一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。
一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。今にして思えば、やっぱりあれは、畳の上の水練だったということです。数年後に、ぼくは、夢が実現した形で、カラコルムに行くのですが、パキスタンでの一日は、日本での練習の何ケ月にも相当すると思いました。
パキスタン人の多くが、ぼく達が、中・高・大学と十年間も英語を学んでいると聞いて、冗談をいっていると思ったようです。その時にぼくは感じたのですが、ぼく達は、英語ではなくて、英語学を学んだのだということでした。それは、丁度、いくら栄養学を勉強しても料理が作れないのとおんなじなんではないか。そしてさらにいえば、いくらお料理教室の秀才でも、山でめしがうまく作れるとは限らない。ところが、逆に、山でめしを作った経験があれば、街でも、どんな時でも、なんとか喰う物を作るのはたやすい話なんです。
やっぱり、何事であれ、現場主義、実地体験が必須なんではなかろうか、と思うのです。
♣♣♣♣
YMCAに通いだして、数ケ月たった頃だったと思います。その外人会話のクラスは、ぼくの危惧に反して、あんまりうまい奴がいなくて、ぼくは上手な方の数人に入っていました。人間そうなると調子づくもんで、さぼりのぼくとしては、異例に真面目に出席していたようです。
そんなある日、授業が終って、建物の外に出た所で、ぼくは、一人の女の子に再会したのです。もう、一年も会っていなかった。A子さんは、やはりここに通っていて、初級コースに入っているのだそうです。
「むづかして困ってんの、教えて」
懐かしさもあって、ぼくは、彼女と「再会」という名のキッサ店に行きました。いや別にカッコつけた訳ではなく、何となく入ったんです。
中級コースの優等生として、大いにのっていたぼくは、でかい面して、口うつしの発音練習をやりました。うす暗い、そのキッサ店の中で、真剣な表情で、たどたどしく、口をゆがめて後を追う彼女の唇が、奇妙にコケティッシュに映り、ぼくは、キスしたい衝動にかられたのでした。でも、以前とおんなじように、ぼくは真面目な態度で、一緒に帰りの電車に乗りました。
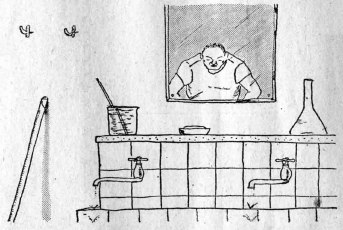 学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。
学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。昼頃、大学へ行くと、研究室を回って、「すまん、モクくれや」とタバコを集めます。十数本集めた所で、自分の部屋へ帰り、タバコを吸って、やってくる山岳部の後輩とだべっていると直ぐ夕方になってしまいます。その頃になると、いつも決って連れのダンボーが現われ、「よお、タカダ、どや、センターいこか」。センターというのは、ぼくたちの符牒で四条河原町あたりの事でした。
市電で行き着くと、もうその辺りは、通勤帰りのサラリーマンでラッシュでした。
「お前、金あるんやろ」
「ないぞ、お前ある思てた」
「アホか、出よかいうて誘うからあると思うやんケ」
でも、ダンボーは、少しもあわてず、「なんとかなる」と、そのまま、人の流れの中に立っているのです。ものの二〇分としないうちに、彼の知り合いが通りかかり、彼は、二人分のコーヒ代を貸りてしまいます。膳所高のラグビー部のエースだった彼には、沢山の友人がいるんだそうでした。
そこで、ぼく達は、いつものキッサ店にゆき、閉店近くまでねばります。それからまた大学にとって帰り、もう誰もいない、深夜の大学の冷たく光るガラス器具にとりまかれ、水道の滴の音だけが、チョポン、チョポンと異様に響く、少し不気味な感じの実験室で、一人実験を始めるのでした。
さて、あのキッサ店に、ウエイトレスとして、A子さんが現われたのは、もう卒論をまとめ始めていた頃だったと思います。
Comments