連載第1回「バンコックの40日」
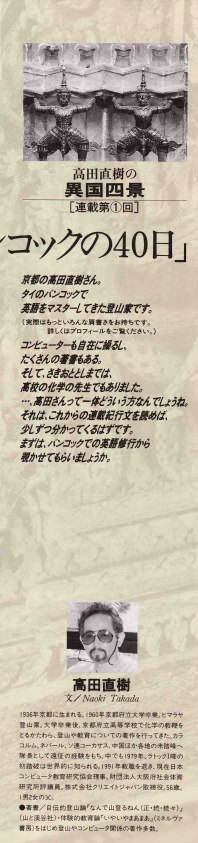 バンコックの空港に初めて降り立ったのは、もう28年も昔のことで最初のカラコルム登山の帰路のことでした。
バンコックの空港に初めて降り立ったのは、もう28年も昔のことで最初のカラコルム登山の帰路のことでした。お寺を見物に出かけると、総身金色の巨大な仏様が横ざまに横たわり、ニンマリと笑っていらっしゃった。なんじゃこれは。「裸のマハ」の化け物ではないか。つきつめた表情の阿修羅像やまこと静やかに物思う半伽思惟(はんかしい)の弥靭菩薩を好むぼくとしては、なんともいえぬ違和感を持たされてしまったのでした。
それにお線香といえば細い棒と思っていたのに、バカでかい蚊取線香みたいなお香の煙るバンコックのお寺はなんともけったいな感じ。どう考えてもぼくのバンコックの初印象はいいものではなかったといえます。
そのせいか、その後何度かバンコックを訪れる機会があったものの、さしてなじみを覚えるでもなく今日に至ったわけです。そのぼくがどうしたわけか、バンコックに40日間も滞在したのです。2年前のことでした。 考えるに人の人生には何度かある出来事が起こり、それによってその人の人生は決定的に変わる。その出来事は時には人の死であるかもしれないし、人との出会いであることもあるでしょう。
ぼくの場合、わが自伝的登山論『なんで山登るねん』の「三十なかば変身のきっかけはコーカサスのショック」でも書いたように、それはソ連コーカサスの風土とロシアの人々との出会いでした。そして二度目の決定的な出来事は、あのバンコック夏の40日ではなかったか。そんな気がするのです。翌年、かなり先の定年を残して、ぼくは30年間の教職生活に終止符を打つことになったのですから……。
ぼくは英語の勉強のためにバンコックに留学したのです。
大体ぼくの英語ときたら、パキスタン仕込みのもので、まあ普通の用事をこなすにはさして不自由はしないものの、一度しっかりと勉強し直さないといけないとずいぶん前から思っていたのです。それがコンピュータがらみでアメリカにいく用事ができてくると、ぼくの英語の再勉強への要請はかなり差し迫ったものとなったのでした。
ぼくは極めて流暢なウルド一語をあやつる数少ない日本人なのですが、何回かの遠征を通じてウルド一語を習得していった経験から、ぼくは「母国語が使えない環境が言語習得に必須」と固く信じているのです。一種の現地主義ともいえるでしょう。
だからアメリカ、ハワイなどというなかば遊び半分の日本人の大学留学生が群れているようなところは論外でした。それ以外のポイントは、滞在費、カリキュラムも重要です。いろいろ調べたり聞いたりした結果、浮かび上がったのは意外にもバンコックだったのです。
ぼくが選んだのはA・U・Aと呼ばれる有名な英語学校でした。American University Alumini Centerというのが正式名称です。アメリカ大学同窓会つまりアメリカの大学に留学したタイ人、そういう人は大体タイの指導者層なのですが、彼等が自分たちの子弟をアメリカの大学に留学させるための勉学塾を作ったのが始まりで、独自のメソッドと長い歴史をもっています。
英語だけではなくタイ語のコースもあり、朝7時から夜10時までに出入りする学生数はなんと延べ八千人に達するといいます。
 A・U・Aは夏に専門及び学術英語集中講座(Professional Academic lntensive Course)という特別コースを開講することが分かったのですが、このコースは特別なので試験があり、受験の申し込みも一カ月前の3日間に限られるというのです。これは尋常の手段では駄目だと判断したぼくは、春休みを待ってバンコックに飛んだのです。
A・U・Aは夏に専門及び学術英語集中講座(Professional Academic lntensive Course)という特別コースを開講することが分かったのですが、このコースは特別なので試験があり、受験の申し込みも一カ月前の3日間に限られるというのです。これは尋常の手段では駄目だと判断したぼくは、春休みを待ってバンコックに飛んだのです。門を入るとぼくはまっすぐに校長室に向かいました。ドアをノックすると女性の声が答え、入り口の部屋には秘書が大きなデスクに座っていました。ぼくはこの米国人のおばちゃんに、何故ここにきたか、何故A・U・Aで学びたいかをまくしたて、彼女は何のためにもっと英語を学びたいのか、日本ではどうして駄目なのか等と厳しく質問し、やりとりは十数分も続いたでしょうか。やがて彼女はメモ用紙に女性の名前を書いて渡し、「分かりました。今から学生課にいってこの人に相談なさい。電話しておきますから」と言ったのです。
かくてぼくの実力行動作戦は成功し、6月19〜21日の3日間のみの受験申し込みを特別に4月にやってしまうことができたのです。
試験の当日、前日から近くのバンコックリージェントホテルに投宿していたぼくは、ラーチャダムリ通りの歩道を歩いてA・U・Aに向かいました。
試験を受ける、受験するなどということはもういつ頃からやっていないのか覚えていないくらいのもので、少々の不安感とどちらかといえば心地よい緊張感があったのを記憶しています。
受験者は86名、講堂に整然と配置された机と椅子、緊張した受験者の表情、重苦しい雰囲気、これは聞いていたのとは違うぞとぼくは思い始めていました。
8時に始まったテストは、12時30分まで続きました。聞く、書く、読むの3パートで各100間ずつ、すべてマークシート方式でした。このテストがかの有名なTOEFL様のもので、さらに難度の高いものであることは後で知ったのです。
最初の「聞く」では少し焦ることもありましたが、まあなんとか通過。
「書く」は意外と余裕という感じで来たのですが、「読む」になって唖然としてしまいました。なにしろ一つの問題の英文の量が新聞の半ページほどもあるのです。
先立つこと一年間ほどの、『パスカル言語プログラミング』の本の執筆のために英文文献を読むという経験やアップルコンピュータ関係の文献や雑誌を読むという日常がなかったら、おそらくぼくは投げ出していたかもしれません。
2日後に発表がありました。合格者は23名。13名の上級クラスと10名の中級クラスの名簿が張ってあります。ぼくの名前は中級クラスにありました。ここにない人は集中コースには入れず通常コースに回されるのだそうです。
23日から授業が始まりました。朝の8時からの一講はReading/Writingつまり読み書きです。先生はジェフ・タッカーというシアトル生まれの人でシアトル大学林学科卒の35歳。トレッキング大好きでネパールヒマラヤに行きたいためにバンコックに住みつき、タイ人の奥さんをもらったというようなことは、後になって分かったことですが、とにかく山が好きだということで話が合ったのです。 翌年、彼は奥さんと一緒に来日し、ぼくの家にしばらく滞在しました。日本が気に入ったとシアトル大で英語の教員免許を取り直して再来日、現在北海道で朝日教養講座の教師をしています。
抱えてきたテキストを順に配り終わると、
「はい。私が合図したら読み始めなさい。同じところを二度読んではいけません。先へ先へどんどん進みなさい。時間は四分間です」 それでもう一度同じ行を読みたいのを我慢して先に進んで行き、ようやく半ページほどのところで、もう周りからパラ、パラというページをめくる音が聞こえるのです。ほんとに焦ったものです。
タッカーの毎日の作文の宿題は結構厳しくて、これをこなすのに最低4時間は必要でした。彼は、誤りの箇所とその種類を指摘するだけで決して訂正はせず、再提出がいつまでも続くのです。
もうひとりの先生は、英会話の先生でカティヤ先生。父親はトルコ人、母親はイラン人、そして生まれ育ったのはアメリカという人で回教徒。エリザベス・テーラーみたいな顔だちのかなり年配の美人でした。授業でミドルエイジを40から60と説明し、
「私たちはまだ中年じゃないわね。ねえ、ミスタータカダ」などと言ったのですが、タッカーによればぼくより年配だということでした。
毎日目の覚めるような色彩のプリントのタイシルクの服をまとい、ネックレスやイヤリング、指輪はいつも素敵なものを付けていらっしゃいました。
「タイ人はすぐに鼻や耳にさわるでしょ。アメリカでは絶対に触ってはいけないのよ。だって、鼻を触ったてで握手されたら困るでしょ」「アメリカでは黙っていてはいけないのよ。アメリカでは銃器の携帯が許されてるでしょ。みんなでしゃべってるときに一人黙っている人がいたら、みんなはその人が突如襲いかかるかもしれないと、恐怖するのよ。だから沈黙は罪悪なの」
日本の習慣や考え方についてしつこく質問され、毎時間苦しめられたのですが、彼女が教えようとしたのは、たんなる英会話ではなく、文化とその相対化であったように思います。
 クラス10人、みんなぼくの息子や娘くらいのクラスメートでした。全員が留学生試験に合格していて、行く先の大学もほとんど決まっている人達でした。女性は4人。タイ美人のシバナン・オンスリ愛称ジブ。2年勤めた銀行を考えるところあって辞め、9月からサンフランシスコの大学に行きます。シリポンはタイの東大・チュラロンコン大学の大学院の音楽科のフルート吹きなのですが、ニューョークのコンセルトバトルの研究生を目指しています。世界中から年にたった2人だけが選抜されるのだそうです。
クラス10人、みんなぼくの息子や娘くらいのクラスメートでした。全員が留学生試験に合格していて、行く先の大学もほとんど決まっている人達でした。女性は4人。タイ美人のシバナン・オンスリ愛称ジブ。2年勤めた銀行を考えるところあって辞め、9月からサンフランシスコの大学に行きます。シリポンはタイの東大・チュラロンコン大学の大学院の音楽科のフルート吹きなのですが、ニューョークのコンセルトバトルの研究生を目指しています。世界中から年にたった2人だけが選抜されるのだそうです。いわゆる外人はぼくとビルマ(ミャンマー)のミスター・ツーの二人だけでした。彼はメルボルン大学に入ることになっています。
男の子でぼくの一番の仲良しはピラニットといいました。彼はクラスでも一番出来る方で、タッカーがよくやった英語のクロスワードやクロスバーブ(動詞をうめる)パズルのコンペでは、ぼくと彼が組むといつも優勝しました。
彼は毎日、朝の7時30分にはぼくのアパートの前まで車で迎えにきてくれました。時にその車はベンツで、役人の父親が出張中で貸してくれたということでしたが、何回かはぼく達は、黒塗りのベンツで登校したのでした。
9月1日、集中コースが終了した時皆出席はぼく一人でした。タッカー先生とカティヤ先生からそれぞれに賞状を手渡されたときは正直にうれしかった。
バンコックの40日、それは遠く忘れていたような新しい体験であったという気がしています。